
職場で他の同僚は褒められているのに、自分だけ褒められないと感じることはありませんか。
同じように成果を出しているはずなのに、なぜか評価されていないように感じ、辛い気持ちや劣等感を抱いてしまうこともあるでしょう。
このような状況は、仕事へのモチベーション低下にもつながりかねません。
しかし、自分だけ褒められないと感じるのには、必ず何らかの理由や原因が存在します。
それは、あなた自身のコミュニケーションの取り方や、上司との関係性、あるいは自己肯定感の低さといった心理的な要因が関係しているのかもしれません。
また、職場環境や評価の基準が影響しているケースも考えられます。
このまま何もしなければ、辛い状況は変わらず、仕事に対する情熱を失ってしまう可能性さえあります。
大切なのは、なぜ自分だけ褒められないのか、その原因を正しく理解し、具体的な対策を講じることです。
この記事では、自分だけ褒められないと感じる原因を深掘りし、その背景にある心理や職場での人間関係について詳しく解説します。
さらに、その辛い状況から抜け出し、正当な評価を得るための具体的な方法や、周囲を気にしないための考え方まで、幅広くご紹介します。
- 自分だけ褒められない根本的な原因
- 褒められない背景にある心理的な要因
- 職場での人間関係やコミュニケーションの影響
- 劣等感や辛い気持ちへの具体的な対処法
- 自己肯定感を高めて状況を改善する方法
- 上司からの評価を得やすくなるポイント
- 周囲を気にしないための考え方のシフト
目次
自分だけ褒められない状況に隠された3つの原因
- 成果をアピールできていないという現実
- 上司や同僚との関係性が希薄な可能性
- 過度な承認欲求が辛さを増幅させる心理
- 仕事へのやる気を失い劣等感を抱く前に
- 褒められない人の行動に見られる共通点
成果をアピールできていないという現実

自分だけ褒められないと感じる最も一般的な原因の一つに、自分自身の成果を周囲に適切にアピールできていないという現実があります。
多くの真面目で誠実な人ほど、「仕事は黙って結果を出すものだ」「誰かが見ていてくれるはず」と考えがちです。
しかし、特に規模の大きな職場や、多忙な上司の下で働いている場合、一人ひとりの細かな成果をすべて把握するのは非常に困難でしょう。
上司は多くの部下をマネジメントしており、それぞれのタスクの進捗や貢献度を完璧に追跡できているわけではありません。
そのため、自分から積極的に報告やアピールをしないと、せっかくの努力や成果が埋もれてしまう可能性が高くなります。
例えば、プロジェクトの裏方として地道なデータ分析や資料作成を完璧にこなしたとしても、そのプロセスや貢献度を報告しなければ、最終的な成果物だけを見た上司にはその価値が十分に伝わらないかもしれません。
一方で、声高に成果をアピールする同僚がいた場合、たとえ貢献度が同じであったとしても、上司の印象には残りやすくなります。
これが、自分だけ褒められないという感覚につながるのです。
アピールというと、自己顕示欲が強いといったネガティブなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、ビジネスにおけるアピールは自己満足のためではなく、組織内での情報共有と正当な評価を得るための重要なコミュニケーションスキルです。
自分の仕事の価値を正しく相手に伝える努力を怠っていては、評価される機会を自ら手放しているのと同じことになります。
「これくらい言わなくても分かるだろう」という期待は、残念ながらビジネスの場では通用しないことが多いのです。
したがって、自分だけ褒められないと感じたら、まずは自分の成果や努力を客観的に伝えられているかどうかを振り返ってみる必要があります。
定期的な報告や、業務完了時のサマリー提出など、自分の仕事を「見える化」する工夫が求められるでしょう。
それは決して自慢話ではなく、自分の仕事に対する責任感の表れでもあるのです。
上司や同僚との関係性が希薄な可能性
職場で自分だけ褒められないと感じる背景には、上司や同僚との人間関係、つまり関係性が希薄であることが影響している可能性も考えられます。
人間は感情の生き物であり、どれだけ公平な評価を心がけていても、無意識のうちに親近感や好意を持っている相手を高く評価してしまう傾向があります。
これは心理学でいう「ハロー効果」の一種とも言えるでしょう。
つまり、普段から良好なコミュニケーションを築いている相手に対しては、その人の成果もポジティブに受け取りやすくなるのです。
もしあなたが、業務上の会話以外はほとんどせず、雑談やランチの誘いにも応じないなど、周囲との間に壁を作っているとしたら、それが原因であなたの成果が見過ごされているのかもしれません。
たとえ仕事で優れた結果を出していたとしても、上司から「何を考えているか分からない」「話しかけにくい」と思われていると、褒めるきっかけを掴みづらくなります。
逆に、普段から積極的にコミュニケーションを取り、自分の意見や考えを共有している人は、上司や同僚から人間的な興味を持たれやすく、その結果として仕事ぶりにも注目が集まりやすくなるのです。
例えば、業務の進捗報告をする際に、ただ事実を伝えるだけでなく、「この部分で少し苦労しましたが、工夫して乗り越えました」といった一言を添えるだけでも、相手に与える印象は大きく変わります。
これは、あなたの仕事への取り組み方や人柄を伝える絶好の機会です。
また、同僚との関係性も重要です。
チームで仕事を進める上で、協力的な姿勢を見せたり、他のメンバーの仕事に関心を示したりすることで、周囲からの信頼を得ることができます。
そうした信頼関係が、あなたの評価を間接的に高めることにもつながるでしょう。
自分だけ褒められないと感じるなら、一度自分のコミュニケーションスタイルを見直してみることをお勧めします。
挨拶や感謝の言葉をきちんと伝える、相手の話に興味を持って耳を傾けるといった基本的なことから始めるだけでも、周囲との関係性は少しずつ改善していくはずです。
人間関係の構築は、正当な評価を得るための土台作りとも言えるでしょう。
過度な承認欲求が辛さを増幅させる心理
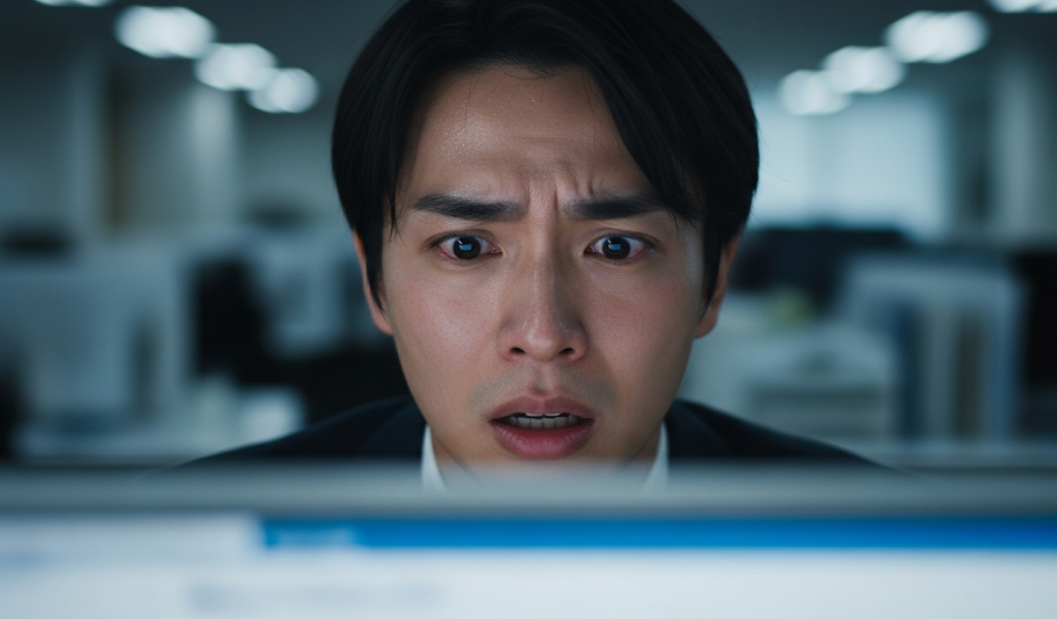
自分だけ褒められないという状況をことさらに辛く感じてしまう背景には、自分自身の心理状態、特に「過度な承認欲求」が隠れている場合があります。
承認欲求とは、「他者から認められたい」「価値ある存在だと思われたい」という、誰もが持つ自然な感情です。
しかし、この欲求が強すぎると、自分の価値を他者からの評価に依存してしまうようになります。
つまり、「褒められていない自分は価値がない」という思考に陥りやすくなるのです。
このような心理状態では、他人が褒められている場面を見るたびに、「それに比べて自分は…」と劣等感を抱き、強いストレスを感じてしまいます。
たとえ客観的に見て十分な成果を出していたとしても、他者からの明確な「褒め言葉」がなければ、自分自身でその成果を認めることができません。
自己肯定感が低く、自分に自信が持てない人ほど、この傾向は強くなります。
自分の内側に評価の軸がなく、常に他人の物差しで自分を測ろうとするため、褒められないという事実が、自分の存在そのものを否定されたかのように感じられてしまうのです。
この過度な承認欲求は、いくつかの問題を引き起こします。
他人の評価に一喜一憂する
褒められれば有頂天になる一方で、少しでも批判的な意見を言われたり、無視されたりすると、ひどく落ち込んでしまいます。
感情の起伏が激しくなり、精神的に不安定な状態が続くことになります。
周りの顔色ばかりうかがう
褒められることを目的として行動するようになるため、自分の意見や信念よりも、上司や同僚に気に入られることを優先してしまいます。
その結果、主体性のない、いわゆる「イエスマン」になってしまう危険性があります。
燃え尽き症候群のリスク
常に他者からの評価を求め続けることは、精神的に大きなエネルギーを消耗します。
どれだけ頑張っても期待した評価が得られない状況が続くと、やがて心身ともに疲れ果て、無気力状態に陥ってしまうことも少なくありません。
自分だけ褒められないという悩みの根源が、実は自分の内側にある過度な承認欲求かもしれないと気づくことは、問題解決の第一歩です。
他者からの評価を求める前に、まずは自分自身が自分の努力や成果を認め、褒めてあげることが重要になります。
自分の価値は、他人が決めるものではないという認識を持つことが、この辛さから抜け出す鍵となるでしょう。
仕事へのやる気を失い劣等感を抱く前に
自分だけ褒められないという状況が続くと、仕事に対するモチベーション、つまり「やる気」が著しく低下してしまう危険性があります。
人間は、自分の行動が認められたり、評価されたりすることで、次も頑張ろうという意欲が湧くものです。
この「認められる」という経験が欠如すると、次第に「何のために頑張っているのだろう」「どうせやっても無駄だ」というネガティブな感情が芽生え始めます。
最初は小さな不満だったものが、日々の積み重ねによって、やがては仕事全体に対する無関心や虚しさへと発展していきます。
そうなると、業務の質が低下したり、新たな挑戦を避けたりと、実際のパフォーマンスにも悪影響が出始めます。
これは、負のスパイラルに陥る入り口と言えるでしょう。
さらに深刻なのは、やる気の低下と同時に「劣等感」が心を蝕んでいくことです。
同僚が上司から褒められているのを見るたびに、自分とその同僚を比較し、「自分はあの人よりも劣っている」「自分には才能がないんだ」と思い込んでしまいます。
この劣等感が強くなると、職場にいること自体が苦痛になり、出社するのが億劫になったり、人と顔を合わせるのが怖くなったりすることさえあります。
また、劣等感は自信を喪失させ、本来持っている能力の発揮を妨げます。
「どうせ自分なんて…」という思い込みが、プレゼンテーションでの発言を躊躇させたり、新しいアイデアの提案をためらわせたりするのです。
その結果、ますます評価されにくい状況を自ら作り出してしまうという悪循環に陥ります。
このような状態になる前に、早急な対策が必要です。
「最近、仕事がつまらない」「同僚の成功を素直に喜べない」と感じたら、それは心が発している危険信号かもしれません。
その信号を無視し続けると、やがてはメンタルヘルスに不調をきたし、休職や離職といった事態につながる可能性も否定できません。
自分だけ褒められないという悩みは、単なる気分の問題ではなく、あなたのキャリアや心身の健康に直結する重要な課題なのです。
手遅れになる前に、なぜそのような状況が起きているのかを冷静に分析し、具体的な行動を起こすことが何よりも大切です。
褒められない人の行動に見られる共通点

自分だけ褒められないと悩んでいる人々の行動や思考パターンには、いくつかの共通点が見られることがあります。
もし、あなたがこれらの特徴に当てはまるのであれば、それが褒められない状況を生み出す一因となっているのかもしれません。
自分自身を客観的に見つめ直し、改善のヒントを探ってみましょう。
まず挙げられるのが、「報告・連絡・相談(報連相)」が不足しているという点です。
特に、途中経過の報告を怠る傾向があります。
自分の中では順調に進んでいるつもりでも、上司から見れば「あの件はどうなっているだろう?」と不安に感じているかもしれません。
完了報告だけでなく、定期的に進捗を伝えることで、上司は安心感を得ると同時に、あなたの仕事への真摯な姿勢を評価するでしょう。
次に、自己完結しすぎてしまい、周囲に助けを求めないという特徴もあります。
責任感が強い人ほど、「自分の力で何とかしなければ」と考えがちですが、一人で抱え込む姿勢は、時としてチームワークを阻害し、「協調性がない」と見なされることもあります。
適切なタイミングで相談することは、自分の弱みを見せることではなく、問題を早期に解決し、プロジェクトを円滑に進めるための賢明な判断です。
また、表情が硬かったり、リアクションが薄かったりすることも、損をしている可能性があります。
話しかけられても素っ気ない態度を取ってしまうと、相手は「自分は歓迎されていないのでは」と感じ、徐々に距離を置くようになります。
たとえ内面では感謝や喜びを感じていたとしても、それが表情や態度に表れなければ、相手には伝わりません。
意識的に口角を上げたり、相槌を打ったりするだけでも、印象は大きく改善されます。
さらに、ネガティブな発言が多いというのも共通点の一つです。
「でも」「だって」「どうせ」といった言葉が口癖になっていないでしょうか。
このような否定的な言葉は、周囲のやる気を削ぐだけでなく、「この人は物事を前向きに捉えられないのだな」という印象を与えてしまいます。
たとえ困難な状況であっても、「どうすればできるか」という建設的な視点で物事を語る人の方が、応援され、評価されやすいのは当然のことです。
これらの共通点は、決してあなたの能力が低いことを意味するものではありません。
多くは、少しの意識と行動で改善できるコミュニケーションの癖や習慣です。
自分だけ褒められない現状を嘆く前に、まずは自分の日頃の言動を振り返り、改善できる点がないか探してみることが、状況を打開する第一歩となるでしょう。
自分だけ褒められない悩みから抜け出すための具体的な方法
- まずは小さな成功体験で自己肯定感を高める
- 周囲の評価を気にしない考え方を持つ
- 積極的なコミュニケーションで関係を改善
- 自分の価値観を大切にする自己評価の習慣
- 自分だけ褒められない状況を乗り越えるために
まずは小さな成功体験で自己肯定感を高める

自分だけ褒められないという悩みから抜け出すための第一歩は、他者からの評価に依存するのではなく、自分自身の内側から自信を育むことです。
その最も効果的な方法が、「小さな成功体験」を積み重ねて自己肯定感を高めることでしょう。
自己肯定感とは、「ありのままの自分を肯定し、価値ある存在として受け入れる感覚」のことです。
これが低いと、他人の評価がなければ自分を認められず、褒められない状況に過剰に苦しむことになります。
大きな目標を掲げることも大切ですが、それだけでは達成までに時間がかかり、途中で挫折してしまうリスクもあります。
そこで重要になるのが、日々の業務の中に、自分でコントロール可能で、確実に達成できる小さな目標を設定することです。
例えば、以下のようなものが考えられます。
- 午前中のうちに、今日のタスクリストをすべて洗い出す
- 会議で一度は必ず発言する
- 普段話さない同僚に、自分から挨拶して雑談を一つする
- 退社前に、15分かけて明日の準備を完璧に整える
これらの目標は、どれも難しいものではありません。
しかし、「自分で決めたことを、自分で実行できた」という事実は、紛れもない「成功体験」です。
そして、この小さな成功を一つひとつクリアしていくたびに、「自分はやればできるんだ」という感覚が、潜在意識に刷り込まれていきます。
ポイントは、達成できたことを可視化することです。
手帳やノートに達成した目標を書き出し、チェックマークを付けていくと、自分の頑張りが目に見えて、より達成感を味わうことができます。
夜寝る前に、その日達成できたことを3つ書き出す「成功日記」も効果的です。
このプロセスを繰り返すうちに、あなたの自己評価は、徐々に他人の言動に左右されない、安定したものへと変わっていきます。
自分の中に確固たる自信の土台ができてくると、たとえ他人から褒められなくても、必要以上に落ち込んだり、自分を卑下したりすることがなくなります。
むしろ、「自分は自分の基準で、しっかりと前に進んでいる」という静かな満足感を得られるようになるでしょう。
自己肯定感が高まると、表情や態度にも自信が表れ、それが周囲からの評価を変えるきっかけになることも少なくありません。
まずは、今日から始められる小さな目標を一つ、設定してみてはいかがでしょうか。
周囲の評価を気にしない考え方を持つ
自分だけ褒められないという悩みから解放されるためには、周囲の評価を過剰に気にしないという、ある種の「鈍感力」を身につけることも非常に重要です。
もちろん、他者からのフィードバックは成長のために不可欠ですが、それに振り回されすぎていては、自分らしいパフォーマンスを発揮することはできません。
ここで大切なのは、課題の分離という考え方です。
これは、アドラー心理学で提唱されている概念で、「自分の課題」と「他者の課題」を明確に分けることを指します。
あなたが仕事で成果を出すために努力するのは「自分の課題」です。
しかし、その成果を上司がどう評価し、褒めるか褒めないかというのは、あなたにはコントロールできない「他者の課題」なのです。
私たちは、他人の感情や行動を直接コントロールすることはできません。
それならば、自分がコントロールできないことで悩むのはやめて、自分がコントロールできる「自分の課題」に集中する方が、はるかに建設的です。
「自分はやるべきことをやった。
評価は相手が決めること」と割り切ることで、精神的な負担は大きく軽減されます。
また、視点を変えてみることも有効です。
褒めてくれない上司は、もしかしたら「部下を褒めて育てる」というスタイルを持っていないだけかもしれません。
あるいは、人前で個人を褒めることを良しとしない文化の職場で育ってきた可能性もあります。
つまり、褒められないのは、あなたの能力の問題ではなく、単に上司のスタイルや価値観の問題である可能性も十分にあるのです。
そう考えると、褒められないことに対して、それほど深刻に悩む必要はないと思えてくるのではないでしょうか。
さらに、「評価の多様性」を認識することも心を軽くします。
あなたを褒めない上司がいる一方で、あなたの仕事ぶりを正当に評価してくれる同僚や、他の部署の人がいるかもしれません。
たった一人の評価が、あなたの全てを決めるわけではないのです。
視野を広げ、社内のさまざまな人と関わることで、多様なフィードバックを得る機会が増え、特定の個人の評価に固執することが少なくなります。
周囲の評価を気にしないというのは、独りよがりになることではありません。
他者の意見に耳を傾けつつも、最終的な自分の価値は自分で決めるという、健全な自己肯定感に基づいたスタンスのことです。
この考え方を身につけることで、あなたはもっと自由に、そして力強く、自分の仕事に取り組むことができるようになるでしょう。
積極的なコミュニケーションで関係を改善

自分だけ褒められない状況を打開するための、最も直接的で効果的な行動の一つが、積極的なコミュニケーションによって周囲との関係性を改善することです。
前述の通り、人は良好な関係を築いている相手に対して、ポジティブな注意を向けやすいという性質があります。
関係性の改善は、あなたの努力や成果が正しく認識され、評価されるための土壌を耕す作業と言えるでしょう。
では、具体的にどのようなコミュニケーションを心がければ良いのでしょうか。
まずは、基本的な「報連相(報告・連絡・相談)」の質と量を向上させることから始めましょう。
報告の工夫
仕事の完了報告だけでなく、進捗状況をこまめに伝えることが重要です。
特に、上司が気にしているであろう案件については、週に一度、あるいは数日に一度、簡単なサマリーをメールやチャットで送るだけでも、「きちんと考えて行動しているな」という印象を与えられます。
報告の際には、単なる事実だけでなく、「この部分は計画通りですが、次のステップで少し課題がありそうです」といった見通しや、「〇〇さんの協力のおかげでスムーズに進みました」といった感謝を付け加えると、より深みのあるコミュニケーションになります。
連絡の徹底
些細なことでも、関係者に影響がありそうな情報は、早めに共有する癖をつけましょう。
情報共有の速さと正確さは、信頼の基本です。
「知らなかった」という事態を未然に防ぐことで、あなたは「安心して仕事を任せられる人」という評価を得ることができます。
相談のスキル
一人で抱え込まず、適切なタイミングで上司や同僚に相談することも、重要なコミュニケーションです。
相談する際は、ただ「どうすればいいですか?」と丸投げするのではなく、「自分はこう考えているのですが、ご意見をいただけますか?」という形で、自分の考えを添えることがポイントです。
これにより、あなたの主体性を示すと同時に、相手も的確なアドバイスをしやすくなります。
業務上のコミュニケーションに加えて、日常的な雑談も関係性構築には欠かせません。
ランチに誘ってみたり、相手の趣味や週末の過ごし方について質問してみたりと、少しずつで良いので、個人的な関心を示すようにしましょう。
相手の人間性を知ることで、あなたに対する親近感が湧き、仕事上のやり取りも円滑になります。
重要なのは、相手からのアクションを待つのではなく、自分から主体的に働きかけることです。
最初は勇気がいるかもしれませんが、挨拶に一言添える、エレベーターで一緒になった時に話しかけるなど、小さな一歩から始めてみましょう。
その積み重ねが、やがては職場におけるあなたの存在感と評価を、着実に高めていくことになるはずです。
自分の価値観を大切にする自己評価の習慣
他者からの評価に一喜一憂する状態から抜け出し、自分だけ褒められないという悩みと決別するためには、最終的に「自分自身の価値観に基づいた評価軸」を確立することが不可欠です。
これは、他人の物差しではなく、自分の物差しで自分の仕事ぶりや成長を測る習慣を身につけることを意味します。
まず、あなたにとって「良い仕事」とは何かを定義してみましょう。
それは、単に売上や数字といった結果だけでしょうか。
もしかしたら、「新しいスキルを習得できたこと」「チームの誰かを助けることができたこと」「以前よりも効率的に作業を進められたこと」といったプロセスの中に、あなたならではの価値を見出すことができるかもしれません。
自分が仕事において何を大切にしたいのか、どのような状態でありたいのかを明確にすることで、他人の評価とは独立した、自分だけの満足感や達成感を得る基準が生まれます。
次に、その価値観に基づいて、定期的に自分自身を振り返る「自己評価」の時間を設ける習慣をつけましょう。
週に一度、あるいは一日の終わりに、手帳や日記に次のようなことを書き出してみるのがお勧めです。
- 今週、自分が設定した価値観に沿って行動できたことは何か?
- どのような点で成長できたか、新しい学びはあったか?
- うまくいかなかったことは何か、その原因と次への改善点は?
- 自分自身を褒めてあげたい点はどこか?
このプロセスのポイントは、他人との比較ではなく、過去の自分との比較に焦点を当てることです。
「先週よりも報告がうまくできるようになった」「1ヶ月前にはできなかった業務が、今は一人でできるようになった」というように、自分自身の成長の軌跡を確認することで、着実に前に進んでいるという実感を得ることができます。
この実感こそが、外部からの評価がなくても揺らがない、本物の自信の源泉となります。
そして、自己評価の結果、自分を褒めてあげたい点が見つかったら、心から自分を労い、認めてあげてください。
「よく頑張ったね」「この部分は本当に素晴らしかった」と、自分自身の一番の理解者になってあげるのです。
この習慣が身につくと、あなたはもはや、上司から褒め言葉をもらうことを必死に追い求める必要がなくなります。
なぜなら、誰よりも自分の頑張りを知っている自分自身が、最高の評価者になっているからです。
もちろん、他者からの評価が不要になるわけではありません。
しかし、それはあくまで数あるフィードバックの一つとして客観的に受け止め、自分の成長の糧にするための参考情報となります。
自分の価値観という羅針盤を持つことで、あなたは評価という荒波に翻弄されることなく、着実に自分の目指す港へと進んでいくことができるようになるでしょう。
自分だけ褒められない状況を乗り越えるために

これまで、自分だけ褒められないと感じる原因と、その辛い状況から抜け出すための具体的な方法について考察してきました。
原因は、成果のアピール不足やコミュニケーションの問題、あるいは自分自身の心理状態など、多岐にわたることがお分かりいただけたかと思います。
そして、対処法もまた、自己肯定感を高める内面的なアプローチから、関係性を改善する外面的なアプローチまで、さまざまな側面からの取り組みが必要となります。
重要なのは、これらの原因や対処法を知識として知るだけでなく、実際に行動に移してみることです。
この記事で紹介した方法の中から、今の自分にできそうなことを一つでも二つでも選び、今日から実践してみてください。
最初は小さな変化しか感じられないかもしれません。
しかし、その一歩が、確実にあなたの状況を好転させるきっかけとなります。
成果のアピール方法を見直せば、あなたの努力が上司の目に留まるようになります。
積極的なコミュニケーションを心がければ、周囲との関係が改善され、職場がより居心地の良い場所になるでしょう。
そして何よりも、自分自身で自分を認め、評価する習慣を身につけることができれば、他人の言動に心を揺さぶられることが少なくなり、穏やかで力強い心を保つことができます。
自分だけ褒められないという悩みは、決してあなた一人が抱える特殊なものではありません。
多くの人が、キャリアのどこかの段階で同じような壁にぶつかります。
しかし、この悩みは、あなたに自分自身と向き合い、コミュニケーションスキルや自己肯定感といった、ビジネスパーソンとして、そして一人の人間として成長するための大切な機会を与えてくれているとも言えるのです。
この状況を、単なる「辛い時期」としてやり過ごすのではなく、「自分を成長させるための転機」と捉え、前向きに取り組んでみてはいかがでしょうか。
あなたの努力と工夫次第で、未来は必ず変えられます。
この記事が、あなたがその一歩を踏み出すための、ささやかな後押しとなれば幸いです。
- 自分だけ褒められない悩みは多くの人が抱える
- 原因はアピール不足やコミュニケーションにある
- 過度な承認欲求が辛さを増幅させている可能性
- まずは客観的に自分の行動を振り返ることが重要
- 上司や同僚との関係性を見直す
- 日頃から成果を適切に報告する習慣をつける
- 自己肯定感を高めるために小さな成功を意識する
- 他者評価ではなく自己評価の軸を持つ
- 周囲の評価を気にしない考え方も一つの手段
- 劣等感を感じたら一度立ち止まり原因を探る
- 積極的なコミュニケーションが状況を好転させる
- 自分の価値観を大切に仕事に取り組む
- 辛い気持ちは一人で抱え込まず信頼できる人に相談
- 褒められること自体が目的にならないように注意
- 自分自身の成長を実感することが最も大切






