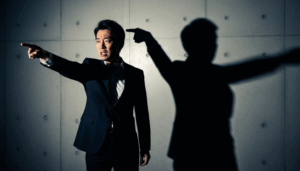かつては活き活きと業務に取り組んでいた優秀な部下が、最近どうも元気がない、と感じることはありませんか。
優秀な部下がやる気をなくすという状況は、多くの管理職が直面する深刻な問題です。
この問題の背後には、単純な疲れだけではない、複雑な理由が隠されていることが少なくありません。
部下のモチベーション低下には、明確なサインが現れることが多く、その原因を理解することが解決の第一歩となります。
上司として、部下の変化に気づきながらも、どのように対処法を講じればよいか分からず、悩んでいる方もいるでしょう。
そこには、上司自身の何気ない言動や、無意識のNG行動が関わっている可能性も考えられます。
また、仕事の与え方、日々のコミュニケーションの質、そして納得感のある評価制度など、職場環境全体が部下の意欲に大きく影響を与えているのです。
この記事では、優秀な部下がやる気をなくすという問題に焦点を当て、その根本的な原因から具体的な対処法までを網羅的に解説していきます。
- 優秀な部下がやる気をなくす根本的な理由
- 部下のモチベーション低下を示す危険なサイン
- 上司が避けるべき具体的なNG行動
- 部下の意欲を再燃させるための対処法
- 信頼を築くためのコミュニケーションの取り方
- 成長を促す仕事の任せ方と評価方法
- 優秀な人材の離職を防ぐ職場環境づくり
目次
優秀な部下がやる気をなくす根本的な原因
- 部下が見せるモチベーション低下の危険なサイン
- 優秀な部下の意欲を削ぐ上司のNG行動とは
- 不公平感が生まれる評価制度とその問題点
- 単調な仕事がもたらす成長機会の喪失という理由
- 優秀な人材の離職を招く職場環境の特徴
部下が見せるモチベーション低下の危険なサイン

優秀な部下がやる気をなくす時、その変化は日々の業務態度や行動に微細ながらも明確なサインとして現れます。
これらのサインを早期に察知し、適切に対応することが、問題の深刻化を防ぐ鍵となるでしょう。
上司として、部下の日々の様子を注意深く観察することが求められます。
以前より会議での発言が減る
最も分かりやすいサインの一つが、会議やディスカッションの場での発言数の減少です。
以前は積極的に意見を述べ、議論をリードしていた部下が、口数が少なくなり、ただ黙って聞いているだけになるケースが見られます。
これは、自分の意見が評価されない、あるいは聞いてもらえないと感じていることの表れかもしれません。
貢献意欲の低下や、組織への関心の喪失を示唆する危険な兆候と言えるでしょう。
単に体調が悪い、あるいはプライベートで悩みを抱えている可能性も考えられますが、この状態が続くようであれば注意が必要です。
新しい仕事への挑戦を避けるようになる
優秀な人材は、本来、知的好奇心が旺盛で、自己の成長につながる新しい挑戦を歓迎する傾向にあります。
しかし、やる気を失い始めると、これまで喜んで引き受けていたような難易度の高い仕事や新しいプロジェクトへの関与を避けるようになります。
「今の業務で手一杯です」といった理由で断ったり、自ら手を挙げなくなったりするのは、失敗を恐れているか、あるいは努力が正当に評価されないと感じている可能性があります。
このような行動は、成長意欲の減退を示す重要なサインであり、放置すれば能力の停滞にもつながりかねません。
遅刻や欠勤が増え、業務の質が低下する
モチベーションの低下は、勤怠の乱れや業務パフォーマンスの悪化として現れることもあります。
以前は時間管理が徹底できていた部下が、遅刻や急な欠勤を繰り返すようになったり、提出物の期限を守れなくなったりするのは、仕事への責任感やエンゲージメントが低下している証拠かもしれません。
また、ケアレスミスが増える、資料の作り込みが甘くなるなど、アウトプットの質が明らかに低下した場合も、注意深く見守る必要があります。
これらのサインは、精神的な疲弊や、会社への帰属意識の低下を示している可能性が高いと考えられます。
部下の些細な変化を見逃さず、早期に対話の機会を持つことが、問題解決への第一歩となるのです。
優秀な部下の意欲を削ぐ上司のNG行動とは
優秀な部下がやる気をなくす背景には、多くの場合、上司のマネジメントスタイルや日々の言動が深く関わっています。
上司としては良かれと思って取った行動が、部下の自尊心や成長意欲を奪っているケースは少なくありません。
ここでは、特に注意すべき上司のNG行動について具体的に解説します。
マイクロマネジメントで部下の裁量を奪う
マイクロマネジメントとは、上司が部下の業務の細部にまで過剰に干渉し、逐一報告を求めたり、指示を出したりする管理手法です。
特に優秀な部下は、自律的に仕事を進め、自分の判断で創意工夫を凝らすことにやりがいを感じています。
それに対して、上司が細かく口を出し、裁量権を奪ってしまうと、部下は「自分は信頼されていない」と感じ、仕事への主体性を失ってしまいます。
結果として、指示待ちの状態に陥り、パフォーマンスの低下を招くことになるでしょう。
部下を信頼し、責任と共に権限を委譲することが、成長を促す上で不可欠です。
成果を正当に評価せず、褒めない
人は誰でも、自分の努力や成果を認められたいという承認欲求を持っています。
優秀な部下が大きな成果を上げたにもかかわらず、それを当然のこととして扱ったり、適切なフィードバックや称賛を怠ったりすると、部下のモチベーションは著しく低下します。
「頑張っても誰も見てくれない」「正当に評価されない」という無力感は、やがて仕事への情熱を冷めさせてしまいます。
また、成果を上司自身の手柄のように報告する行為は、部下の信頼を完全に失わせる最悪の行動と言えるでしょう。
具体的な指示やフィードバックをしない
マイクロマネジメントとは対照的に、部下を放置しすぎることも問題です。
いわゆる「丸投げ」と呼ばれる状態で、業務の目的や背景を十分に説明せず、具体的な指示や期待する成果物についてのすり合わせを怠ると、部下は何をすれば良いのか分からず、不安を感じます。
また、業務の進捗や成果物に対して、具体的なフィードバックがない場合も同様です。
部下は自分の仕事が良いのか悪いのか判断できず、成長の機会を失ってしまいます。
適切な放任と、要所での的確なサポートやフィードバックのバランスが、部下の自律的な成長を支えるのです。
これらのNG行動は、上司の無意識のうちに行われていることも多いため、自身のマネジメントスタイルを定期的に振り返り、改善していく姿勢が求められます。
不公平感が生まれる評価制度とその問題点

優秀な部下がやる気をなくす大きな要因の一つに、評価制度に対する不満や不公平感が挙げられます。
どれだけ熱心に仕事に取り組み、高い成果を上げたとしても、その努力や貢献が評価に正しく反映されなければ、部下の心は離れていくでしょう。
ここでは、評価制度に潜む問題点について深掘りします。
評価基準の曖昧さと不透明性
評価の基準が曖昧であったり、評価プロセスが不透明であったりすると、部下は「何を頑張れば評価されるのか」が分からず、目標設定が困難になります。
例えば、「協調性」や「積極性」といった定性的な項目が、具体的な行動目標に落とし込まれずに評価基準となっている場合、評価が上司の主観や印象に左右されやすくなります。
部下からすれば、「上司に気に入られているかどうかで評価が決まる」という不信感につながりかねません。
評価基準は誰が見ても理解できるよう具体的かつ客観的であるべきで、その基準や評価プロセスは全社員に公開され、透明性が確保されている必要があります。
成果だけでなくプロセスを無視した評価
結果主義が行き過ぎると、成果に至るまでのプロセスや努力が軽視される傾向にあります。
もちろん、ビジネスである以上、最終的な成果は重要です。
しかし、難易度の高い課題に挑戦し、たとえ結果的に失敗に終わったとしても、その過程で得た学びやチームへの貢献は評価されるべきでしょう。
プロセスを無視して結果だけで判断すると、社員は失敗を恐れて挑戦を避けるようになり、組織全体の成長が阻害されます。
優秀な部下ほど、困難な課題に意欲的に取り組むため、プロセス評価の欠如は彼らの挑戦意欲を削ぐ大きな原因となります。
フィードバックの欠如と一方的な通達
評価制度が単なる「査定」のツールとして機能し、給与や昇進を決めるためだけの一方的な通達に終わっている場合、それは部下の成長機会を奪うことになります。
評価の結果を伝える面談の場で、具体的な根拠や改善点についての丁寧なフィードバックがなければ、部下は結果に納得できず、次に何をすべきか分かりません。
評価面談は、部下の貢献を称え、課題を共有し、今後の成長に向けた対話を行うための貴重な機会です。
上司は、評価期間中の具体的なエピソードを交えながら、客観的な事実に基づいてフィードバックを行い、部下の自己認識とのギャップを埋める努力をすべきです。
納得感のある評価と、成長につながるフィードバックこそが、部下のエンゲージメントを高め、組織全体のパフォーマンスを向上させるのです。
単調な仕事がもたらす成長機会の喪失という理由
優秀な部下は、自己の成長を強く望む傾向があります。
彼らにとって、仕事は単なる収入を得るための手段ではなく、自身のスキルや能力を高め、キャリアを築いていくための重要な舞台です。
しかし、与えられる仕事が常に同じことの繰り返しであったり、自身の能力を持て余すような簡単な業務ばかりであったりすると、彼らは成長の機会が失われていると感じ、次第にモチベーションを低下させていきます。
ルーティンワークによるマンネリ化
どんな仕事にも、ある程度のルーティンワークはつきものです。
しかし、その割合が極端に多く、創造性や思考力を働かせる余地のない業務ばかりが続くと、優秀な部下はすぐに飽きてしまいます。
彼らは、常に新しい知識を吸収し、スキルを磨きたいと考えているため、単調な作業の繰り返しは知的な刺激が乏しく、苦痛にさえ感じることがあります。
この「マンネリ化」は、仕事への情熱を徐々に蝕んでいく静かなる脅威です。
上司は、部下の能力や志向を理解し、意図的に新しい挑戦の機会や、業務改善の裁量を与えることで、マンネリ化を防ぐ工夫が求められます。
能力と業務内容のミスマッチ
高いポテンシャルを持つ優秀な部下に対して、その能力に見合わない簡単な仕事ばかりを与え続けることも、やる気を削ぐ大きな原因となります。
例えば、戦略的な思考が得意な部下にデータ入力ばかりを任せたり、高い専門知識を持つ部下に雑務ばかりを押し付けたりするケースです。
このような状況は、部下にとって「自分の能力が正当に評価されていない」「この職場では成長できない」というメッセージとして受け取られかねません。
自分の強みや能力を活かせない環境は、自己肯定感の低下を招き、最終的にはより成長できる環境を求めての離職につながる可能性が高まります。
上司は、部下一人ひとりの能力やキャリアプランを把握し、少し背伸びすれば届くような、挑戦的でストレッチな目標設定や業務のアサインを意識することが重要です。
それが、優秀な部下の成長意欲を刺激し、組織への貢献度を最大化する道筋となるでしょう。
優秀な人材の離職を招く職場環境の特徴

優秀な部下がやる気をなくす問題は、個人の問題や上司との関係性だけでなく、部署や会社全体の職場環境に根差している場合も少なくありません。
従業員のエンゲージメントを低下させ、特に優秀な人材の流出を招きやすい職場環境には、いくつかの共通した特徴が見られます。
自社の環境がこれらに当てはまっていないか、客観的に見直すことが重要です。
挑戦を許容せず、失敗を責める文化
新しいアイデアや挑戦に対して、前向きに受け止める姿勢がなく、むしろ否定的な態度を取るような職場では、従業員の創造性や自発性は育ちません。
特に、一度の失敗を厳しく追及し、責任を個人に押し付けるような文化が根付いている場合、社員は萎縮してしまいます。
「余計なことをして怒られるくらいなら、言われたことだけをやっていた方が安全だ」という思考に陥り、誰もリスクを取らなくなります。
優秀な人材ほど、現状維持に満足せず、新しい価値を創造しようと試みるものです。
彼らの挑戦意欲を削ぎ、成長の機会を奪うような環境は、優秀な人材にとって魅力的ではありません。
心理的安全性が確保され、失敗から学ぶことを奨励する文化の醸成が不可欠です。
情報がクローズドで、風通しが悪い
会社のビジョンや経営状況、重要な意思決定のプロセスといった情報が、一部の経営層や管理職だけで共有され、現場の従業員に開示されない職場は、従業員の間に不信感や疎外感を生みます。
自分が何のためにこの仕事をしているのか、会社の向かう先が見えない状況では、仕事への意義や目的意識を見出すことは難しいでしょう。
また、部署間の連携が悪く、セクショナリズムが蔓延しているような環境も問題です。
風通しの悪い職場では、建設的な意見や問題提起がしにくく、社員は無力感を抱きがちになります。
情報の透明性を高め、オープンなコミュニケーションを促進することが、従業員の当事者意識とエンゲージメントを高める上で重要となります。
従業員のキャリア開発への無関心
会社が従業員の長期的なキャリア形成や成長を支援する姿勢を示さない場合、優秀な人材は「この会社にいても未来はない」と判断し、離職を選択する可能性が高まります。
研修制度が整っていなかったり、多様なキャリアパスが用意されていなかったりする状況は、成長意欲の高い従業員にとって大きな不満となります。
また、上司が部下のキャリア相談に乗らなかったり、個人の希望を無視した異動を強行したりすることも、信頼関係を損なう原因です。
従業員一人ひとりのキャリア開発を組織として支援し、成長の機会を提供し続けることが、優秀な人材を惹きつけ、定着させるための重要な投資と言えるでしょう。
優秀な部下がやる気をなくす状況の具体的な対処法
- まず見直すべきは上司とのコミュニケーション
- 部下の強みを引き出す効果的な仕事の任せ方
- 正当な評価を伝え本人の納得感を高める
- モチベーションを再燃させるための具体的な対処法
- 優秀な部下がやる気をなくす悪循環を断ち切るために
まず見直すべきは上司とのコミュニケーション

優秀な部下がやる気をなくすという問題に直面した時、上司がまず着手すべきなのは、部下とのコミュニケーションのあり方を根本から見直すことです。
多くの問題は、コミュニケーションの不足や質の低さに起因しています。
信頼関係を再構築し、部下の本音を引き出すための対話が、解決への道を切り開きます。
1on1ミーティングの定期的な実施
日々の業務連絡だけでは、部下が抱える悩みやキャリアに対する考えを深く理解することは困難です。
そこで有効なのが、週に1回あるいは隔週に1回、30分程度の1on1ミーティングを定期的に実施することです。
この時間は、業務の進捗確認の場ではなく、部下のための時間と位置づけ、部下が話したいことを自由に話せる雰囲気を作ることが重要となります。
上司は聞き役に徹し、傾聴と質問を通じて、部下の現状や考えていることを深く理解しようと努めるべきです。
プライベートの悩み、キャリアの展望、現在の仕事に対する思いなど、テーマを限定せずにオープンな対話を心がけることで、部下は徐々に心を開いてくれるでしょう。
傾聴と承認を基本とした対話姿勢
コミュニケーションにおいて、上司が自分の意見を一方的に話したり、部下の話を途中で遮ってアドバイスを始めたりするのは逆効果です。
まずは、部下の話を最後まで真摯に聴く「傾聴」の姿勢が求められます。
相手の言葉だけでなく、その背景にある感情や意図まで汲み取ろうとすることが大切です。
そして、部下の意見や感情を、たとえ自分と違ったとしても、まずは「そう思うんだね」と一度受け止める「承認(アクノリッジメント)」の姿勢を示します。
これにより、部下は「自分のことを理解しようとしてくれている」と感じ、心理的な安全性が確保されます。
この信頼関係が、本音での対話の土台となるのです。
高圧的な態度や頭ごなしの否定は、部下の心を固く閉ざしてしまうことを肝に銘じる必要があります。
期待と感謝を具体的に言葉で伝える
優秀な部下であっても、自分が組織から何を期待されているのか、自分の仕事がどのように貢献しているのかを常に確認したいと思っています。
上司は、「君にはこの分野でリーダーシップを発揮してほしい」「このプロジェクトの成功は君の力にかかっている」といったように、期待する役割や成果を具体的に言葉で伝えるべきです。
これにより、部下は自分の役割を明確に認識し、目標に向かって主体的に行動しやすくなります。
また、日々の業務の中で、部下が上げた成果や良い行動に対して、「ありがとう、助かったよ」「この視点は素晴らしいね」といった感謝や称賛の言葉をタイムリーに伝えることも極めて重要です。
これらのポジティブなフィードバックが、部下の承認欲求を満たし、仕事へのモチベーションを維持する原動力となるのです。
部下の強みを引き出す効果的な仕事の任せ方
優秀な部下のモチベーションを再燃させ、さらなる成長を促すためには、仕事の任せ方を工夫することが不可欠です。
単調な作業や能力に見合わない業務ばかりでは、彼らの意欲は削がれる一方でしょう。
部下一人ひとりの強みや志向を深く理解し、それらを最大限に活かせるような業務のアサインを戦略的に行う必要があります。
本人のキャリア志向と強みを活かす
まず、上司は定期的な面談などを通じて、部下が将来どのようなキャリアを歩みたいと考えているのか、どのようなスキルを伸ばしたいと思っているのかを把握することが重要です。
その上で、本人の強みや得意分野は何かを客観的に分析します。
例えば、分析力に長けた部下には市場調査やデータ分析を、コミュニケーション能力が高い部下には顧客折衝やチーム内の調整役を任せるなど、適材適所の配置を心がけます。
自分の強みを活かせる仕事は、部下にとって成果を出しやすく、自己効力感を高めることにつながります。
また、キャリア志向に沿った業務経験は、仕事そのものへの意義を見出しやすくさせ、エンゲージメントを高める効果が期待できるでしょう。
裁量権を与え、挑戦的な目標を設定する
仕事を任せる際には、業務の目的や最終的なゴールは明確に共有しつつも、その達成プロセスについてはできる限り部下の裁量に委ねることが大切です。
「やり方は君に任せるよ」という信頼のメッセージが、部下の主体性と責任感を引き出します。
細かく指示を出すマイクロマネジメントを避け、部下が自ら考え、工夫し、試行錯誤する余地を残しておくのです。
さらに、現在の能力で容易に達成できる目標ではなく、少しストレッチした挑戦的な目標を設定することも有効です。
困難な課題を自らの力で乗り越えた経験は、大きな達成感と自信をもたらし、次なる挑戦への意欲をかき立てます。
もちろん、丸投げにするのではなく、上司はいつでも相談に乗れるサポーターとしての立ち位置を保ち、必要な支援を惜しまない姿勢が前提となります。
この「信頼して任せる」という経験こそが、優秀な部下をさらに優秀なリーダーへと成長させるのです。
正当な評価を伝え本人の納得感を高める

優秀な部下がやる気をなくす大きな要因である「評価への不満」を解消するためには、評価制度そのものの公平性・透明性を高めると同時に、評価結果を伝える際のコミュニケーションが極めて重要になります。
部下が「自分は正当に評価されている」と心から納得できて初めて、評価はモチベーション向上と成長促進の機能を果たします。
客観的な事実に基づいたフィードバック
評価面談の場で、上司の主観や曖昧な印象論で評価を語ることは絶対に避けなければなりません。
「君はもっと頑張れたはずだ」といった根拠のない精神論ではなく、評価期間中に部下が取った具体的な行動や、達成した成果といった客観的な事実に基づいて話を進める必要があります。
そのためには、上司は日頃から部下の仕事ぶりをよく観察し、具体的なエピソードを記録しておくことが有効です。
良い点も改善すべき点も、具体的な事実を挙げて説明することで、フィードバックの説得力は格段に増します。
「〇〇のプロジェクトで、君が主体的に他部署を巻き込んで調整してくれたおかげで、計画が前倒しで進んだ。高く評価している」というように、具体的に伝えることが重要です。
双方向の対話による評価面談の実践
評価面談は、上司から部下へ一方的に結果を申し渡す「通告の場」ではありません。
部下自身の自己評価を聞き、上司の評価との間にギャップがあれば、その理由についてすり合わせを行う「対話の場」であるべきです。
まずは部下に自己評価を発表してもらい、そのように評価した根拠を説明してもらいます。
その上で、上司としての評価を伝え、認識が異なる点については、具体的な事実を基に議論を深めていきます。
このプロセスを通じて、部下は自身の行動を客観的に振り返る機会を得るとともに、上司の視点や期待を理解することができます。
最終的に評価に納得し、次の目標に向けて前向きな気持ちになることをゴールとすべきです。
今後の期待と成長への支援を約束する
評価のフィードバックは、過去の行動を振り返るだけでなく、未来に向けたものでなければなりません。
評価面談の最後には、今回の評価を踏まえて、部下に対して今後どのような役割や成果を期待しているのかを具体的に伝えます。
そして、その期待に応えるために、部下がどのようなスキルを伸ばし、経験を積む必要があるのかを共に考え、上司として、また会社として、その成長をどのように支援していくのかを具体的に約束します。
例えば、研修への参加を推薦したり、新しいプロジェクトのキーパーソンに抜擢したりするなど、具体的なサポートプランを提示することが有効です。
自分の成長を真剣に考えてくれているという上司の姿勢は、部下にとって大きな励みとなり、会社へのエンゲージメントを高めることにつながるでしょう。
モチベーションを再燃させるための具体的な対処法
部下のモチベーション低下のサインに気づき、その原因をある程度特定できたなら、次はいよいよ具体的なアクションに移る段階です。
コミュニケーションの改善や仕事の任せ方の見直しといった基本的なアプローチに加え、部下の状況に応じてさらに踏み込んだ対処法を講じることで、やる気を効果的に再燃させることが可能になります。
ここでは、即効性と持続性の両面から有効な手法を紹介します。
短期的な成功体験を積ませる
一度やる気を失ってしまった部下に対して、いきなり壮大で長期的な目標を与えても、プレッシャーに感じてしまい逆効果になることがあります。
まずは、比較的短期間で達成可能な、具体的で小さな目標を設定し、それをクリアさせることで「やればできる」という感覚を取り戻させることが重要です。
この小さな成功体験の積み重ねが、失いかけていた自信と自己効力感を回復させます。
上司は、目標達成のプロセスを細かく見守り、適切なタイミングで称賛や承認の言葉をかけることで、部下のポジティブな感情を強化していくべきです。
成功のサイクルが回り始めれば、部下は自ずとより大きな挑戦に向かう意欲を取り戻していくでしょう。
新しい役割や責任を与えて期待を示す
マンネリ化や成長の停滞感によってモチベーションが低下している部下には、新しい役割や責任を与えることが特効薬となる場合があります。
例えば、プロジェクトのリーダーを任せる、後輩の指導役を依頼する、新しい業務領域の開拓を任せる、といったアサインが考えられます。
これは、部下に対する上司からの「君の能力を信頼し、期待している」という強力なメッセージになります。
新しい役割は、新たな視点やスキルセットの獲得を促し、仕事への新鮮な刺激となります。
もちろん、丸投げではなく、必要な権限移譲とサポート体制をセットで提供することが大前提です。
責任ある立場が、部下の当事者意識を再び呼び覚まし、眠っていたポテンシャルを引き出すきっかけとなることは少なくありません。
社内外の研修や学習機会を提供する
知的好奇心や成長意欲が高い優秀な部下にとって、新しい知識やスキルを学ぶ機会は、最高のインセンティブとなり得ます。
現在の業務から一度離れ、外部の研修やセミナーに参加することは、視野を広げ、新たな気づきを得る絶好の機会です。
また、資格取得の支援や書籍購入費用の補助といった制度も、学習意欲を後押しします。
上司は、部下のキャリアプランと本人の興味関心を踏まえ、最適な学習機会を提案・提供することが求められます。
自己投資を奨励する会社の姿勢は、従業員エンゲージメントを高めるとともに、そこで得た新しい知識やスキルが組織に還元されるという好循環を生み出します。
学習による成長実感は、仕事へのモチベーションを内発的に高める上で非常に効果的なアプローチと言えるでしょう。
優秀な部下がやる気をなくす悪循環を断ち切るために

これまで、優秀な部下がやる気をなくす原因と、その具体的な対処法について多角的に解説してきました。
優秀な部下のモチベーション低下は、本人の問題だけでなく、上司のマネジメントや職場環境が複雑に絡み合った結果として生じます。
一度この問題が発生すると、放置すればするほど状況は悪化し、本人のパフォーマンス低下に留まらず、チーム全体の士気低下や、最悪の場合、貴重な人材の離職という形で組織に大きな損失をもたらします。
重要なのは、この負のスパイラルを早期に断ち切り、ポジティブなサイクルへと転換させることです。
そのためには、本記事で挙げたようなサインを見逃さず、原因を冷静に分析し、粘り強く対処していく必要があります。
上司一人の努力には限界があり、時には人事部や経営層を巻き込み、会社全体として評価制度や職場文化の改善に取り組むことも不可欠です。
優秀な部下は、組織にとってかけがえのない財産です。
彼らが常に意欲的に、そして活き活きと働き続けられる環境を整えることこそ、変化の激しい時代を勝ち抜くための最も確実な投資と言えるのではないでしょうか。
部下との信頼関係を基盤に、一人ひとりの成長と真摯に向き合うこと。
その積み重ねが、優秀な部下がやる気をなくすという不幸な事態を防ぎ、組織全体を活性化させる原動力となるのです。
- 優秀な部下がやる気をなくすのは上司や環境に原因がある
- 会議での発言減少はモチベーション低下の初期サイン
- 挑戦を避ける態度は成長意欲の減退を示している
- 勤怠の乱れや業務品質の低下は危険信号
- 上司のマイクロマネジメントは部下の裁量を奪う
- 成果を正当に評価し称賛することが重要
- 曖昧な評価基準は部下の不信感を招く
- 単調なルーティンワークは成長機会を喪失させる
- 失敗を責める職場文化は挑戦意欲を削ぐ
- 定期的な1on1で部下の本音を傾聴する
- 仕事は裁量権を与え挑戦的な目標を設定する
- 客観的な事実に基づき納得感のある評価を行う
- 小さな成功体験で自信を回復させる
- 新しい役割を与えて期待を示すことが有効
- 優秀な部下がやる気をなくす問題は組織全体で取り組むべき課題である