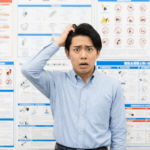最近、なぜかどんどん人が嫌いになる、と感じていませんか。
以前はそうでもなかったのに、人と会うのが億劫になったり、他人の言動に過剰にイライラしてしまったりする。
その感情の背景には、自分でも気づかないうちに蓄積されたストレスや、複雑な心理状態が隠れているのかもしれません。
仕事における人間関係に疲れたと感じることや、過去のトラウマが人間不信につながっているケースも少なくありません。
また、人一倍繊細なHSP気質が原因で、周囲の環境に過敏に反応してしまうことも考えられます。
このままではいけないと克服したい気持ちと、もういっそ一人でいたいという気持ちの間で、心が揺れ動いている方もいるでしょう。
この記事では、どんどん人が嫌いになるという感情の根本的な原因や心理を深く掘り下げ、具体的な対処法や状況を改善するためのヒントを多角的に解説していきます。
ご自身の気持ちと向き合い、少しでも心が軽くなる一歩を踏み出すための手助けとなれば幸いです。
- どんどん人が嫌いになる背後にある心理的な原因
- 人間関係の疲れが引き起こす具体的なサイン
- 過去のトラウマが対人関係に与える影響
- 繊細なHSP気質と人嫌いの関連性
- 状況を改善するための具体的な対処法
- 意識的に一人の時間を持つことの重要性
- 専門家の助けを借りるという選択肢
目次
どんどん人が嫌いになるのはなぜ?その心理的な原因
- 人間関係に疲れたと感じるサイン
- 過去のトラウマが信頼を失わせる
- 完璧主義がストレスを増大させる
- 繊細なHSP気質が影響している可能性
- 他人の欠点ばかりが目につく心理
どんどん人が嫌いになるという感情は、決して特別なものではありません。
多くの人が、人生のある時点で同様の気持ちを経験します。
しかし、その感情が日常生活に支障をきたすほど強くなると、その原因を理解し、適切に対処することが重要になります。
この感情の背後には、単なる好き嫌いを超えた、複雑な心理的なメカニズムが働いていることが多いのです。
ここでは、なぜ人が他人を嫌いになってしまうのか、その根本にある心理的な原因を5つの側面から詳しく掘り下げていきます。
ご自身の状況と照らし合わせながら、心の奥にある原因を探ってみましょう。
人間関係に疲れたと感じるサイン

私たちの日常は、公私にわたり多くの人との関わりで成り立っています。
そのため、知らず知らずのうちに人間関係の疲れが溜まってしまうことは少なくありません。
人間関係に疲れた状態が続くと、それが原因でどんどん人が嫌いになるという負のループに陥ることがあります。
まずは、その疲れのサインに気づくことが第一歩です。
身体的・行動的な変化
心が疲れると、体や行動にも変化が現れます。
例えば、以前は楽しめていた飲み会や集まりに参加するのが億劫になったり、頻繁に一人になりたいと感じるようになったりするのは、典型的なサインと言えるでしょう。
人と会う約束が近づくと、理由もなく気分が落ち込んだり、体がだるく感じたりすることもあります。
また、些細なことでイライラしやすくなったり、人との会話中に笑顔が作れなくなったりするのも、心が休息を求めている証拠かもしれません。
これらの行動は、無意識のうちにこれ以上対人関係で傷つきたくない、エネルギーを消耗したくないという自己防衛本能の表れなのです。
もし、このような変化に心当たりがあるなら、それはあなたの心が「少し休みたい」と発している重要なメッセージです。
精神的なサイン
精神的なサインは、より内面的な部分に現れます。
他人とのコミュニケーションそのものが苦痛に感じられ、会話の内容が頭に入ってこなかったり、相手の言葉の裏を過剰に読んでしまったりします。
他人の成功を素直に喜べなくなったり、逆に他人の不幸に安堵感を覚えたりするような、自己嫌悪に陥る感情もサインの一つです。
さらに、誰といても心から安らげず、常に孤独感を抱えている状態も、人間関係の疲れが深刻化している兆候と考えられます。
こうした精神的な疲労は、人を信じる気持ちをむしばみ、結果として「どうせ誰も理解してくれない」という諦めにつながり、どんどん人が嫌いになる感情を加速させてしまうのです。
過去のトラウマが信頼を失わせる
過去に受けた心の傷、いわゆるトラウマも、人を嫌いになる大きな原因となり得ます。
特に、信頼していた人からの裏切りや、いじめ、精神的な虐待などの経験は、対人関係における基本的な信頼感を根底から揺るがしてしまいます。
このような経験をすると、心は自分を守るために防衛的になり、他人に対して過剰な警戒心を抱くようになります。
トラウマが引き起こす対人関係のパターン
トラウマを抱えていると、無意識のうちに「また傷つけられるかもしれない」という恐怖から、他人と深い関係を築くことを避けるようになります。
相手が親切にしてくれても、「何か裏があるのではないか」と疑ってしまったり、相手の些細な言動をネガティブに解釈して、一方的に距離を置いてしまったりすることがあります。
これは、過去の傷が再燃することを恐れるあまり、先回りして関係を断ち切ろうとする防衛機制の一種です。
「どうせこの人も私を裏切るに違いない」という思い込みが、健全な人間関係の構築を妨げ、結果的に孤立を深めてしまうのです。
信頼感の再構築の難しさ
一度失われた信頼感を取り戻すのは、非常に時間とエネルギーを要する作業です。
頭では「すべての人が過去に自分を傷つけた人と同じではない」と理解していても、感情が追いつかないのです。
新しい出会いがあっても、過去の経験がフラッシュバックし、相手を試すような行動をとってしまったり、わざと突き放すような態度をとってしまったりすることもあります。
この状態が続くと、自分自身も「なぜ自分はうまく人と関われないのだろう」と責め始め、自己肯定感の低下を招きます。
そして、その苦しみから逃れるために、他人と関わること自体を諦め、どんどん人が嫌いになるという結論に至ってしまうのです。
トラウマが原因である場合、その根本にある傷と向き合うことが、状況改善の鍵となります。
完璧主義がストレスを増大させる

意外に思われるかもしれませんが、完璧主義な性格も、どんどん人が嫌いになる一因となり得ます。
完璧主義の人は、自分自身に高い基準を課すだけでなく、無意識のうちに他人にも同じレベルの完璧さを求めてしまう傾向があるからです。
しかし、当然ながら他人は自分の思い通りには動いてくれませんし、価値観も様々です。
この理想と現実のギャップが、大きなストレスや失望感を生み出します。
他人への期待と失望
完璧主義の人は、「こうあるべきだ」という強い規範意識を持っています。
例えば、「約束の時間は絶対に守るべきだ」「仕事は細部まで完璧にこなすべきだ」といった考え方です。
そのため、時間にルーズな人や、仕事でミスが多い人に対して、強い不満や怒りを感じやすくなります。
相手に悪気がないと分かっていても、「なぜ当たり前のことができないのか」と理解に苦しみ、それが積み重なることで、その人自身、ひいては人間全体に対する失望感へとつながっていくのです。
自分の「べき論」に合わない他者を受け入れることができず、その結果として相手を「嫌い」というカテゴリーに分類してしまうのです。
自己批判と他者批判の連鎖
完璧主義の根底には、多くの場合、「ありのままの自分では受け入れられない」という自己肯定感の低さが隠されています。
自分に厳しい人は、他人にも厳しくなりがちです。
自分の欠点や不完全さを許せないため、他人の欠点も同様に許せなくなります。
他人のアラを探して批判することで、相対的に自分の価値を保とうとする無意識の働きが起こることもあります。
しかし、他人を批判すればするほど、人間関係は悪化し、孤立感は深まります。
そして、その孤立感がさらなる自己嫌悪と他者への不信感を生み出すという悪循環に陥ります。
この連鎖を断ち切るには、「完璧でなくても良い」と自分自身を許し、他人の不完全さも受け入れる心の柔軟性を持つことが求められます。
繊細なHSP気質が影響している可能性
HSP(Highly Sensitive Person)とは、生まれつき感受性が強く、様々な刺激に敏感な気質を持つ人のことを指します。
HSPの人は、五感が鋭い、人の感情を読み取りすぎる、物事を深く考え込むといった特徴があります。
これらの特性は、クリエイティブな才能や深い共感力といった長所にもなりますが、一方で、対人関係において大きな疲れやストレスを感じやすい原因にもなります。
もしあなたが、どんどん人が嫌いになると感じているなら、それはHSP気質が関係しているかもしれません。
刺激に圧倒される脳
HSPの人は、そうでない人と比べて、外部からの刺激を処理する脳の領域が活発に働きやすいと言われています。
そのため、人混みのざわつきや、相手の表情、声のトーン、些細な言葉尻など、他の人が気づかないような情報まで無意識にキャッチしてしまいます。
これらの膨大な情報を脳が処理し続けるため、人と一緒にいるだけで、どっと疲れてしまうのです。
この疲労感が蓄積すると、人と会うこと自体が苦痛になり、刺激の源である他者を避けるようになります。これが、人嫌いにつながる一因です。
共感力の高さがもたらす疲労
HSPの高い共感力は、相手の感情がまるで自分のことのように流れ込んでくる感覚をもたらします。
相手が怒っていればその怒りを、悲しんでいればその悲しみを、自分の感情のように強く感じ取ってしまいます。
友人から相談を受ければ、自分の問題以上に悩み込んでしまうこともあるでしょう。
このように、他人の感情に振り回され続けると、心の境界線が曖昧になり、精神的なエネルギーを過剰に消耗します。
その結果、自分の心を守るために、感情的な刺激をもたらす人との関わりを断ちたいと感じるようになり、どんどん人が嫌いになるという状態に陥ってしまうのです。
HSPの人が健やかに過ごすためには、自分の気質を正しく理解し、刺激を調整する方法を学ぶことが非常に重要です。
他人の欠点ばかりが目につく心理

誰にでも長所と短所があるのは当たり前のことです。
しかし、なぜか他人の欠点やアラばかりが気になってしまい、その結果として人を嫌いになってしまうことがあります。
この現象の背後には、いくつかの心理的な要因が考えられます。
単に相手が悪いと切り捨てるのではなく、なぜ自分が相手の欠点にこれほどまでに注目してしまうのか、その内面的な理由を探ることが大切です。
自己投影のメカニズム
心理学には「投影」という概念があります。
これは、自分が認めたくない自分自身の欠点や嫌いな部分を、あたかも相手が持っているかのように映し出して見てしまう心の働きです。
例えば、自分が優柔不断であることを認められない人は、他人の優柔不断な態度にことさら腹を立てることがあります。
自分が本当は怠けたいのにそれを許せずにいる人は、のんびりしている人を見るとイライラするかもしれません。
つまり、他人の欠点に対して感じる強い嫌悪感は、実は自分自身への嫌悪感の裏返しである可能性があるのです。
相手の嫌な部分が目につくとき、「これは自分の中にもある要素ではないか」と一度立ち止まって考えてみることで、新たな気づきがあるかもしれません。
自己肯定感の低さと劣等感
自己肯定感が低く、自分に自信がない人も、他人の欠点を探しがちです。
これは、他人の欠点を見つけて批判することで、相対的に自分の立場を優位に立たせ、一時的に安心感を得ようとする防衛的な行動です。
「あの人にもこんな欠点があるのだから、自分はまだマシだ」と感じることで、自分の劣等感を紛らわせようとするのです。
しかし、この方法は根本的な解決にはならず、むしろ人間関係を悪化させるだけです。
他人を貶めて得られる安心感は長続きせず、常に他人のアラを探し続ける「批判者」としての役割から抜け出せなくなります。
この状態が続けば、周囲から人が離れていき、ますます孤立し、人嫌いが深刻化するという悪循環に陥ってしまいます。
根本的な解決のためには、他人との比較ではなく、自分自身の価値を認め、自己肯定感を育てていくことが不可欠です。
どんどん人が嫌いになる状況を改善するための対処法
- 意識的に一人の時間を作ってみる
- 職場での人間関係を見直す
- SNSとの健全な距離の保ち方
- 専門家への相談も有効な選択肢
- ポジティブな側面に目を向ける訓練
- どんどん人が嫌いになる自分と向き合うには
どんどん人が嫌いになるという感情に飲み込まれそうになった時、ただその気持ちに耐えるだけでは、状況はなかなか好転しません。
大切なのは、その感情を認めつつ、具体的な行動を起こして、心の負担を軽くしていくことです。
原因が人それぞれであるように、その対処法も一つではありません。
ここでは、今日からでも始められる具体的な対処法を6つの観点からご紹介します。
自分に合った方法を見つけ、少しずつ試していくことで、きっと変化の兆しが見えてくるはずです。
完璧を目指す必要はありません。
まずは、自分をいたわることから始めましょう。
意識的に一人の時間を作ってみる

常に誰かと一緒にいたり、周囲の期待に応えようとしたりしていると、心は知らず知らずのうちに疲弊していきます。
特に、HSP気質の人や内向的な性格の人は、対人関係で消費したエネルギーを回復させるために、一人の時間が不可欠です。
どんどん人が嫌いになると感じるときは、心が「もう十分だ、一人にさせてほしい」というサインを送っているのかもしれません。
そんな時は、罪悪感を抱くことなく、意識的に一人の時間を確保することが非常に有効な対処法となります。
一人の時間の質の高め方
ただ一人でいるだけでなく、その時間をいかに心地よく過ごすかが重要です。
例えば、好きな音楽を聴きながら読書に没頭する、誰にも邪魔されずに映画の世界に浸る、近所の公園をゆっくり散歩するなど、自分が心からリラックスできる活動を見つけましょう。
重要なのは、その時間の中で「~すべき」という思考を一切手放すことです。
仕事のことも、人間関係のことも、一旦頭の隅に追いやり、ただただ「今、ここ」の感覚を味わうことに集中します。
カフェで人間観察をするのも良いですが、他人の存在が気になるなら、自宅でハーブティーを淹れて静かに過ごす方が合っているかもしれません。
自分だけの聖域とも言える時間を定期的に持つことで、すり減った心のエネルギーを充電し、他人と向き合うための余裕を取り戻すことができます。
孤独と孤立の違いを理解する
一人の時間を持つことに対して、「孤立してしまうのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。
しかし、「孤独(Solitude)」と「孤立(Isolation)」は全く異なります。
孤独とは、自ら進んで一人になる、積極的で豊かな時間です。
一方、孤立とは、望まないのに他者とのつながりを失い、寂しさや疎外感を伴う状態を指します。
意識的に一人の時間を作ることは、他者との関係を断絶することではありません。
むしろ、自分自身との対話を深め、心を整えることで、より健全な状態で他者と関わるための準備期間なのです。
この時間を大切にすることで、他人に振り回されるのではなく、自分の軸を持って人と接することができるようになります。
職場での人間関係を見直す
多くの人にとって、一日の大半を過ごす職場は、人間関係の悩みが最も生じやすい場所の一つです。
合わない上司や同僚との関わりは、大きなストレスとなり、仕事へのモチベーションだけでなく、プライベートの精神状態にまで悪影響を及ぼすことがあります。
職場が原因でどんどん人が嫌いになると感じているなら、一度その関係性を見直し、適切な距離感を設定することが必要です。
割り切る勇気と境界線の設定
職場の人間関係は、友人関係とは異なり、必ずしも全員と仲良くする必要はありません。
仕事上の目的を達成するために必要なコミュニケーションが取れていれば、それ以上の深い関係を無理に築こうとしなくても良いのです。
「仕事は仕事」と割り切り、プライベートな感情を持ち込まないように意識するだけでも、心の負担は大きく軽減されます。
また、相手との間に適切な「境界線(バウンダリー)」を引くことも重要です。
例えば、業務時間外の連絡には応じない、プライベートな質問には当たり障りなくかわす、無理な頼み事は断る勇気を持つ、といった具体的な行動が、自分を守ることにつながります。
環境を変えるという選択肢
個人の努力だけでは、どうしても改善が難しい状況もあります。
ハラスメントが横行している、企業の文化そのものが自分に合わないといった場合は、環境を変える、つまり異動や転職を視野に入れることも、決して逃げではありません。
心身の健康を損なってまで、その場所に留まり続ける必要はないのです。
転職を考える際に整理すべきポイントを以下に示します。
- 何が一番のストレス源か(特定の人物、業務内容、社風など)
- 次の職場に求める条件は何か(人間関係、仕事の裁量、労働時間など)
- 自分自身の強みやスキルは何か
これらの点を整理することで、より自分に合った環境を見つけやすくなります。
自分の心と体を守るための戦略的な選択として、環境を変えることをポジティブに検討してみましょう。
SNSとの健全な距離の保ち方

現代社会において、SNSは便利なコミュニケーションツールである一方、精神的な疲労や人間不信の大きな原因にもなり得ます。
他人のキラキラした投稿を見て劣等感を抱いたり、何気ない一言に傷ついたり、義理で「いいね」を押すことに疲れたり…。
こうしたSNS疲れが、どんどん人が嫌いになる感情を増幅させているケースは非常に多いです。
SNSとの付き合い方を見直すことは、心の平穏を取り戻すために不可欠です。
デジタルデトックスの実践
最も効果的な方法の一つが、「デジタルデトックス」です。
これは、一定期間スマートフォンやSNSから意識的に離れることで、情報過多の状態から脳と心を解放する試みです。
いきなり完全にやめるのが難しい場合は、段階的に始めるのがおすすめです。
- 寝る前1時間はスマホを見ない。
- 食事中はスマホをテーブルに置かない。
- 休日の午前中はSNSアプリを開かない。
- 通知をオフにして、自分が見たいときだけ見るようにする。
こうした小さなルールを設けるだけでも、SNSに振り回される時間が減り、現実世界での活動や自分自身の感覚に集中できるようになります。
SNSから離れてみると、他人の動向が気にならなくなり、自分が本当に大切にしたいものが見えてくることがあります。
情報の受け取り方を変える
SNSを完全にやめるのではなく、使い方を工夫する方法もあります。
まず、フォローするアカウントを見直しましょう。
見ていて不快な気持ちになったり、劣等感を煽られたりするアカウントは、思い切ってミュートやフォロー解除をします。
代わりに、自分の好きな趣味や、見ていて癒される動物、美しい風景などのアカウントを増やすことで、タイムラインを自分にとって心地よい空間に変えることができます。
また、SNSで発信されている情報は、その人の人生の「ハイライト」を切り取ったものに過ぎないと理解することも重要です。
投稿の裏側にある日常や苦労は見えないということを常に意識することで、他人の投稿と自分を比較して落ち込むことが少なくなります。
専門家への相談も有効な選択肢
自分一人で悩みや感情を抱え込み、どうしても解決の糸口が見つからないとき、専門家の力を借りることは非常に賢明で勇気ある選択です。
日本ではまだカウンセリングへのハードルが高いと感じる人もいますが、心の専門家は、客観的かつ専門的な視点から、あなたの状況を整理し、問題解決の手助けをしてくれます。
風邪をひいたら内科に行くように、心が疲れたら専門家に相談するのは、ごく自然なことです。
カウンセリングで得られること
カウンセラーや臨床心理士は、あなたの話を傾聴し、評価や批判をすることなく、ありのままのあなたを受け止めてくれます。
安心して自分の感情を吐き出せる安全な場所が得られるだけでも、心は大きく軽くなります。
さらに、専門家との対話を通じて、自分では気づかなかった感情のパターンや思考の癖、問題の根本原因を明らかにすることができます。
例えば、どんどん人が嫌いになるという感情が、実は幼少期の親子関係に起因する愛着の問題や、対処が必要なトラウマのサインである可能性も指摘してくれるかもしれません。
原因が明確になることで、漠然とした不安が具体的な課題へと変わり、対処法も見えやすくなります。
心療内科や精神科という選択
不眠、食欲不振、気分の落ち込み、強い不安感など、日常生活に支障をきたすほどの身体的な症状も現れている場合は、心療内科や精神科の受診も検討しましょう。
これらの症状は、うつ病や適応障害、不安障害などのサインである可能性もあります。
医師の診察を受けることで、適切な診断がなされ、必要であれば薬物療法なども含めた治療を受けることができます。
薬物療法に抵抗がある人もいるかもしれませんが、それは脳内で起こっている化学的な不調を整えるためのものであり、カウンセリングと並行することで、回復を大きく助ける場合があります。
専門家への相談は、自分を弱いと認めることではなく、自分を大切にし、より良く生きるための積極的な一歩なのです。
ポジティブな側面に目を向ける訓練

どんどん人が嫌いになるとき、私たちの心はネガティブな情報に対して非常に敏感になっています。
他人の欠点や嫌な部分ばかりがフィルターにかかったように目につき、良い部分が見えにくくなっています。
この心の癖を修正し、意識的に物事のポジティブな側面に光を当てる訓練は、状況を改善する上で効果的なアプローチです。
これは無理にポジティブになろうとするのではなく、偏った見方をニュートラルな状態に戻していく作業と言えます。
感謝日記(スリーグッドシングス)
簡単に始められる訓練として、「感謝日記」や「スリーグッドシングス」があります。
これは、一日の終わりに、その日にあった「良かったこと」や「感謝したこと」を3つ書き出すというシンプルな習慣です。
内容はどんな些細なことでも構いません。
- コンビニの店員さんが笑顔で接してくれた。
- 同僚が仕事を手伝ってくれた。
- 友人が面白い話を聞かせてくれた。
これを続けることで、脳がポジティブな情報を探し出す癖がつき、日常生活の中に隠れている小さな幸せや、他人の親切に気づきやすくなります。
人の嫌な部分にばかり向いていた意識のチャンネルを、少しずつ良い部分に向ける練習になるのです。
リフレーミングの技術
リフレーミングとは、物事を見る枠組み(フレーム)を変えることで、その出来事の意味付けをポジティブなものに変える心理的な技術です。
例えば、「おせっかいな人」という見方を、「面倒見の良い、親切な人」と捉え直してみます。
「頑固で融通が利かない人」は、「意志が強く、信念を持っている人」と見ることもできます。
もちろん、すべての欠点を無理に美化する必要はありません。
しかし、一つの出来事や人物には、必ず多面的な側面があるということを理解し、別の角度から見る癖をつけることが重要です。
この訓練を繰り返すことで、他人の行動に対する許容範囲が広がり、すぐに「嫌い」と決めつけるのではなく、「そういう側面もあるのだな」と一旦保留できるようになります。
これにより、対人関係におけるストレスが大きく軽減されるでしょう。
どんどん人が嫌いになる自分と向き合うには
この記事を通じて、どんどん人が嫌いになる原因とその対処法について探ってきました。
人間関係の疲れ、過去のトラウマ、完璧主義、HSP気質など、その背後には様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かります。
そして、それらに対処するためには、一人の時間を大切にしたり、SNSとの距離を置いたり、時には専門家の助けを借りたりと、具体的な行動が有効です。
しかし、最も重要なのは、そう感じてしまう自分自身を否定しないことです。
自己受容から始める
「人を嫌いになるなんて、自分は心が狭い人間だ」と自分を責めてしまうかもしれません。
しかし、その感情は、あなたの心が傷つき、疲弊している証拠であり、あなた自身を守るための自然な反応なのです。
まずは、「そうか、自分は今、人が嫌いになるほど疲れているんだな」と、その感情をありのままに受け止めてあげましょう。
自分を責めることをやめ、自分に優しくなることから、回復への道は始まります。
自分自身を最大の味方につけることが、この苦しい状況を乗り越えるための最も大きな力となります。
小さな一歩を大切にする
状況を一度に変えようと焦る必要はありません。
この記事で紹介した対処法の中から、まずは一つでも、できそうなことから試してみてください。
5分だけ早く起きて、静かにお茶を飲む時間を作る。
寝る前にスマホを見るのをやめてみる。
それだけでも、大きな一歩です。
小さな成功体験を積み重ねていくことで、自己効力感が高まり、「自分ならこの状況を変えていけるかもしれない」という希望が生まれてきます。
どんどん人が嫌いになるという感情は、あなたに「これまでの生き方や人間関係を見直す時期だよ」と教えてくれる、人生の転機となるサインなのかもしれません。
この機会を、自分自身と深く向き合い、より健やかで自分らしい生き方を見つけるためのきっかけとして活かしていきましょう。
- どんどん人が嫌いになるのは心からのSOSサイン
- 原因は人間関係の疲れやストレスの蓄積にあることが多い
- 過去の裏切りやトラウマが人間不信を引き起こす
- 完璧主義は他人への過度な期待と失望を生む
- HSP気質は刺激に敏感で対人疲労を感じやすい
- 他人の欠点が目につくのは自己投影の可能性がある
- 対処法として意識的に一人の時間を作ることが重要
- 一人の時間はエネルギーを充電するための大切な時間
- 職場の人間関係は割り切りと境界線が鍵
- 心身の健康が最優先であり転職も選択肢の一つ
- SNSとの距離を置くデジタルデトックスを試す
- 悩みが深い場合はカウンセリングなど専門家を頼る
- 感謝日記などで物事のポジティブな面に目を向ける訓練をする
- 人を嫌いになる自分を責めずに受け入れることが第一歩
- 小さな成功体験を重ねて自信を取り戻していく