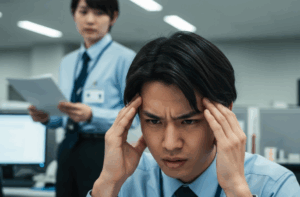あなたは、誰かから褒められたときに、素直に喜べず、どう反応していいか分からずに困ってしまった経験はありませんか。
多くの人が、褒められるのが苦手という悩みを抱えています。
その背景には、複雑な心理や理由が隠されていることが多いのです。
この記事では、なぜ褒められるのが苦手と感じるのか、その根本的な原因を探っていきます。
自己肯定感の低さや特有の性格、あるいは幼少期の育ちといった要因が、どのように影響しているのかを一つひとつ解き明かします。
さらに、具体的な対処法や、今すぐに実践できる克服のためのステップも紹介します。
仕事の場面やプライベートな恋愛におけるコミュニケーションで役立つ、スマートな返し方も身につけることができるでしょう。
本記事を最後まで読めば、褒め言葉を素直に受け入れ、ポジティブな力に変えていくためのヒントが見つかるはずです。
- 褒められるのが苦手な人の心理的な背景
- 自己肯定感が低いとなぜ褒め言葉を疑うのか
- 褒められたときの適切な対処法と返し方
- 仕事の場面で褒められたときのスマートな対応
- 恋愛において褒め言葉を素直に受け入れるコツ
- 苦手意識を克服するための具体的なステップ
- 育ちや性格がどう影響するのかの解説
目次
褒められるのが苦手な人の5つの心理的理由
- つい「裏があるのでは」と疑ってしまう
- 自己肯定感の低さが影響している
- 注目されるのが恥ずかしいと感じる性格
- 褒め言葉がプレッシャーになることも
- 過去の経験や育ちが関係している
つい「裏があるのでは」と疑ってしまう

褒められるのが苦手な人が抱える心理の一つに、相手の言葉の裏を読んでしまい、素直に受け取れないという傾向があります。
誰かから「すごいね」や「助かったよ」といった肯定的な言葉をかけられたとしても、その言葉を額面通りに受け止めることができません。
「何か下心があるのではないか」「お世辞で言っているだけだろう」「後で何か面倒なことを頼まれる前触れかもしれない」といった疑念が、心の中に渦巻いてしまうのです。
このような思考パターンに陥る背景には、過去の人間関係における経験が影響している場合があります。
例えば、以前に誰かから褒められた後で、不本意な要求をされたり、利用されたりした経験があると、褒め言葉そのものに対して警戒心が芽生えてしまいます。
また、競争の激しい環境に身を置いてきた人は、他人の称賛を素直に信じることが難しくなることもあるでしょう。
相手をライバルとして認識するあまり、「自分を油断させるための戦略ではないか」と深読みしてしまうのです。
この疑念は、コミュニケーションにおいて壁を作ってしまう原因にもなります。
相手は純粋な好意から褒めているにもかかわらず、こちらが疑いの目で見ていると、その態度は相手にも伝わってしまうものです。
結果として、人間関係がぎくしゃくしたり、相手との間に距離が生まれたりすることにもなりかねません。
大切なのは、すべての褒め言葉に裏があるわけではないと理解することです。
もちろん、中には社交辞令やお世辞も含まれているかもしれませんが、多くの場合は、相手が感じたままのポジティブな気持ちを表現してくれています。
まずは、相手の言葉を一度フラットな気持ちで受け止めてみる姿勢が、この疑心暗鬼から抜け出す第一歩と言えるでしょう。
つい「裏があるのでは」と疑ってしまう
褒められるのが苦手な人の心理として、自己肯定感の低さが大きく関わっているケースは非常に多いです。
自己肯定感とは、ありのままの自分を価値ある存在として認め、尊重する感覚のことを指します。
この感覚が低いと、自分自身に対する評価が極端に低くなってしまうため、他人からの高い評価、つまり褒め言葉を素直に受け入れることができなくなるのです。
例えば、仕事で成果を出して上司から「君は本当に優秀だな」と褒められたとします。
自己肯定感が高い人であれば、「ありがとうございます、頑張った甲斐がありました」と素直に喜べるでしょう。
しかし、自己肯定感が低い人は、「そんなことはない、今回はたまたま運が良かっただけだ」「自分なんて大した能力もないのに、過大評価されている」と感じてしまいます。
褒め言葉と、自分自身が抱いている自己イメージとの間に大きなギャップがあるため、心の中に強い違和感や居心地の悪さが生まれるのです。
このギャップは、「自分は褒められるに値しない人間だ」という無意識の思い込みから生じます。
そのため、褒められると「相手は自分の本当の姿を知らないから、こんなことを言うんだ」「いつか本当の能力のなさがバレて、がっかりさせてしまうに違いない」といった不安や恐怖を感じることさえあります。
自己肯定感が低い状態では、褒め言葉は喜びではなく、むしろ自分の不完全さを突きつけられるような苦痛な体験になってしまうのです。
この問題を解決するためには、まず自分自身が「自分は褒められてもいい存在なのだ」と許可を出す必要があります。
他人からの評価を待つのではなく、自分自身の小さな成功や努力を認め、自分で自分を褒めてあげる習慣をつけることが、自己肯定感を育む上で非常に重要になります。
日々の生活の中で、できたことや頑張ったことを意識的に見つけ、それを肯定する作業を繰り返すことで、少しずつ他人からの称賛も受け入れられるようになっていくでしょう。
注目されるのが恥ずかしいと感じる性格

褒められるという行為は、その瞬間、自分に周囲の注目が集まることを意味します。
褒められるのが苦手な人の中には、この「注目を浴びること」自体に強い羞恥心や居心地の悪さを感じる性格の人が少なくありません。
特に、内向的であったり、謙遜を美徳とする文化で育ったりした人は、自分が主役になるような状況を避けたいと考える傾向があります。
例えば、会議の場で自分の出したアイデアが採用され、上司から名指しで称賛されたとしましょう。
その瞬間、会議室にいる全員の視線が自分に注がれます。
このような状況で、「嬉しい」という気持ちよりも先に、「恥ずかしい」「どうしよう」「早くこの場から消えたい」といった感情が湧き上がってくるのです。
顔が赤くなったり、冷や汗をかいたり、しどろもどろになったりするのは、この羞恥心からくる身体的な反応です。
このタイプの人は、できるだけ目立たずに、平穏に過ごしたいと願っています。
そのため、褒められることで自分が周囲から浮いた存在になってしまうことを恐れます。
「褒められたことで、他の同僚から嫉妬されるかもしれない」「自分だけ特別扱いされているように思われたくない」といった、周囲との調和を気にする気持ちも強く働きます。
彼らにとって褒め言葉は、自身の平穏を乱す、できれば避けたいイベントなのです。
このような性格の人が褒め言葉に慣れていくためには、少しずつ自己表現の場に慣れる練習が有効です。
大人数の前でいきなり対応するのは難しくても、まずは信頼できる友人や家族など、ごく親しい間柄で、自分の意見を伝えたり、小さな成功を報告したりすることから始めてみましょう。
安心できる環境で注目される経験を少しずつ積むことで、他者からのポジティブな視線に対する耐性がつき、羞恥心も和らいでいく可能性があります。
また、「注目される=攻撃される」という無意識の思い込みを、「注目される=認められる」というポジティブな認識へと変えていく意識改革も助けになるでしょう。
褒め言葉がプレッシャーになることも
褒められるのが苦手な理由として、褒め言葉が未来への期待として重くのしかかり、プレッシャーに感じてしまうという側面があります。
特に、真面目で責任感の強い人ほど、この傾向が強く見られます。
例えば、上司から「君の企画書はいつも素晴らしいな。次も期待しているよ」と褒められたとします。
この言葉は、本来であれば自分の仕事を認められた証であり、喜ばしいはずです。
しかし、プレッシャーを感じやすい人は、「次も今回以上のものを作らなければならない」「期待を裏切ってはいけない」「もし次が失敗したら、がっかりさせてしまう」といった思考に陥ってしまいます。
つまり、過去の実績に対する称賛が、未来の成功を約束する「呪い」のように感じられてしまうのです。
この心理の根底には、完璧主義的な考え方があります。
常に100点満点でなければならない、一度上げたハードルは決して下げてはならない、という思い込みが強いと、褒め言葉は次への挑戦を後押しするエールではなく、失敗が許されない状況を作り出す重圧となります。
その結果、褒められるたびに「また期待値が上がってしまった」と、むしろ憂鬱な気分になってしまうことさえあるのです。
このようなプレッシャーから解放されるためには、物事の捉え方を少し変えてみることが有効です。
- 褒め言葉は、あくまで過去の特定の行動や成果に対する評価であり、未来のすべてを縛るものではないと理解する。
- 「次も成功させなければ」ではなく、「次も自分らしくベストを尽くそう」と考える。
- 失敗は成長の過程で当然起こりうるものであり、一度の失敗で自分の価値がすべて失われるわけではないと認識する。
褒め言葉を「期待」というプレッシャーではなく、「信頼」というエネルギーとして受け止める練習が必要です。
相手はあなたにプレッシャーをかけるために褒めているのではありません。
あなたの能力を信頼し、応援したいという気持ちから言葉をかけてくれているのです。
その好意を、次への活力として前向きに捉えることができれば、褒められることへの苦手意識も少しずつ薄れていくでしょう。
過去の経験や育ちが関係している

褒められるのが苦手という感覚は、その人の生まれ持った性格だけでなく、これまでの人生経験、特に幼少期の家庭環境や学校での体験、いわゆる「育ち」が大きく影響している場合があります。
人の価値観や物事の捉え方の土台は、子どもの頃の親や教師との関わりの中で形成されていくためです。
例えば、あまり褒められずに育った家庭環境は、その一因となり得ます。
親が厳しく、子どもが良い成績を取ったり、何かを達成したりしても、「できて当たり前だ」「もっと上を目指しなさい」といった接し方をされてきた場合、子どもは「自分は認められるに値しない」という感覚を内面化していきます。
このような環境で育つと、大人になってから他人に褒められても、どう反応していいか分からなかったり、居心地の悪さを感じたりするようになります。
なぜなら、自分の中に「褒められる」という経験の引き出しがほとんどないためです。
逆に、条件付きの愛情で育てられた経験も影響します。
「テストで100点を取ったら褒めてあげる」「言うことを聞く良い子でいたら愛してあげる」というように、何かを達成したときだけ褒められる環境では、「ありのままの自分には価値がない」というメッセージを受け取ってしまいます。
その結果、大人になってから褒められても、「何か特別なことをしたから褒められているだけで、本当の自分はすごくない」と感じ、素直に喜べなくなってしまうのです。
また、学校での体験も無視できません。
褒められたことで、友人から嫉妬されたり、仲間外れにされたりした辛い経験があると、褒められること自体を「危険なこと」として学習してしまいます。
目立つことで人間関係が悪化することを恐れ、無意識のうちに褒められるような状況を避けるようになるのです。
これらの過去の経験や育ちは、現在の自分の思考パターンに深く根付いています。
もし、自分の苦手意識の背景にこのような要因があるかもしれないと感じた場合は、まずその事実を自分自身で認識することが大切です。
過去を変えることはできませんが、「あの頃の経験が、今の自分の考え方に影響しているんだな」と客観的に理解することで、そのパターンから抜け出すきっかけを掴むことができます。
自分を責めるのではなく、そう感じるようになった背景を理解し、今の自分を労ってあげることが、克服への重要な一歩となります。
褒められるのが苦手な状況を克服する方法
- まずは「ありがとう」と感謝を伝える練習
- 上手な返し方で会話をスムーズに
- 仕事での評価を素直に受け止める
- 恋愛における褒め言葉への対処法
- ポジティブな思考への具体的な改善策
- 褒められるのが苦手な自分と向き合う
まずは「ありがとう」と感謝を伝える練習

褒められるのが苦手な状況を克服するための、最もシンプルで、かつ最も効果的な第一歩は、褒められたときに「ありがとうございます」と感謝の言葉を口に出して伝える練習をすることです。
多くの人は、褒められると咄嗟に「いえいえ、そんなことないです」「私なんて全然です」といった否定の言葉を返してしまいます。
これは謙遜のつもりかもしれませんが、相手のポジティブな言葉を打ち消してしまう行為であり、会話を気まずくさせてしまう原因にもなりかねません。
相手はせっかくあなたを認め、好意を伝えようとしているのに、それを否定されてしまうと、「褒めたのが悪かったかな」「喜んでもらえなかったな」と感じてしまうかもしれません。
そこで、まずは心の中でどう感じていようとも、反射的に「ありがとうございます」と返せるように習慣づけることが重要です。
このアプローチの利点は、褒め言葉の内容を肯定も否定もせず、ただ相手の「褒めてくれたという行為」に対して感謝を示すだけで済むという点にあります。
「自分はすごい」と無理に思い込む必要はありません。
ただ、「そう言ってくれて、ありがとう」という気持ちを伝えるのです。
最初は、心の中で居心地の悪さや違和感を感じるかもしれません。
口では「ありがとう」と言いながらも、心の中では「本当はそう思っていないのにな」と感じることもあるでしょう。
しかし、それでも構いません。
大切なのは、行動を先に変えてしまうことです。
言葉と行動を繰り返すうちに、少しずつ心もその状態に慣れていきます。
具体的な練習方法
- 鏡に向かって、自分で自分を褒め、「ありがとうございます」と笑顔で返す練習をする。
- 家族や親しい友人など、信頼できる相手に協力してもらい、褒めてもらうシミュレーションをする。
- 日常のささいな場面で「ありがとう」と言う機会を増やす(例:店員さんに、バスの運転手さんに)。
「ありがとう」という言葉は、相手の好意を受け入れるというサインです。
この一言がスムーズに出るようになるだけで、コミュニケーションは格段に円滑になります。
そして、相手が喜んでくれる様子を見るうちに、「褒められることは、必ずしも悪いことではないのかもしれない」と、少しずつポジティブな経験として心に蓄積されていくはずです。
上手な返し方で会話をスムーズに
褒められたときに「ありがとうございます」と感謝を伝えることができるようになったら、次のステップとして、会話をより自然で豊かにするための「上手な返し方」を身につけていきましょう。
感謝の言葉一言で終わらせてしまうと、そこで会話が途切れてしまい、気まずい沈黙が流れてしまうこともあります。
少しだけ言葉を付け加えることで、相手とのコミュニケーションを円滑にし、ポジティブな雰囲気を持続させることができます。
ここでは、状況に応じて使えるいくつかのパターンを紹介します。
1. 「感謝」+「ポジティブな一言」
これは最も基本的な応用形です。「ありがとうございます」の後に、嬉しい気持ちや今後の意欲などを簡潔に付け加えます。
例:
「そのように言っていただけて、とても嬉しいです。」
「ありがとうございます。今後の励みになります。」
「そうなんですよ、この部分は特にこだわったので、気づいてもらえて嬉しいです。」
2. 「感謝」+「相手を褒め返す」
相手を不快にさせない程度に、相手の良い点を褒め返すテクニックです。ただし、お世辞に見えないように、具体的で正直な点を指摘することがポイントです。
例:
「ありがとうございます。〇〇さんのサポートがあったおかげです。」
「恐縮です。いつも的確なアドバイスをくださる〇〇さんに言われると、自信が持てます。」
「そんなことないですよ。〇〇さんのファッションこそ、いつも素敵だなと思って見ています。」
3. 「感謝」+「質問で返す」
相手に質問を投げかけることで、会話のボールを相手に渡し、スムーズに話題を転換させることができます。自分のことから相手のことへと関心を移すテクニックです。
例:
「ありがとうございます。そういえば、〇〇さんが先日取り組んでいたプロジェクトはどうなりましたか?」
「嬉しいです。ちなみに、〇〇さんはこの件についてどう思われますか?」
これらの返し方のポイントは、褒め言葉を否定せずに一旦受け入れた上で、会話を次に繋げる意識を持つことです。
自分を卑下する必要もなければ、過剰に自慢する必要もありません。
相手からのポジティブなボールを、感謝というクッションで受け止め、そして相手が受け取りやすいボールを投げ返すようなイメージです。
これらのフレーズをいくつか覚えておき、状況に合わせて使い分ける練習をすることで、褒められたときの気まずさや戸惑いは大幅に軽減されるでしょう。
仕事での評価を素直に受け止める

職場は、成果や能力に対する評価、つまり「褒め言葉」が頻繁に行き交う場所です。
上司や同僚、クライアントからの称賛は、自身のキャリアにおける重要なフィードバックであり、成長の糧となるものです。
しかし、褒められるのが苦手な人にとっては、仕事での評価が大きなストレスの原因となることも少なくありません。
仕事の場面で褒められたときに、それを素直に受け止めるための考え方と具体的なアクションについて解説します。
まず大切なのは、仕事における評価は、人格そのものではなく、「特定の業務遂行能力や成果」に対して与えられるものであると理解することです。
「君は素晴らしい人間だ」という漠然とした評価ではなく、「先日のプレゼンテーションの資料が、非常に分かりやすくて良かった」といった具体的な行動に対する評価です。
このように、褒められているポイントを具体的に捉えることで、過剰に恐縮したり、自分自身を過大評価されていると感じたりすることを防げます。
「自分のすべてが褒められているわけではない、この部分を評価してもらえたのだ」と限定的に捉えることで、心はだいぶ楽になります。
次に、褒め言葉を「チームの成果」として受け止める視点も有効です。
特に、自分が中心となって進めたプロジェクトが評価された場合、過度な謙遜は、共に働いた同僚の貢献を軽視することにも繋がりかねません。
そんなときは、個人としてではなく、チームの代表として感謝の言葉を述べるとスムーズです。
例:
「ありがとうございます。チームメンバー全員で協力して頑張った結果です。」
「この成功は、サポートしてくださった皆様のおかげです。本当にありがとうございます。」
このように返すことで、自分一人に注目が集まるのを避けつつ、感謝の意を伝え、チーム全体の士気を高めることにも貢献できます。
さらに、受け取った評価を次のアクションに繋げる意識を持つことも重要です。
褒められた内容を分析し、「自分のどのようなスキルや行動が評価されたのか」「その強みを今後どのように活かしていけるか」を考えるのです。
評価を客観的なデータとして捉え、自己分析と今後のキャリアプランニングに役立てることで、褒め言葉はプレッシャーではなく、貴重な成長のヒントに変わります。
仕事での評価は、あなたの市場価値を示すバロメーターの一つです。
それを謙遜や自己否定で突き返してしまうのは、非常にもったいない行為です。
まずは客観的な事実として受け止め、感謝し、次に活かす。
このサイクルを意識することで、褒められることへの苦手意識は、プロフェッショナルとしての自信へと昇華していくでしょう。
恋愛における褒め言葉への対処法
恋愛関係において、パートナーからの褒め言葉は、愛情表現や関係を深めるための重要なコミュニケーションの一つです。
「今日の服、似合ってるね」「君のそういう優しいところが好きだな」といった言葉は、二人の絆を強める潤滑油の役割を果たします。
しかし、褒められるのが苦手だと、この大切な愛情表現を素直に受け取ることができず、関係がぎくしゃくしてしまう原因にもなり得ます。
恋愛の場面で、パートナーからの褒め言葉に上手に対処するための心構えを紹介します。
まず理解すべきなのは、パートナーがあなたを褒めるとき、それは単なるお世辞や社交辞令ではないということです。
パートナーは、あなたのことを最も身近で見ており、あなたの素敵な部分を心から良いと思って伝えてくれています。
それを「そんなことないよ」と否定してしまうのは、相手の気持ちや、あなたを見る目を否定することと同じです。
相手は「自分の好きなところを、この人は自分で分かっていないんだな」「気持ちが伝わらなくて悲しいな」と感じてしまうかもしれません。
恋愛においては、まず「ありがとう」と笑顔で受け入れることが何よりも大切です。
そして、もし照れくさい気持ちがあるなら、その気持ちも素直に伝えてしまうのが良いでしょう。
例:
「ありがとう。そんな風に言ってもらえると、すごく照れるけど…嬉しいな。」
「本当?自分ではそう思わないけど、あなたに言われると自信が持てるよ。ありがとう。」
自分の弱さや戸惑いを正直に見せることで、パートナーはあなたをより愛おしく感じ、二人の心理的な距離はさらに縮まるはずです。
また、自分からも積極的にパートナーを褒める習慣をつけることも、非常に効果的です。
自分が相手を褒めることで、「褒める」という行為が、いかに相手を喜ばせ、ポジティブなエネルギーを生み出すものであるかを実感できます。
そして、自分が相手の良いところをたくさん見つけているように、相手も自分の良いところを見てくれているのだと、自然に信じられるようになります。
褒め言葉のキャッチボールは、お互いの自己肯定感を高め合い、関係をより良好に保つための素晴らしいトレーニングです。
パートナーからの褒め言葉は、あなたへの愛情の証です。
それを疑ったり、突き返したりせず、最高のプレゼントとして両手で受け取ってください。
その素直な反応が、パートナーにとっては何よりの喜びとなり、二人の関係をさらに豊かなものにしてくれるでしょう。
ポジティブな思考への具体的な改善策

褒められるのが苦手な状況を根本的に克服していくためには、褒め言葉を素直に受け取れない原因となっている、ネガティブな思考の癖そのものを改善していくアプローチが不可欠です。
ここでは、日々の生活の中で実践できる、ポジティブな思考を育むための具体的な改善策をいくつか紹介します。
1. 自分の長所をリストアップする
多くの人は自分の短所ばかりに目が行きがちです。
意識的に自分の長所や得意なこと、人から感謝された経験などを紙に書き出してみましょう。
どんな些細なことでも構いません。「時間を守れる」「植物を育てるのが上手」「人の話を最後まで聞ける」など、できるだけ多くリストアップすることがポイントです。
この作業を通じて、自分がいかに多くのポジティブな側面を持っているかを客観的に認識することができます。
このリストは、他人から褒められたときに「自分には、確かにそういう良い部分もあるかもしれない」と、褒め言葉を受け入れるための土台となります。
2. ポジティブ日記をつける
一日の終わりに、その日にあった「良かったこと」「嬉しかったこと」「感謝したこと」を3つ書き出す習慣です。
これを「スリー・グッド・シングス」と呼びます。
例えば、「ランチで食べたパスタが美味しかった」「電車の席を譲ってもらえた」「夕焼けが綺麗だった」など、日常の小さな幸せに目を向ける練習です。
この習慣を続けることで、脳は自然とポジティブな出来事を探すようになり、物事の良い側面に気づきやすい思考回路が作られていきます。
ネガティブな出来事よりもポジティブな出来事を記憶に留める癖がつけば、褒め言葉というポジティブな情報も受け入れやすくなります。
3. リフレーミングを実践する
リフレーミングとは、ある出来事や状況を、異なる視点(フレーム)から捉え直すことです。
例えば、褒められたときに「お世辞を言われている」とネガティブに捉えるのではなく、「相手は自分を元気づけようとしてくれているのかもしれない」「場の雰囲気を良くしようとしてくれているんだな」というように、相手の善意の側面から捉え直してみるのです。
自分の思考の癖に気づき、意識的に別の視点を探す練習をすることで、自動的なネガティブ思考から抜け出すことができます。
これらの改善策は、一朝一夕に効果が出るものではありません。
筋力トレーニングのように、毎日少しずつ継続することで、徐々に心の筋肉、つまりポジティブな思考力が鍛えられていきます。
焦らず、自分のペースで取り組んでいくことが大切です。
褒められるのが苦手な自分と向き合う
これまで、褒められるのが苦手な心理的理由や、具体的な克服法について解説してきました。
様々なテクニックや思考法を試すことは非常に重要ですが、最後に最も大切なのは、「褒められるのが苦手な自分」そのものを否定せず、まずは受け入れてあげることです。
「なぜ自分は素直に喜べないのだろう」「こんな性格を直さなければ」と自分を責めてしまうと、自己肯定感はさらに低下し、問題はより深刻になってしまいます。
苦手だと感じるのには、これまで述べてきたように、あなたなりの理由や背景が必ずあるのです。
それは、あなたが慎重で、思慮深い性格であることの裏返しなのかもしれません。
あるいは、他人の気持ちに敏感で、周囲との調和を大切にする優しい性格だからこそ、目立つことをためらってしまうのかもしれません。
まずは、「自分は、褒められるのが少し苦手なんだな。それには、こういう理由があるのかもしれない」と、自分自身を客観的に理解し、共感してあげましょう。
自分を責めるのをやめ、自分の感情の動きを優しく見守る姿勢が、変化への第一歩です。
その上で、完璧を目指さないことも重要です。
この記事で紹介した対処法を、すべて完璧にこなす必要はありません。
「今日は『ありがとう』が言えた」「今回は少しだけ素直に嬉しいと思えた」といった、小さな一歩を自分で見つけて、褒めてあげてください。
他人から褒められるのが苦手なら、まずは自分で自分を褒める達人になるのです。
苦手意識を無理やり克服しようと焦るのではなく、時間をかけてゆっくりと付き合っていく、というスタンスでいることが、結果的に最も早い改善への道となります。
褒められるのが苦手という特性は、あなたの個性の一部です。
それを完全に消し去る必要はありません。
その特性を理解し、受け入れた上で、少しずつコミュニケーションを円滑にするスキルを身につけていく。
そうすることで、あなたはあなたらしさを失わずに、より軽やかに、そして豊かに人との関わりを築いていけるようになるはずです。
- 褒められるのが苦手な背景には複雑な心理がある
- 言葉の裏を読み疑ってしまうのは過去の経験が影響
- 自己肯定感の低さが褒め言葉を拒絶させる原因に
- 注目を浴びる羞恥心から褒められるのを避ける性格もある
- 褒め言葉が次へのプレッシャーとなり重荷に感じる
- 幼少期の育ちや家庭環境が苦手意識の根源になることも
- 克服の第一歩は反射的に「ありがとう」と感謝を伝える練習
- 感謝に一言加える上手な返し方で会話がスムーズになる
- 仕事での評価は人格ではなく具体的な成果へのものと捉える
- チームの成果として感謝を述べると受け入れやすい
- 恋愛での褒め言葉はパートナーの愛情表現と理解する
- 自分の長所リストアップやポジティブ日記で思考を改善
- リフレーミングで物事を多角的に捉える癖をつける
- 苦手な自分を責めずにありのまま受け入れることが最も重要
- 完璧を目指さず小さな成功体験を自分で褒めて積み重ねる