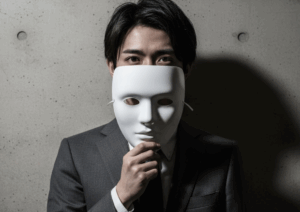SNSを開くたびに、誰かの「いいね」の数やキラキラした投稿が気になってしまう。
自分の投稿への反応が少ないと、なんだか落ち着かない。
そんな、SNSで承認欲求に振り回されて、心が疲れたと感じている方はいませんか。
現代社会において、SNSはコミュニケーションツールとして欠かせないものとなりましたが、その一方で、私たちの心に大きな影響を与えています。
特に、SNSで承認欲求が満たされない苦しみや、他人と比較してしまうストレスは、多くの人が抱える悩みではないでしょうか。
この承認欲求が暴走してしまうと、一体どのような末路を辿るのでしょうか。
本記事では、まずSNSで承認欲求が生まれる心理的な原因を深掘りし、なぜ心が満たされないのか、自己肯定感とどう関係しているのかを解き明かします。
そして、もうSNSなんてやめたい、と思うほど疲れた心を軽くするための具体的な対処法や、これからの時代における承認欲求との賢い付き合い方について詳しく解説していきます。
他人の評価を気にしない自分になるためのヒントが、ここにあります。
- SNSで承認欲求が生まれる心理的な背景
- 承認欲求が満たされない根本的な原因
- 自己肯定感の低さが承認欲求に与える影響
- SNS疲れから心を解放するための具体的なステップ
- 承認欲求が暴走したときのリスクと末路
- 承認欲求を完全に消すのではなく上手に付き合う方法
- 他人の評価を気にしない自分になるための思考法
目次
SNSで承認欲求が強まる心理的な原因とは
- 「いいね」の数を気にする心理の正体
- 承認欲求が満たされないと感じる理由
- 自己肯定感の低さが引き起こす影響
- 他人の投稿を見て疲れたと感じる瞬間
- 承認欲求が暴走した先にある末路
「いいね」の数を気にする心理の正体

SNSで投稿をした後、何度も通知を確認し、「いいね」の数に一喜一憂してしまう経験は、多くの人にあるのではないでしょうか。
この行動の裏には、人間の根源的な欲求である「社会的承認」を求める心理が深く関わっています。
そもそも承認欲求とは、心理学者アブラハム・マズローが提唱した欲求5段階説の中の「承認(尊重)の欲求」に該当するものです。
これは、他者から価値ある存在だと認められたい、尊敬されたいという欲求であり、人間が社会的な生き物である以上、ごく自然な感情と言えるでしょう。
しかし、SNSの登場により、この欲求が可視化され、より強く刺激されるようになりました。
「いいね」というシステムは、他者からの承認を数値という非常に分かりやすい形で示します。
そのため、私たちは「いいね」の数を自分の価値の指標として捉えやすくなってしまうのです。
脳科学的には、「いいね」を受け取ると、脳内ではドーパミンという快楽物質が放出されることが分かっています。
ドーパミンは報酬や快感、意欲に関わる神経伝達物質であり、これが放出されることで私たちは心地よさを感じます。
つまり、「いいね」をもらうことは、脳にとってご褒美のようなものなのです。
この仕組みは、ギャンブルやゲームの依存症と似た構造を持っており、一度快感を覚えると、さらなる快感を求めて投稿を繰り返すというサイクルに陥りやすくなります。
結果として、「いいね」の数が少ないと不安になったり、もっと多くの「いいね」を得るために過激な投稿をしたりと、行動がエスカレートしていく可能性があるわけです。
また、SNS上での自己呈示も重要な要素です。
人々はSNS上で「理想の自分」を演出しようとします。
充実したプライベート、素晴らしいキャリア、完璧な人間関係など、現実の自分とは少し違う、あるいは一部分を切り取って誇張した姿を投稿します。
この「理想の自分」が他者から承認されることで、一時的に自尊心が満たされる感覚を得られるのです。
しかし、これはあくまで仮想空間での承認であり、現実の自分とのギャップが大きければ大きいほど、心の空虚感は増していくことになります。
このように、「いいね」の数を気にする心理の正体は、人間の本能的な承認欲求が、SNSの持つ即時的で quantifiable(数値化可能)な評価システムと、脳の報酬系回路によって増幅された結果であると言えるでしょう。
自分の価値を他者の評価に委ねてしまう危うさを理解することが、この心理から抜け出す第一歩となります。
承認欲求が満たされないと感じる理由
SNSでどれだけ「いいね」を集めても、フォロワーが増えても、なぜか心が満たされない。
むしろ、投稿すればするほど、渇望感が強くなるように感じるのはなぜでしょうか。
その理由は、SNSで得られる承認が、本質的な心の充足には繋がりにくい性質を持っているからです。
主な理由として、以下の三つの点が挙げられます。
1. 他者承認への依存
SNSで得られる承認は、「他者承認」です。
これは、他者からの評価によって自分の価値を認識しようとするものであり、その評価軸は常に自分以外の誰かが握っています。
他人の気まぐれな「いいね」やコメントに一喜一憂する状態は、いわば感情のコントロールを他人に委ねているようなものです。
このような他者からの承認は、一時的な高揚感はもたらしますが、持続的な満足感には繋がりません。
なぜなら、評価が途絶えれば、すぐに不安や自己否定に陥ってしまうからです。
本当に心を満たすために必要なのは、「自己承認」、つまり自分で自分を認め、価値を信じる感覚です。
自己承認ができていれば、他者からの評価に過度に依存することなく、心の安定を保つことができます。
SNSは、この自己承認を育む機会を奪い、他者承認を求めるループへと私たちを誘い込む傾向があるのです。
2. 比較という無限のゲーム
SNSは、本質的に「他者との比較」を助長するプラットフォームです。
タイムラインを眺めれば、友人やインフルエンサーたちの華やかな日常が次々と目に飛び込んできます。
旅行、高級レストラン、キャリアの成功、幸せな家庭。それらの投稿は、たとえそれが演出された一部分であったとしても、無意識のうちに自分の人生と比較してしまいます。
「あの人に比べて自分は…」という思考は、自己肯定感を著しく低下させます。
社会心理学における社会的比較理論では、人は自分を評価するために他者と自分を比較する傾向があるとされています。
特に、自分より優れていると感じる相手と比べる「上方比較」は、劣等感や嫉妬心を生み出しやすいのです。
SNSの世界では、常に自分より「上」の存在が見つかります。
フォロワー数、いいねの数、生活の質。どれだけ頑張っても、上には上がいるという無限の比較ゲームに参加させられることで、承認欲求は永遠に満たされることがありません。
3. 仮想と現実の乖離
前述の通り、SNSでは多くの人が「理想の自分」を演出します。
その演出された自分への承認が増えれば増えるほど、現実のありのままの自分との間にギャップが生まれます。
SNS上では人気者で、常にポジティブな発信をしている人が、現実では孤独感や不安を抱えているケースは少なくありません。
この乖離が大きくなると、「本当の自分は誰にも認められていない」という感覚が強まり、心の空虚さは増していきます。
SNSでの承認は、あくまで「演出された自分」に向けられたものであり、「ありのままの自分」が受け入れられているわけではないと感じてしまうのです。
この感覚が、どれだけ賞賛されても心が満たされない根本的な原因となります。
これらの理由から、SNSでの承認欲求は、追いかければ追いかけるほど逃げていく蜃気楼のようなものだと言えるでしょう。
真の満足感は、SNSの外、つまり自分自身の内側に見出す必要があるのです。
自己肯定感の低さが引き起こす影響

SNSで承認欲求が過剰になってしまう背景には、多くの場合、「自己肯定感の低さ」が隠れています。
自己肯定感とは、ありのままの自分を肯定し、価値ある存在として受け入れる感覚のことです。
この感覚が低いと、自分の価値を自分自身で見出すことが難しくなり、その不足分を外部からの評価、特にSNSでの承認によって補おうとする傾向が強まります。
自己肯定感の低さは、SNSの利用において様々な悪影響を引き起こします。
1. 他者評価への過剰な依存
自己肯定感が低い人は、自分の判断や価値観に自信が持てません。
そのため、「他者からどう見られているか」が行動の基準になりがちです。
SNSの投稿内容も、「みんなにウケるのは何か」「いいねがたくさん貰えそうなのはどれか」という視点で選ばれるようになります。
自分の「好き」や「楽しい」という感情よりも、他者からの承認を優先してしまうのです。
その結果、投稿への反応が少ないと、「自分は価値がないのではないか」「嫌われているのではないか」と深刻に落ち込み、精神的に不安定になります。
まさに、自分の心の天秤を他人の手に委ねてしまっている状態です。
2. ネガティブな比較と嫉妬
自己肯定感が低いと、他人の成功や幸福を素直に喜べず、自分と比較して劣等感を抱きやすくなります。
SNSで友人が楽しそうにしている投稿を見ると、「それに比べて自分はなんて惨めなんだろう」と感じたり、嫉妬心から攻撃的なコメントをしたくなったりすることもあります。
このネガティブな感情は、さらに自己肯定感を低下させるという悪循環を生み出します。
本来であれば、他人は他人、自分は自分と切り離して考えられるはずですが、心の基盤が揺らいでいると、他人の輝きが自分の影を濃くするように感じられてしまうのです。
3. 完璧主義と投稿への過剰なこだわり
「完璧な自分でなければ認められない」という思い込みも、自己肯定感の低さからくる特徴です。
SNSに投稿する写真一枚に対しても、何度も撮り直し、完璧な加工を施さなければ気が済みません。
文章も、一言一句にこだわり、誤解を招かないか、批判されないかと過剰に気にしてしまいます。
このような完璧主義は、SNSを純粋に楽しむことを妨げ、投稿すること自体が大きなストレスとなっていきます。
少しの欠点も許せず、常に理想の自分を演じ続けなければならないというプレッシャーは、心をすり減らす大きな原因です。
4. 承認欲求を満たすための自己犠牲的な行動
自己肯定感が低いと、承認を得るためなら自己犠牲も厭わなくなります。
例えば、経済的に無理をして高価なブランド品を購入して投稿したり、本当は乗り気ではない集まりにも参加して「リア充」をアピールしたりします。
さらに深刻なケースでは、注目を集めるために危険な行為に及んだり、他人を傷つけるような投稿をしてしまうこともあります。
これらはすべて、歪んだ形で承認を得ようとする心の叫びとも言えますが、その代償は計り知れません。
このように、自己肯定感の低さはSNSでの承認欲求を増幅させ、精神的な不安定さや不適切な行動を引き起こす引き金となります。
SNSとの健全な付き合い方を考える上で、自分自身の自己肯定感と向き合うことは避けて通れない重要な課題なのです。
他人の投稿を見て疲れたと感じる瞬間
何気なくSNSを開いたはずが、気づけば気分が落ち込んでいたり、どっと疲れを感じたりする。
多くの人が経験するこの「SNS疲れ」は、特に他人の投稿に触れることで引き起こされます。
具体的にどのような瞬間に、私たちは疲れを感じるのでしょうか。
その心理的なメカニズムと共に見ていきましょう。
1. 「キラキラ投稿」による上方比較
最も一般的な疲れの原因は、いわゆる「キラキラ投稿」にあります。
海外旅行、高級ディナー、ブランド品、パートナーとの記念日など、他人の幸福や成功を象徴するような投稿を目にしたとき、無意識に自分の現状と比較してしまいます。
「みんな楽しそうなのに、自分だけが平凡で退屈な毎日を送っている」
「同年代の友人は結婚して幸せそうなのに、自分は…」
このような「上方比較」は、劣等感や焦燥感、嫉妬といったネガティブな感情を直接的に刺激します。
SNSに投稿されるのは、その人の人生のハイライト、つまり最も輝いている瞬間を切り取ったものです。
頭ではそれが全てではないと分かっていても、連続してそうした情報に触れることで、あたかもそれがその人の日常であるかのように錯覚してしまいます。
他人のハイライトと自分の日常を比較すれば、落ち込むのは当然と言えるでしょう。
2. 義務感からくるコミュニケーション疲れ
SNSは本来、自由なコミュニケーションの場であるはずですが、いつしか「いいねを返さなければ」「コメントに返信しなければ」といった義務感に変わってしまうことがあります。
特に、フォロー関係にある人々の投稿すべてに目を通し、適切に反応しようとすると、それはもはや楽しむためのツールではなく、一つの「仕事」のようになってしまいます。
「この人の投稿に反応しないと、関係が悪くなるかもしれない」
「自分の投稿に『いいね』をくれたから、お返しをしないと失礼だ」
こうした人間関係の維持コストが、精神的な負担となってのしかかります。
また、興味のない投稿や、不快に感じる投稿が流れてきても、関係性を気にして見続けてしまうことも、心を消耗させる一因です。
3. 情報過多による脳の疲労
SNSのタイムラインは、膨大な情報が絶え間なく流れてくる場所です。
友人たちの近況、ニュース、広告、インフルエンサーのおすすめ商品など、多種多様な情報が混在しています。
私たちの脳は、これらの情報を無意識のうちに処理し続けています。
特にスマートフォンは、いつでもどこでも手軽に情報にアクセスできるため、脳が休まる時間がありません。
この絶え間ない情報の洪水は、脳に過剰な負荷をかけ、集中力の低下や判断力の鈍化、そして精神的な疲労感を引き起こします。
何か特定の目的もなく、ただ惰性でSNSをスクロールし続けている時、脳は休息どころか、フル回転で働き続けているのです。
これらの瞬間を振り返ってみると、SNS疲れは、他者との比較による心理的ダメージ、人間関係の維持コスト、そして単純な情報過多という三つの側面から成り立っていることが分かります。
自分がどのタイプの疲れを感じやすいのかを自覚することが、対策を考える上で重要になります。
承認欲求が暴走した先にある末路
SNSで承認欲求を追い求めることは、誰にでもある自然な心理です。
しかし、その欲求が適切なコントロールを失い、「暴走」し始めると、その先には深刻な結末が待ち受けている可能性があります。
それは個人の精神的な問題にとどまらず、社会的、経済的な破綻にまで至るケースも少なくありません。
承認欲求が暴走した先にある、代表的な末路をいくつか見ていきましょう。
1. 精神的な健康の崩壊
最も深刻な末路の一つが、精神的な健康を損なうことです。
常に他者の評価を気にし、「いいね」の数に一喜一憂する生活は、自律神経のバランスを崩し、慢性的なストレス状態を引き起こします。
その結果、以下のような精神疾患に繋がるリスクが高まります。
- うつ病:他者との比較による劣等感や、批判的なコメントによる精神的ダメージが蓄積し、無気力、抑うつ状態に陥る。
- 不安障害:投稿への反応が気になって常に不安を感じたり、SNSを見ていないと取り残されるような感覚(FOMO: Fear of Missing Out)に苛まれたりする。
- 依存症:「いいね」によるドーパミンの快感が忘れられず、SNSから離れられなくなる。日常生活に支障をきたしても、SNSを優先してしまう。
仮想空間での評価のために、現実世界の自分が蝕まれていくという、本末転倒な事態に陥るのです。
2. 人間関係の破綻
SNS上での関係を優先するあまり、現実世界での大切な人間関係が壊れてしまうことがあります。
友人や家族と過ごしている時間でさえ、スマートフォンを片時も手放さず、SNSのチェックに夢中になる。
投稿内容も、現実の友人に見せるためのものではなく、不特定多数のフォロワーからの「ウケ」を狙ったものが中心になります。
また、友人や知人の投稿に対して過剰な嫉妬心を抱き、陰で悪口を言ったり、関係を断ってしまったりすることもあります。
さらには、SNS上での見栄のために嘘をつき、それが発覚して信頼を失うケースも後を絶ちません。
承認欲求の暴走は、本来大切にすべき身近な人々との絆を、脆くも崩壊させてしまう力を持っているのです。
3. 経済的な困窮
「リア充」を演出し、他者からの羨望を集めるために、身の丈に合わない消費を繰り返すようになるのも、危険な兆候です。
毎週末のように高級レストランに行き、海外旅行の写真を投稿し、次々と新作のブランド品を身につける。
これらの費用を捻出するために、貯金を切り崩したり、さらには借金を重ねたりするようになります。
SNS上での「いいね」という、実体のない承認を得るために、現実の生活基盤が揺らいでいくのです。
インスタグラムなどの写真がメインのSNSでは、特にこの「見栄消費」の傾向が強く、自己破産に至るケースも報告されています。
4. 社会的信用の失墜と法的トラブル
承認欲求が極限まで暴走すると、注目を集めるためなら手段を選ばなくなります。
過激なパフォーマンスや迷惑行為を撮影して投稿する「炎上系」の行動は、その典型です。
一時的に多くの注目を集めることはできるかもしれませんが、その代償として社会的信用を完全に失います。
場合によっては、器物損壊罪や威力業務妨害罪といった法的な責任を問われ、前科がつくことさえあります。
また、他人を誹謗中傷することで注目を集めようとする行為も、名誉毀損で訴えられるリスクを伴います。
ほんの少しの承認欲求が、人生を大きく狂わせてしまう危険性は、誰にでも潜んでいるのです。
これらの末路は、決して他人事ではありません。
SNSとの付き合い方に少しでも危うさを感じたら、早期に立ち止まり、自分の心と向き合う勇気が必要です。
SNSでの承認欲求とうまく付き合うための対処法
- 承認欲求をなくすのではなく受け入れる
- 他人の評価を気にしないための考え方
- 承認欲求との上手な付き合い方を見つける
- SNSをやめたいと思った時に試すこと
- これからのSNSでの承認欲求との向き合い方
承認欲求をなくすのではなく受け入れる

SNSで承認欲求に振り回され、疲弊してしまうと、「この欲求さえなければ楽になれるのに」と考えてしまいがちです。
しかし、承認欲求を完全になくそうとすることは、現実的ではありませんし、必ずしも健全なアプローチとは言えません。
なぜなら、前述の通り、承認欲求は人間が社会生活を営む上で、ごく自然に備わっている本能的な欲求だからです。
問題なのは承認欲求そのものではなく、その欲求が肥大化し、コントロールできなくなっている状態です。
したがって、目指すべきは「承認欲求の消去」ではなく、「承認欲求との上手な共存」です。
その第一歩として、まずは「自分には承認欲求がある」という事実を、ありのままに受け入れることから始めましょう。
自分の感情を否定しない
「いいねが欲しいと思ってしまう自分はダメだ」
「他人を羨んでしまうなんて、心が狭い」
このように、承認欲求から生まれる感情を自分でジャッジし、否定してしまうと、自己嫌悪に陥り、かえって苦しくなります。
そうではなく、「ああ、今自分は認められたいんだな」「他人の投稿を見て、羨ましいと感じているな」と、自分の感情を客観的に観察し、そのまま認めてあげることが大切です。
感情に良いも悪いもありません。
それは天気のようなもので、自然に湧き上がってくるものです。
自分の感情を否定せず、ただ「そう感じているんだね」と受け止めるだけで、心は少し軽くなります。
これは、マインドフルネスやアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)といった心理療法でも重視される考え方です。
承認欲求のルーツを探る
なぜ自分はこれほどまでに承認を求めているのだろうか、と少しだけ深く自分の内面を探ってみるのも有効です。
もしかしたら、幼少期の経験や、過去の成功体験、あるいは現在の環境が影響しているのかもしれません。
例えば、以下のような要因が考えられます。
- 幼少期に親からあまり褒めてもらえなかった。
- 学生時代、スポーツや勉強で成果を出すと周りから認められた経験がある。
- 現在の職場では、正当な評価をされていないと感じている。
- 現実の生活で、孤独感や疎外感を抱えている。
自分の承認欲求の源泉を理解することで、漠然とした渇望の正体が見えてきます。
正体が分かれば、対処法もおのずと見つけやすくなります。
例えば、職場での評価不足が原因なのであれば、SNSで承認を求めるのではなく、上司と面談の機会を設けたり、転職を考えたりする方が、より根本的な解決に繋がるかもしれません。
このように、承認欲求を敵視して戦うのではなく、自分を理解するためのサインとして捉え直すことが重要です。
「承認欲求があってもいい。でも、それに振り回される必要はない」というスタンスを持つこと。
この受容的な態度こそが、SNSで承認欲求とうまく付き合っていくための、最も重要な土台となるのです。
他人の評価を気にしないための考え方
SNSで心が疲弊する大きな原因は、「他人の評価」に自分の価値を委ねてしまうことです。
「いいね」の数、フォロワー数、コメントの内容。これら他者からの反応によって、自分の気分がジェットコースターのように乱高下してしまう。
この状態から抜け出し、心の平穏を取り戻すためには、他人の評価と自分の価値を切り離す思考法を身につける必要があります。
すぐに完璧にできるようになるのは難しいかもしれませんが、意識することで少しずつ変化が生まれます。
1. 「課題の分離」を実践する
心理学者アルフレッド・アドラーが提唱した「課題の分離」という考え方は、非常に有効です。
これは、「自分の課題」と「他者の課題」を明確に分けるという考え方です。
SNSに当てはめてみましょう。
自分の考えや好きなことを投稿するのは「自分の課題」です。
しかし、その投稿を見た他者がどう感じ、どう評価(いいねを押す、押さない、コメントする等)するかは、その人自身の問題、つまり「他者の課題」です。
私たちは他者の課題に介入することはできません。
それなのに、他者の課題である「評価」をコントロールしようとするから苦しくなるのです。
「自分はここまで。ここから先は相手の領域」と心の中で線引きをする練習をしてみましょう。
自分がコントロールできるのは、自分の投稿内容と、それに対する自分の心の持ちようだけです。
2. 評価軸を自分の中に取り戻す
他人の評価を気にしなくなるためには、自分自身の「評価軸」をしっかりと持つことが不可欠です。
他人の「いいね」ではなく、自分の「好き」を基準に行動するということです。
投稿する前に、自問自答してみましょう。
「私は、誰からの『いいね』がなくても、本当にこれを投稿したいだろうか?」
「これは、他人のためではなく、自分のための記録や表現だろうか?」
この問いに「イエス」と答えられるものだけを投稿するように心がけると、SNSとの付き合い方が大きく変わってきます。
他者からの承認を目的とするのではなく、自分の楽しみや学び、成長の記録としてSNSを活用するのです。
そうすれば、反応の数は気にならなくなり、たとえ批判的なコメントが来たとしても、「自分はこう思うから、これでいい」と、どっしりと構えていられるようになります。
3. 全員に好かれようとしない
「八方美人」という言葉があるように、すべての人から好かれ、認められようとすることは、不可能なだけでなく、多大な精神的エネルギーを消耗します。
SNSの世界では、不特定多数の様々な価値観を持つ人々と繋がります。
あなたの投稿を素晴らしいと感じる人もいれば、何とも思わない人、あるいは不快に感じる人さえいるかもしれません。
それは、ごく自然なことです。
「10人いれば、1人は自分を批判し、2人は自分と気が合い、残りの7人は自分のことなど気にも留めない」というくらいの気持ちでいると、心が楽になります。
たった一人の批判的な意見に心を痛めるのではなく、自分のことを理解し、応援してくれる少数の人々との繋がりを大切にする方が、よほど建設的です。
他人の評価という不確かなものに心を揺さぶられるのではなく、自分でコントロール可能な「自分の課題」に集中し、自分自身の価値観を大切にする。
この思考の転換が、SNSの呪縛からあなたを解放してくれる鍵となるでしょう。
承認欲求との上手な付き合い方を見つける

承認欲求を受け入れ、他人の評価から距離を置く心の準備ができたら、次はいよいよ具体的な行動に移していきましょう。
SNSで承認欲求と上手に付き合っていくためには、SNSの使い方そのものを見直し、自分なりのルールを作ることが効果的です。
ここでは、今日から実践できる具体的な付き合い方のヒントをいくつかご紹介します。
1. デジタルデトックスを試す
四六時中SNSに接続している状態では、心が休まる暇がありません。
意図的にSNSから離れる時間を作る「デジタルデトックス」は、非常に有効な方法です。
最初は短い時間からでも構いません。
例えば、以下のようなルールを試してみてはいかがでしょうか。
- 食事中や入浴中はスマートフォンを見ない。
- 寝る前の1時間はSNSを開かない(睡眠の質の向上にも繋がります)。
- 週に一度、半日だけSNSを完全にオフにする曜日を作る。
- 通知設定をオフにして、自分が見たいタイミングでだけアプリを開くようにする。
SNSから物理的に距離を置くことで、いかに自分が無意識に情報を追いかけていたか、そしてSNSがなくても世界は何も変わらないという事実に気づくことができます。
空いた時間で、読書をしたり、散歩をしたりと、現実世界での活動に目を向けることで、心のバランスが整っていきます。
2. SNSの利用目的を明確にする
「なんとなく」SNSを使っていると、他人の投稿に振り回され、時間を浪費してしまいがちです。
そこで、自分が何のためにSNSを使うのか、その目的を明確にしてみましょう。
例えば、
「遠方の友人との近況報告のため」
「自分の趣味(写真、料理など)の記録と、同じ趣味を持つ人との交流のため」
「仕事に必要な情報収集のため」
といった具体的な目的を設定します。
そして、その目的に沿った使い方を意識するのです。
目的と関係のないアカウントのフォローを外したり、ミュート機能を活用して、タイムラインに流れてくる情報を自分でコントロールすることも重要です。
SNSを「目的を達成するためのツール」として捉え直すことで、受け身の姿勢から、主体的で能動的な使い方へとシフトすることができます。
3. 現実世界での充足感を増やす
SNSで承認欲求が満たされない根本的な原因は、現実世界での自己肯定感や充足感が不足していることにあります。
したがって、最も本質的な解決策は、SNSの外での活動を充実させることです。
どんなに小さなことでも構いません。
新しい趣味を始めてみる、資格の勉強をする、運動習慣を身につける、ボランティア活動に参加するなど、何かに打ち込み、自分で自分を褒めてあげられるような経験を積み重ねていくことが、自己肯定感を育む上で非常に重要です。
また、オンラインでの繋がりだけでなく、家族や親しい友人など、現実世界での対面でのコミュニケーションを大切にしましょう。
ありのままの自分を受け入れてくれる人々と過ごす時間は、SNSでの何千もの「いいね」よりも、はるかに深く心を満たしてくれます。
現実世界が充実してくれば、自然とSNSでの評価は気にならなくなっていくものです。
これらの方法を組み合わせ、自分に合ったスタイルを見つけることで、SNSを「心をすり減らす場所」から、「人生を豊かにするツール」へと変えていくことができるでしょう。
SNSをやめたいと思った時に試すこと
SNSによる疲労がピークに達し、「もうアカウントごと削除してしまいたい」と感じることもあるでしょう。
完全にやめてしまうことも一つの選択肢ですが、その前に試せること、考えるべきことがあります。
衝動的に関係を断ち切ってしまうと、後で後悔したり、必要な繋がりまで失ってしまったりする可能性があるからです。
SNSをやめたい、と思った時に、一度立ち止まって試してほしいステップをご紹介します。
1. 「やめたい理由」を書き出してみる
まず、なぜ自分はSNSをやめたいのか、その理由を具体的に紙に書き出してみましょう。
頭の中で漠然と考えているだけでは、感情的になりがちですが、文字にすることで客観的に自分の状況を整理することができます。
例えば、
- 「Aさんの投稿を見ると、嫉妬してしまって辛い」
- 「投稿への反応がないと、無視されているようで悲しくなる」
- 「気づいたら何時間も見てしまっていて、時間を無駄にしていると感じる」
- 「義務的な『いいね』のやり取りに疲れた」
このように理由を具体化すると、問題の核心が見えてきます。
もしかしたら、問題はSNSそのものではなく、特定の人物との関係性や、自分の時間の使い方にあるのかもしれません。
原因が特定できれば、アカウントを削除するという最終手段を取らなくても、解決策が見つかる可能性があります。
例えば、「Aさんをミュートする」「アプリの使用時間に制限をかける」といった対策で、問題が軽減されるかもしれません。
2. 一時的な「休止期間」を設ける
アカウントをいきなり削除するのではなく、まずは「お休み」をしてみるのも良い方法です。
プロフィールに「しばらく休みます」と一言書き、アプリをスマートフォンからアンインストールしてみましょう。
アカウント自体は残っているので、いつでも再開できます。
この休止期間を1週間、あるいは1ヶ月と設けることで、SNSのない生活が自分にどのような影響を与えるかを試すことができます。
最初は落ち着かないかもしれませんが、数日もすれば、驚くほど心が穏やかになり、自由に使える時間が増えることに気づくでしょう。
そして、休止期間が終わった時に、
「やっぱりSNSがなくても平気だ。このままやめよう」
「特定の情報収集には便利だったから、使い方を限定して再開しよう」
「友人との連絡手段としては必要だから、見る頻度を減らして続けよう」
など、冷静な判断ができるようになります。
感情的な勢いではなく、実体験に基づいた合理的な決断を下すことができるのです。
3. 利用するSNSを絞る・見直す
私たちは、複数のSNSを同時に利用していることが多いです。
しかし、それぞれのSNSには異なる特性があり、自分に与えるストレスの種類も異なります。
写真中心で「キラキラ投稿」が多いInstagramに疲れているのであれば、それをやめ、テキスト中心で趣味の合う人と繋がりやすいX(旧Twitter)だけに絞る、というのも一つの手です。
あるいは、不特定多数との繋がりをやめ、本当に親しい友人だけと繋がるクローズドなSNSや、LINEのようなメッセージングアプリだけを利用するという選択肢もあります。
自分が最もストレスを感じているプラットフォームは何かを見極め、そこから離れるだけでも、精神的な負担は大きく軽減されます。
すべてを断ち切るのではなく、自分にとって有益な部分だけを残すという「選択と集中」の発想が、持続可能なデジタルライフには不可欠です。
SNSをやめたいという感情は、あなたの心が休息を求めている重要なサインです。
その声に耳を傾け、自分にとって最適な距離感を見つけるための機会と捉えましょう。
これからのSNSで承認欲求との向き合い方

これまで、SNSで承認欲求が生まれる心理的な原因から、具体的な対処法までを詳しく見てきました。
SNSが社会に深く根付いた現代において、承認欲求と完全に無縁でいることは難しいでしょう。
大切なのは、その存在を認め、暴走させずに、自分の人生を豊かにする力へと変えていくことです。
これからの時代を生きる私たちが、SNSで承認欲求と健全に向き合っていくために、最後に総括として心に留めておきたい考え方をまとめます。
まず、SNSは現実世界の一部を切り取ったものに過ぎず、決してその人の全てではないという事実を常に意識することが重要です。
他人の輝かしい投稿は、あくまで編集されたハイライトであり、その裏には私たちと同じような悩みや葛藤、平凡な日常が存在します。
他人の虚像と自分の現実を比較し、心を消耗させるのはもうやめにしましょう。
そして、評価の基準を他者の手に委ねるのではなく、自分自身の内側に取り戻すことが何よりも大切です。
他者からの「いいね」の数で自分の価値を測るのではなく、自分が何に喜びを感じ、何を大切にしたいのかという「自分のものさし」をしっかりと持つこと。
その上で、SNSを自己表現や他者との交流を楽しむための「ツール」として、主体的に活用していくのです。
承認欲求は、使い方を間違えれば心を蝕む毒にもなりますが、本来は自己成長や社会貢献へのモチベーションにも繋がる強力なエネルギー源です。
誰かに認められたいという気持ちが、新しいスキルを学ぶきっかけになったり、より良い仕事をしようという意欲に繋がったりすることもあります。
重要なのは、そのエネルギーをSNSという閉じた世界の中だけで満たそうとするのではなく、現実世界での具体的な行動へと昇華させていくことです。
現実での小さな成功体験や、身近な人からの感謝の言葉こそが、揺るぎない自己肯定感を育み、あなたの心を真に満たしてくれるでしょう。
SNSとの付き合い方に正解はありません。
時には距離を置き、時にはツールとして活用する。
自分自身の心の声に耳を傾けながら、あなたにとって最適なバランスを見つけていくことが、これからのSNSで承認欲求との賢い向き合い方と言えるのではないでしょうか。
- SNSで承認欲求は人間の本能的な欲求が可視化されたもの
- 「いいね」は脳内報酬系を刺激し依存性を生む
- 承認欲求が満たされないのは他者承認に依存しているから
- SNSは他者との比較を助長し自己肯定感を下げる
- 自己肯定感の低さが過剰な承認欲求の根本原因
- SNS疲れは比較や情報過多によって引き起こされる
- 承認欲求の暴走は精神や人間関係の破綻を招く
- 承認欲求をなくすのではなく存在を受け入れることが第一歩
- 他者の評価は「他者の課題」と割り切る思考が有効
- 評価軸を自分の中に取り戻し自分の「好き」を大切にする
- デジタルデトックスでSNSと物理的な距離を置く
- SNSの利用目的を明確化し主体的に使う
- 最も重要な対策は現実世界での充足感を増やすこと
- SNSをやめたい時は理由を整理し一時休止を試す
- これからのSNSで承認欲求とは自分なりの距離感で賢く付き合う