
毎日仕事へ行くのがつらい、また怒られるのではないかと憂鬱になる。
そんなふうに、怒られてばかりで疲れたと感じている方も多いのではないでしょうか。
自分の能力が低いからだろうか、どうして自分だけが、と一人で悩みを抱え込んでしまうのは、精神的にもしんどい状況ですよね。
しかし、その原因はあなた一人だけの問題ではないかもしれません。
仕事の環境や上司との関係、あるいは自分でも気づいていない心理的な特徴が影響している可能性も考えられます。
この記事では、怒られてばかりで疲れたと感じる根本的な原因を探り、具体的な対処法を詳しく解説していきます。
なぜ怒られやすいのかという理由や特徴から、HSPのような繊細な気質が関係しているケース、自己肯定感の低さが引き起こす悪循環について深く掘り下げます。
そして、心がしんどいと感じた時にどうすれば良いのか、日々の仕事の中で実践できる気持ちの改善策や、どうしても今の会社が辛い場合に辞めたいと思った時の考え方まで、あなたの悩みに寄り添う対策を網羅しました。
この記事を読めば、怒られることへの過度な恐れを気にしない方法や、上司とのコミュニケーションを円滑にするヒントが見つかるはずです。
一人で抱え込まず、まずはこの記事で紹介する情報を参考に、自分自身の気持ちと向き合う一歩を踏み出してみましょう。
- 怒られてばかりで疲れたと感じる根本的な原因がわかる
- 怒られやすい人に共通する特徴とその背景を理解できる
- HSP気質が仕事のストレスにどう影響するかがわかる
- 自己肯定感を高め、負のスパイラルから抜け出す方法が見つかる
- 精神的に追い詰められた時の危険なサインに気づける
- 怒られた後の具体的な気持ちの切り替え方が身につく
- 現状を改善し、前向きに仕事に取り組むためのヒントが得られる
目次
怒られてばかりで疲れたと感じる原因と心理的背景
- なぜか怒られやすい人の特徴と原因
- 仕事でミスが続いてしまう時の考え方
- HSP気質が影響している可能性も
- 自己肯定感の低さが招く悪循環とは
- 精神的にしんどいと感じた時のサイン
なぜか怒られやすい人の特徴と原因
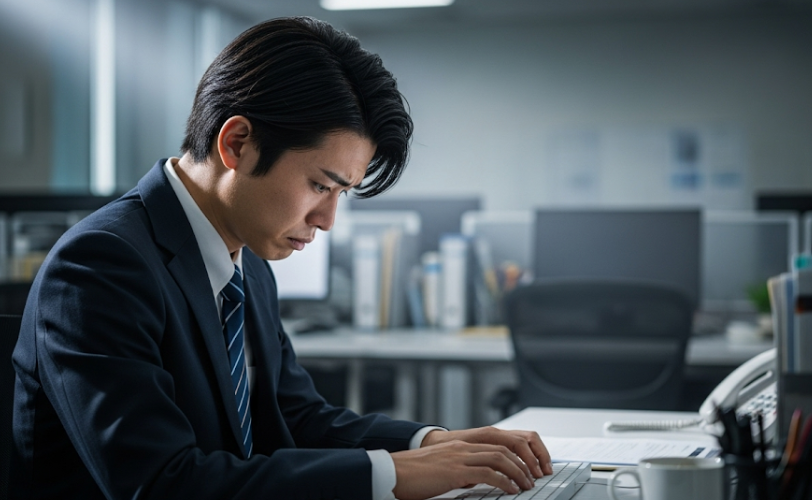
毎日怒られてばかりで疲れたと感じる背景には、いくつかの共通した特徴や原因が潜んでいることがあります。
もちろん、理不尽に怒る側に問題があるケースも少なくありませんが、ここでは自分自身を振り返ることで改善の糸口を見つける視点から解説します。
自分に当てはまる部分がないか、客観的に確認してみましょう。
報告・連絡・相談が不足している
仕事の基本である「報連相」が不足していると、上司や同僚はあなたの仕事の進捗状況を把握できません。
「これくらい大丈夫だろう」「後で報告しよう」といった自己判断が、結果的に大きなトラブルにつながり、怒られる原因になることは非常に多いです。
特に、問題が発生した際にすぐに報告しないことは、事態を悪化させる最大の要因となります。
上司からすれば、「なぜもっと早く言わないんだ」という気持ちになり、信頼を損ねてしまうのです。
質問をしない、または質問の仕方が適切でない
指示された内容がよくわからないまま仕事を進めてしまうと、当然ながら期待された成果とは違うものが出来上がってしまいます。
「質問したら迷惑がられるかもしれない」「こんなことも知らないのかと思われたくない」という気持ちから質問をためらう人は多いですが、結果的に手戻りが増え、余計な時間と労力をかけさせてしまうことになります。
また、質問の仕方も重要です。
自分で全く調べずに丸投げするような質問は相手の時間を奪うため、良い印象を与えません。
まずは自分で調べ、どこがわからないのかを明確にしてから質問する姿勢が大切です。
同じミスを繰り返してしまう
誰にでもミスはありますが、同じミスを何度も繰り返してしまうと、「学習能力がない」「真剣に仕事をしていない」と見なされ、厳しい叱責につながります。
ミスをした後に、なぜそのミスが起きたのかを分析し、再発防止策を立てて実行する、というプロセスを軽視している可能性があります。
メモを取らなかったり、自分なりのチェックリストを作成しなかったりと、ミスを防ぐための具体的な行動を怠っているのかもしれません。
ミスの原因を自分なりに分析し、対策を講じることが成長への第一歩と言えるでしょう。
自信がなさそうに見える
声が小さかったり、視線が泳いでいたり、いつもおどおどした態度を取っていたりすると、相手に「この人に任せて大丈夫だろうか」という不安を与えてしまいます。
自信のなさが態度に表れると、頼りない印象を与え、結果的に上司の過度な介入や叱責を招くことがあります。
たとえ自信がなくても、意識してハキハキと話したり、相手の目を見て話したりするだけで、印象は大きく変わるものです。
まずは形から入ることも、時には重要な改善策となります。
仕事でミスが続いてしまう時の考え方
仕事でミスが続くと、自己嫌悪に陥り、「自分はなんてダメなんだ」と落ち込んでしまいがちです。
怒られてばかりで疲れたという感情は、このミスの連鎖から生まれることも少なくありません。
しかし、ミスをした後の考え方次第で、その経験を成長の糧に変えることができます。
人格とミスを切り離して考える
最も重要なのは、ミスという「出来事」と、あなた自身の「人格」を同一視しないことです。
上司から厳しく叱責されると、まるで自分自身の全人格を否定されたかのように感じてしまうかもしれません。
しかし、指摘されているのはあくまで「その仕事のやり方」や「起きたミスという事実」に対してです。
「私は仕事ができない人間だ」と考えるのではなく、「今回はこの作業でミスをしてしまった」と事実だけを客観的に捉えるように意識しましょう。
自分を責めすぎず、事実と感情を切り分けることで、冷静に次の対策を考える余裕が生まれます。
ミスの原因を客観的に分析する
落ち込むだけでは、何も解決しません。
なぜそのミスが起きたのか、具体的な原因を分析することが不可欠です。
- 知識不足:そもそもやり方を知らなかったのか。
- 確認不足:思い込みで進めてしまい、チェックを怠ったのか。
- 時間不足:スケジュールがタイトで、焦って作業してしまったのか。
- 情報不足:必要な情報が与えられていなかったのか。
- 体調不良:疲労や睡眠不足で集中力が低下していたのか。
このように原因を細分化していくと、具体的な対策が見えてきます。
知識不足ならマニュアルを読み込む、確認不足ならチェックリストを作るなど、次の行動につなげやすくなります。
完璧主義をやめる
ミスを極端に恐れる完璧主義な人ほど、一度のミスで大きく落ち込み、次の行動に萎縮してしまう傾向があります。
しかし、人間である以上、100%完璧な仕事をし続けることは不可能です。
特に新しい仕事や慣れない業務であれば、ミスをするのはある意味当然のことです。
「ミスをしないこと」を目標にするのではなく、「ミスをしたら素早く報告し、次から繰り返さないこと」を目標に切り替えましょう。
80点の完成度でも良いので、まずは一度上司に確認してもらうなど、途中でフィードバックを求めることも有効な手段です。
これにより、最終段階で大きな手戻りが発生するリスクを減らすことができます。
HSP気質が影響している可能性も

もしあなたが、他の人よりも怒られた時の落ち込みが激しかったり、相手の些細な言動に深く傷ついたりすることが多いなら、それはHSP(Highly Sensitive Person)という気質が影響しているのかもしれません。
HSPは病気ではなく、生まれ持った特性の一つです。
怒られてばかりで疲れたと感じる背景に、この気質が隠れている可能性について考えてみましょう。
HSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)とは?
HSPは、心理学者のエレイン・アーロン博士が提唱した概念で、人口の約15~20%、つまり5人に1人程度がこの気質を持っているとされています。
HSPには、主に以下の4つの特徴があると定義されています。
- 深く処理する(Deeply processing):物事を深く、多角的に考える。
- 過剰に刺激を受けやすい(Overstimulated):光、音、匂いなどの外部刺激や、他人の感情に敏感に反応し、疲れやすい。
- 感情反応が強く、共感力が高い(Emotionally responsive and empathetic):他人の喜怒哀楽を自分のことのように感じ取りやすい。
- 些細な刺激を察知する(Sensing the subtle):周囲の雰囲気や人の表情、声のトーンなど、細かい変化によく気づく。
これらの特徴を持つHSPの人は、感受性が豊かで思慮深いという長所がある一方で、刺激の多い環境では人一倍疲れやすいという側面も持っています。
なぜHSPは怒られると人一倍つらく感じるのか
HSPの人が怒られると、他の人よりも精神的なダメージを大きく受けてしまうのは、その気質が大きく関係しています。
まず、共感力が高いため、怒っている相手の感情をダイレクトに受け取ってしまい、まるで自分が攻撃されているかのように感じてしまいます。
また、物事を深く処理する特性から、「なぜ怒られたんだろう」「自分の何がいけなかったんだろう」と長時間にわたって考え込み、頭の中で何度も叱責の場面を反芻してしまいます。
些細な刺激を察知する能力も、上司の不機嫌な表情や声のトーンを敏感に感じ取るため、怒られる前から緊張や不安が高まり、精神的に消耗してしまう原因となります。
これらの特性が組み合わさることで、一度怒られた経験が強いトラウマとなり、仕事への恐怖心につながってしまうのです。
自分の気質を理解し、対策を立てる
もし自分がHSPかもしれないと感じたら、まずはその特性を正しく理解することが第一歩です。
「自分が弱いからだ」と責めるのではなく、「自分はこういう気質だから、疲れやすいんだ」と受け入れることで、心が少し楽になります。
その上で、自分に合った対策を立てていきましょう。
例えば、物理的に刺激を減らすためにイヤホンで静かな音楽を聴いたり、一日に一度は一人になれる静かな場所で休憩したりするなどの工夫が有効です。
また、怒られた後も考え込んでしまう場合は、信頼できる同僚や友人に話を聞いてもらう、趣味に没頭するなど、意識的に思考を切り替える時間を作ることが重要になります。
自己肯定感の低さが招く悪循環とは
怒られてばかりで疲れたと感じている人の多くは、自己肯定感の低さに悩んでいるケースが少なくありません。
自己肯定感とは、ありのままの自分を認め、価値ある存在として受け入れる感覚のことです。
この感覚が低いと、仕事のパフォーマンスにも悪影響を及ぼし、さらなる叱責を招くという負のループに陥りやすくなります。
自己肯定感が低いとどうなるか
自己肯定感が低い人は、常に自分に自信が持てず、以下のような行動や思考に陥りがちです。
- 挑戦を避ける:「どうせ自分には無理だ」と考え、新しい仕事や役割に挑戦することをためらいます。これにより、成長の機会を逃してしまいます。
- 他人の評価を過度に気にする:自分の価値を他人の評価に依存するため、常に周囲の顔色をうかがい、自分の意見を言えなくなります。
- 過度に謝罪する:自分のせいではないことまで「すみません」と謝ってしまい、頼りない印象や責任感がないという誤解を与えてしまうことがあります。
- 褒め言葉を素直に受け取れない:褒められても「お世辞に違いない」「そんなことはないです」と否定してしまい、自己評価をさらに下げてしまいます。
これらの行動は、主体性がない、意欲が低いといったネガティブな印象を周囲に与え、結果的に「もっとしっかりしろ」と怒られる原因を作ってしまうことがあるのです。
「怒られる→自己肯定感が下がる」の悪循環
自己肯定感が低い状態で仕事をしていると、些細なミスでも「やっぱり自分はダメだ」と深刻に受け止め、必要以上に落ち込んでしまいます。
この一連の流れは、抜け出しにくい悪循環を生み出します。
- ミスや叱責:仕事でミスをし、上司から怒られる。
- 自己肯定感の低下:「自分は仕事ができない、価値のない人間だ」と自己評価がさらに下がる。
- 萎縮と不安:「また怒られたらどうしよう」という恐怖心から、行動が消極的・受動的になる。自信なさげな態度が目立つ。
- パフォーマンスの低下:不安や緊張から集中力が散漫になり、普段ならしないようなミスを誘発する。判断力も鈍る。
- 再びミスや叱責:パフォーマンスの低下が原因で新たなミスを犯し、再び怒られる。(1に戻る)
このループにはまり込むと、自分の力だけではなかなか抜け出せなくなり、精神的にどんどん追い詰められてしまいます。
悪循環を断ち切るための第一歩
この悪循環を断ち切るためには、まず自分自身の自己肯定感が低くなっている状態に気づき、それを認めることが重要です。
そして、少しずつでも自己肯定感を育むための行動を始める必要があります。
例えば、「できたことノート」をつけることが有効です。
どんなに小さなことでも構いません。「朝、時間通りに出社できた」「頼まれたコピーを正確に取れた」「〇〇さんに挨拶ができた」など、自分ができたことを毎日書き出していくのです。
これにより、「自分は何もできていないわけではない」という事実を可視化し、少しずつ自信を取り戻すきっかけを作ることができます。
自分を責める時間を、自分を認める時間に変えていく意識が、悪循環を断ち切るための大切な一歩となります。
精神的にしんどいと感じた時のサイン
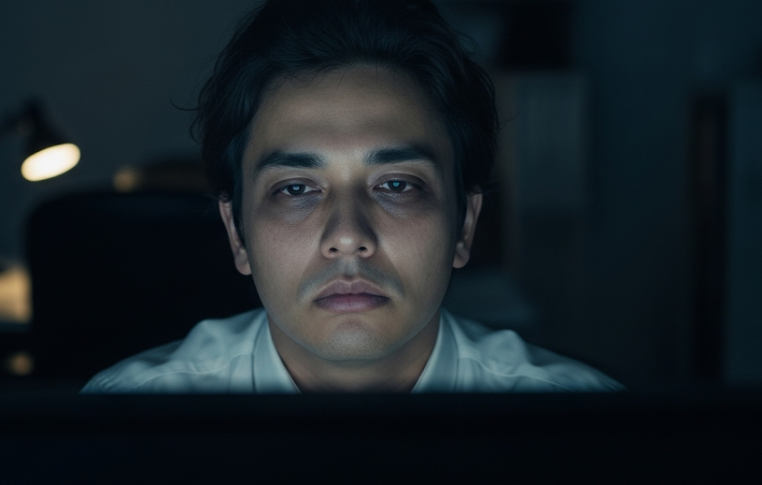
怒られてばかりの日々が続くと、心と体は知らず知らずのうちに限界に近づいていきます。
「まだ大丈夫」「自分が弱いだけだ」と思い込もうとせず、自分が出しているSOSのサインに早期に気づき、適切に対処することが非常に重要です。
ここでは、精神的にしんどい時に現れやすいサインを具体的に紹介します。
もし複数当てはまる場合は、休息や専門家への相談を真剣に検討してください。
身体的なサイン
心の不調は、体に直接的な症状として現れることがよくあります。
これらはストレスに対する体の防御反応ですが、放置すると深刻な病気につながる可能性もあります。
- 睡眠障害:なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、朝早くに目が覚めてしまう、寝ても疲れが取れない。
- 食欲の変化:食欲が全くなくなる、または逆に過食に走ってしまう。特定の物ばかり食べたくなる。
- 原因不明の体調不良:常に頭痛や腹痛、めまい、吐き気がある。耳鳴りがする。病院で検査しても特に異常が見つからない。
- 慢性的な疲労感:十分な休息をとっても、常に体がだるい、重い。朝起きるのが非常につらい。
- 涙もろくなる:何でもないことで急に涙が出てくる。感情のコントロールが難しい。
精神的なサイン
心の状態にも、普段とは違う変化が現れます。
周囲の人から「最近、様子が違うね」と指摘されることもあるかもしれません。
- 意欲の低下:今まで好きだった趣味や活動に全く興味がわかなくなる。何をするのも億劫に感じる(アンヘドニア)。
- 集中力・判断力の低下:仕事中に注意力が散漫になり、簡単なミスが増える。物事を決断できなくなる。本やテレビの内容が頭に入ってこない。
- 気分の落ち込み:理由もなく悲しい気持ちになったり、常に不安や焦りを感じたりする。朝方が特に憂鬱。
- 人との交流を避ける:友人や家族と会うのが億劫になる。一人でいることを好み、社会的に孤立しがちになる。
- ネガティブ思考:物事をすべて悪い方向に考えてしまう。「どうせ自分なんて」といった自己否定的な考えが頭から離れない。
特に「今まで楽しめていたことが楽しめない」という状態は、うつ病のサインの一つでもあり、注意が必要です。
これらのサインに気づいたら
これらのサインは、あなたの心が「もう限界だよ」と叫んでいる証拠です。
決して根性論で乗り切ろうとしないでください。
まずは、意識的に休息を取ることが最優先です。
有給休暇を取得して仕事から物理的に離れる、週末は何もせずにゆっくり過ごすなど、心と体を休ませる時間を作りましょう。
そして、一人で抱え込まずに誰かに相談することも大切です。
家族や信頼できる友人、あるいは会社の産業医やカウンセラー、心療内科や精神科といった専門機関に助けを求めることをためらわないでください。
専門家に相談することは、決して特別なことでも弱いことでもなく、自分自身を守るための賢明な選択です。
怒られてばかりで疲れた状況を乗り越えるための対処法
- 怒られた後の上手な気持ちの切り替え方
- 上司との関係性を改善するコツ
- 今すぐできる「気にしない」ための思考術
- 会社を辞めたいと思った時に考えること
- 怒られてばかりで疲れた自分から卒業する
怒られた後の上手な気持ちの切り替え方

怒られた直後は、誰でも気分が落ち込み、頭が真っ白になってしまうものです。
しかし、そのネガティブな感情を引きずり続けてしまうと、次の仕事にも影響が出てしまい、悪循環に陥りかねません。
ここでは、怒られてしまった後に、できるだけ早く気持ちを切り替えて前を向くための具体的な方法を紹介します。
物理的に場所を移動する
最も手軽で効果的な方法の一つが、その場から物理的に離れることです。
自席に座ったまま落ち込んでいると、ネガティブな思考が堂々巡りしてしまいます。
少しの間、トイレに立ったり、給湯室で一杯お茶を入れたり、可能であれば会社の外に出て数分間新鮮な空気を吸ったりするだけでも、気分転換になります。
場所を変えることで、視覚から入る情報が変わり、思考の切り替えを助けてくれるのです。
事実と感情を書き出して整理する
頭の中が混乱している時は、紙に書き出すことで客観的に状況を整理できます。
ノートや手帳に、以下の2点を分けて書き出してみましょう。
- 事実:「〇〇の書類で、Aというミスをした。その結果、Bという迷惑をかけた。上司からはCという点を指摘された。」
- 感情:「悔しい、悲しい、情けない、腹が立つ、申し訳ない。」
このように書き出すことで、「自分が怒られたのは人格否定ではなく、あくまでAというミスが原因だった」と事実を冷静に認識できます。
また、自分の感情を素直に書き出すことで、気持ちが整理され、少しスッキリする効果もあります(ジャーナリング)。
事実の分析から次のアクション(再発防止策)を考え、感情は書き出すことで一旦脇に置く、という切り分けが重要です。
小さな成功体験を積み重ねる
怒られた後は、自信を喪失している状態です。
そこで、あえて誰でも確実にできるような簡単なタスクから手をつけることをお勧めします。
例えば、デスク周りの整理整頓、簡単なデータ入力、メールの返信など、頭を使わずに完了できる作業が良いでしょう。
「〇〇を完了できた」という小さな成功体験を積み重ねることで、「自分はまだやれる」という感覚を少しずつ取り戻すことができます。
いきなり難しい仕事に戻ろうとせず、簡単なタスクを挟んで助走をつけるイメージです。
信頼できる人に話を聞いてもらう
一人で抱え込んでいると、どんどん視野が狭くなってしまいます。
信頼できる同僚や先輩、あるいは社外の友人や家族に、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなるものです。
この時、アドバイスを求めるというよりは、ただ「話を聞いてほしい」とお願いするのがポイントです。
自分の気持ちを言葉にして誰かに伝える過程で、自分自身の考えが整理されたり、共感してもらうことで「自分だけじゃないんだ」と安心感を得られたりします。
ただし、愚痴が長くなりすぎたり、社内の人間関係に影響が出そうな相手に話したりするのは避けるべきでしょう。
相手を慎重に選ぶことが大切です。
上司との関係性を改善するコツ
「怒られてばかりで疲れた」と感じる原因の多くは、特定の上司との関係性にあることが多いです。
もちろん、パワハラ気質の上司など、根本的に問題がある場合は話が別ですが、コミュニケーションの取り方や仕事への姿勢を少し変えるだけで、関係性が改善されるケースも少なくありません。
ここでは、上司との関係を良好にするための具体的なコツを紹介します。
相手を理解しようと努める
私たちはつい自分の視点から物事を考えがちですが、一度、上司の立場に立って考えてみましょう。
上司には上司の役割と責任があります。
チーム全体の目標達成、部下の育成、さらにその上の上司への報告など、様々なプレッシャーの中で仕事をしています。
あなたを叱責する背景には、「チームとして失敗できない」「部下に成長してほしい」という思いがあるのかもしれません。
また、上司のコミュニケーションスタイル(結論から話してほしいタイプか、過程も説明してほしいタイプかなど)を観察し、それに合わせる努力も有効です。
相手を「ただ怒る人」と決めつけず、その行動の背景を理解しようとすることで、冷静に対応できるようになります。
報連相の質とタイミングを改善する
上司が部下に対して最もストレスを感じるポイントの一つが、報連相の不足です。
これを徹底するだけで、上司の信頼度は格段に上がります。
特に重要なのが、「悪い報告ほど早くする」ことです。
ミスやトラブルが起きた際、隠したり報告を遅らせたりするのが最悪の対応です。
すぐに報告すれば、上司も迅速に対応策を打つことができます。
また、仕事の進捗をこまめに報告することも大切です。
「〇〇の件、現在△△まで進んでいます。次は□□に取り掛かります」のように、定期的に状況を伝えることで、上司は安心感を覚えます。
上司に「あの件どうなってる?」と聞かれる前に、自分から報告する姿勢を心がけましょう。
指示を受ける際にメモを取り、復唱する
指示の聞き間違いや勘違いによるミスは、怒られる典型的なパターンです。
これを防ぐために、上司から指示を受ける際は必ずメモを取る習慣をつけましょう。
そして、指示の最後に「承知いたしました。〇〇というご指示でよろしいでしょうか」と、自分の理解が合っているかを確認(復唱)することが極めて重要です。
この一手間によって、認識のズレを防げるだけでなく、上司に「真剣に話を聞いているな」という真摯な印象を与えることができます。
もし不明な点があれば、その場で「恐れ入ります、△△についてもう少し詳しく教えていただけますでしょうか」と質問しましょう。
後から聞き直すよりも、その場で解決する方が双方にとって効率的です。
今すぐできる「気にしない」ための思考術

怒られたことをいつまでも引きずってしまうのは、精神衛生上非常によくありません。
もちろん、反省すべき点は反省する必要がありますが、必要以上に自分を責めたり、落ち込んだりする必要はないのです。
ここでは、怒られた事実を上手に受け流し、心を軽くするための「気にしない」思考術を紹介します。
課題の分離(アドラー心理学)
「課題の分離」とは、アドラー心理学の中心的な考え方の一つで、「これは誰の課題か?」を冷静に線引きする思考法です。
あなたが仕事でミスをした場合、「ミスを反省し、再発防止策を考える」のは、あなたの課題です。
しかし、そのミスに対して「どのような感情で、どのような言葉を使って怒るか」は、上司の課題です。
もし上司が必要以上に感情的に怒鳴ったり、人格を否定するような言葉を使ったりした場合、それは上司自身の感情コントロールの問題であり、あなたが背負うべき課題ではありません。
「どこまでが自分の責任で、どこからが相手の問題か」を切り分けることで、理不尽な怒りに対して過剰に傷つくのを防げます。
リフレーミング(物事の捉え方を変える)
リフレーミングとは、ある出来事や状況を、異なる視点や枠組みで捉え直すことです。
例えば、「また怒られた、最悪だ」と捉える代わりに、以下のように視点を変えてみます。
- 「自分の弱点に気づく機会をもらえた」
- 「期待されているからこそ、厳しく指導してくれるのかもしれない」
- 「この経験のおかげで、次はもっとうまくやれるだろう」
- 「自分に改善できるポイントが明確になった」
もちろん、無理にポジティブに考える必要はありませんが、一つの出来事には様々な側面があることを知っておくだけでも、気持ちは楽になります。
怒られたというネガティブな事実の中に、一つでも学びや成長の要素を見つけ出す練習をしてみましょう。
自分を客観視する(メタ認知)
メタ認知とは、自分自身の思考や感情を、もう一人の自分が少し離れた場所から客観的に観察しているような状態を指します。
怒られて落ち込んでいる時に、「ああ、今自分は〇〇という言葉に傷ついて、ひどく落ち込んでいるな。心臓がドキドキしている」というように、自分の状態を実況中継するようなイメージです。
感情の渦に飲み込まれるのではなく、自分を客観視することで、感情と自分との間に距離が生まれます。
この距離が、冷静さを取り戻すためのクッションの役割を果たしてくれます。
「落ち込んでも仕方ない、次はどうしようか」と、次のステップに思考を移しやすくなる効果が期待できます。
会社を辞めたいと思った時に考えること
怒られてばかりの毎日が続き、心身ともに疲れ果ててしまうと、「もうこの会社を辞めたい」という気持ちが湧き上がってくるのは自然なことです。
その気持ちから目を背ける必要はありませんが、一時的な感情で衝動的に退職を決めてしまうと、後悔につながる可能性もあります。
ここでは、会社を辞めたいと思った時に、一度立ち止まって冷静に考えるべきポイントを整理します。
問題の所在を明確にする
まず、「辞めたい」と感じる根本的な原因がどこにあるのかを突き詰めて考えてみましょう。
問題の所在によって、取るべき対策は変わってきます。
- 人間関係の問題:特定の上司や同僚との関係が原因か? もしそうなら、部署異動を願い出ることで解決する可能性はないか。
- 仕事内容の問題:現在の仕事が自分の適性や能力に合っていないと感じるか? 会社の他の部署なら、活かせるスキルや興味のある仕事はないか。
- 労働条件・環境の問題:長時間労働や低い給与、会社の文化などが原因か? これは会社全体の問題であり、個人の努力で解決するのは難しいかもしれない。
- 自分自身の問題:どの会社に行っても同じような問題で悩む可能性があるか? スキル不足やコミュニケーションの課題など、自分自身に起因する部分はないか。
原因を冷静に分析することで、退職が唯一の選択肢なのか、それとも社内での解決策があるのかを見極めることができます。
辞めるメリットとデメリットを比較検討する
退職という決断には、必ずメリットとデメリットが伴います。
感情的に「辞めたい」と思っている時でも、一度紙に書き出して客観的に比較してみましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| ・ストレスの原因(上司など)から解放される | ・収入が途絶える(経済的な不安) |
| ・新しい環境で心機一転できる | ・転職活動に時間と労力がかかる |
| ・自分に合った仕事や職場を見つけられる可能性がある | ・次の職場が良い環境である保証はない |
| ・心身の健康を回復させる時間ができる | ・キャリアに空白期間(ブランク)ができる |
このように可視化することで、勢いだけの判断を避け、現実的な視点で自分の状況を評価することができます。
退職する前に準備しておくこと
もし、十分に考えた上で退職の意思が固まったのであれば、次のステップに向けて計画的に準備を進めましょう。
在職中にできることはたくさんあります。
- 情報収集:転職サイトやエージェントに登録し、どのような求人があるのか、自分の市場価値はどのくらいかなどをリサーチする。
- 自己分析とスキル棚卸し:これまでのキャリアを振り返り、自分の強みや弱み、得意なこと、やりたいことを明確にする。
- 貯金:退職後の生活費として、最低でも3ヶ月分、できれば半年分の生活費を準備しておくと精神的な余裕が生まれる。
- 有給休暇の確認:残っている有給休暇の日数を確認し、転職活動や心身のリフレッシュに充てられるよう計画を立てる。
準備をしっかりしておくことで、退職に対する不安を軽減し、自信を持って次のキャリアに進むことができます。
怒られてばかりで疲れた自分から卒業する

この記事では、怒られてばかりで疲れたと感じる原因から、具体的な対処法までを詳しく解説してきました。
重要なのは、自分を責めすぎず、状況を客観的に分析し、小さな一歩でも行動を起こしてみることです。
怒られやすい特徴に気づいたら、報連相を改善したり、指示の受け方を変えたりする努力が有効です。
ミスが続いても人格と切り離して考え、原因分析と対策に集中しましょう。
もしあなたがHSP気質で人一倍傷つきやすいなら、その特性を理解し、自分を守る工夫をすることが大切です。
自己肯定感の低さが悪循環を招いていると感じたら、まずは「できたこと」に目を向けて、少しずつ自信を回復させていきましょう。
そして、怒られた後も上手に気持ちを切り替え、上司との関係改善に努め、時には「気にしない」思考術を身につけることも、あなた自身を守るための強力な武器になります。
もちろん、どうしても状況が改善せず、心身の限界を感じるならば、環境を変える、つまり転職するという選択肢も常に持っておくべきです。
最終的な目標は、あなたが自分らしく、過度なストレスなく働ける環境を見つけることです。
怒られてばかりで疲れた自分から卒業するために、この記事で得たヒントを活かし、明日からの行動を少しだけ変えてみてください。
その小さな変化が、あなたの未来を大きく好転させるきっかけになるかもしれません。
- 怒られてばかりで疲れたと感じるのはあなただけではない
- 原因は報連相不足や質問の仕方にあるかもしれない
- 同じミスを繰り返さないための仕組み作りが重要
- 自信のない態度はさらなる叱責を招く可能性がある
- 仕事のミスと自分の人格は切り離して考える
- HSP気質は怒られた時のダメージを大きくする要因になりうる
- 自分の気質を理解しセルフケアすることが大切
- 自己肯定感の低さはパフォーマンス低下の悪循環を生む
- 「できたこと」に目を向け自己肯定感を育む
- 睡眠障害や意欲低下は心が限界に近いサイン
- 怒られた後は場所を移動して物理的に気分転換を図る
- 事実と感情を書き出して思考を整理する
- 上司の立場を理解しようと努めることで関係は変わる
- 「悪い報告ほど早く」を徹底し信頼を得る
- 課題の分離で理不尽な怒りから心を守る
- 今の環境がどうしても辛いなら転職も有力な選択肢






