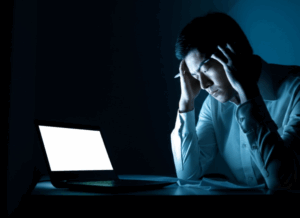あなたの周りに、話が長くてなかなか結論にたどり着かない人はいませんか。
なぜか要領を得ない話し方をする、回りくどい人とのコミュニケーションに、ストレスを感じている方も少なくないでしょう。
職場の上司や同僚がこのタイプだと、仕事の効率にも影響が出かねません。
この記事では、そんな回りくどい人の心理的な背景や特徴を深掘りし、上手な付き合い方や具体的な対処法を解説します。
多くの人が抱えるこの悩みには、はっきりとした原因と、それに対応する改善策が存在するのです。
回りくどい話し方の裏には、自信がない、相手に察してほしい、といった心理が隠れていることが多いと言われます。
私たちは、その根本的な原因を理解することで、より円滑なコミュニケーションを築くためのヒントを得られます。
本記事では、話が長い、結論を言わないといった行動の裏にある心理を解き明かし、職場でのストレスを軽減するための具体的なアプローチを提案します。
さらに、もし自分自身が回りくどい話し方をしてしまうと感じているなら、その治し方についても触れていきます。
相手への効果的な質問の仕方や、自分の要求を明確に伝えるためのコミュニケーション術を身につけ、日々のやり取りをよりスムーズなものに変えていきましょう。
この記事を読めば、回りくどい人への理解が深まり、明日からの人間関係が少し楽になるはずです。
- 回りくどい人の隠れた心理や性格的な特徴
- 結論を言わずに話を長くする人の会話パターン
- 職場やプライベートでの上手な付き合い方
- ストレスを溜めずにコミュニケーションを取る方法
- 会話の主導権を握り要点を引き出す質問術
- 自分自身の回りくどい話し方を改善する治し方
- イライラした時の感情をコントロールするコツ
なぜ?と思わせる回りくどい人の心理と話し方の特徴
- 自分に自信がなく相手の評価を気にする心理
- 結論を言わないで相手に察してほしい気持ちの表れ
- プライドが高く間違いを認めたくないという性格
- 相手より優位に立ちたい上司の隠れた意図
- とにかく話が長い人の会話パターン
自分に自信がなく相手の評価を気にする心理
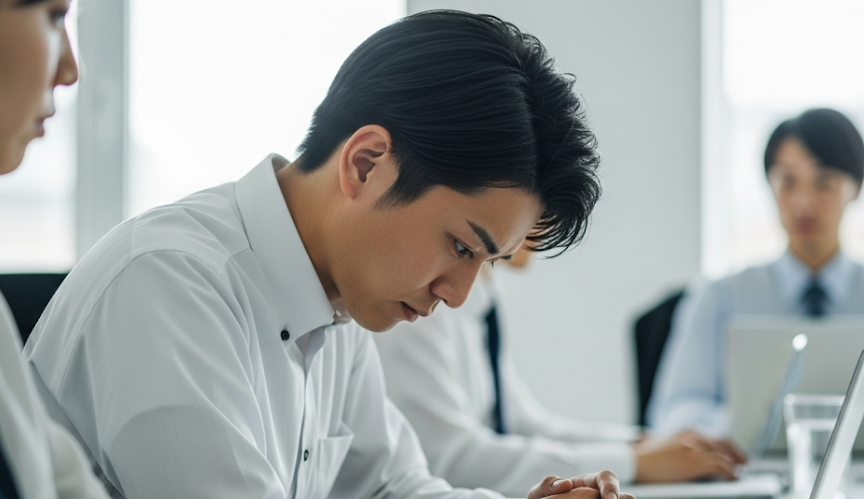
回りくどい人の行動の根底には、自分自身に対する自信の欠如が大きく影響している場合があります。
彼らは自分の意見や考えに確信が持てないため、断定的な表現を避ける傾向が強いのです。
もし間違っていたらどうしよう、相手に否定されたらどうしよう、という不安が常に心の中に渦巻いています。
この不安が、言葉を濁したり、結論を先延ばしにしたりする行動につながるわけです。
また、他者からの評価を過度に気にする心理も、回りくどい話し方の原因となります。
相手に良く思われたい、嫌われたくないという気持ちが強すぎるあまり、ストレートな物言いができなくなってしまいます。
例えば、何かを断る際に「できません」と直接的に言うと相手を傷つけてしまうかもしれない、あるいは自分の評価が下がるかもしれないと恐れます。
その結果、「その件については、少し難しい状況でして…」といった曖昧な前置きから始まり、なかなか本題に入れないのです。
このように、回りくどい表現は、彼らにとって自分を守るための鎧のような役割を果たしています。
直接的な表現で失敗するリスクを冒すよりも、遠回しな言い方で相手の反応をうかがいながら、安全な着地点を探ろうとするのです。
この心理的背景を理解すると、彼らの言動に対してただイライラするのではなく、なぜそのような話し方になるのかという視点を持つことができるようになります。
彼らは攻撃的でいるのではなく、むしろ防御的になっているのかもしれません。
この点を理解することは、彼らとのコミュニケーションを改善するための第一歩と言えるでしょう。
自信のなさは、過去の失敗体験や、常に他者と比較される環境で育ったことなどが原因となっている可能性も考えられます。
自分の発言が他者にどう受け取られるかを常にシミュレーションし、最悪の事態を避けようとするあまり、言葉数が多くなり、結果的に話が分かりにくくなってしまうのです。
結論を言わないで相手に察してほしい気持ちの表れ
回りくどい話し方をする人の中には、直接的な言葉で伝えるのではなく、相手に自分の意図を「察してほしい」と強く願っている場合があります。
これは、日本のコミュニケーション文化の一部とも言える「以心伝心」や「空気を読む」といった価値観が、個人の中で過剰に働いている状態と考えることができます。
彼らは、自分の本当の気持ちや要求をストレートに口にすることを、わがままである、あるいは配慮に欠ける行為だと感じています。
そのため、遠回しな表現や状況説明を長く続けることで、相手が自発的に自分の望みを理解し、行動してくれることを期待しているのです。
例えば、仕事で助けてほしいことがある場合、「手伝ってください」と直接頼む代わりに、「最近、このプロジェクトのタスク量が非常に多くて、少し処理に時間がかかっていまして…」といった状況説明から入ります。
これは、「この状況を理解したあなたなら、私が助けを必要としていることに気づいて、手を差し伸べてくれるはずだ」という期待の表れです。
このように相手の自発的な理解に委ねることで、万が一断られた際の心理的なダメージを軽減したいという意図も隠されています。
直接頼んで断られると、自分の要求が明確に拒絶されたことになりますが、察してもらう形式であれば、相手が気づかなかっただけ、と自分に言い訳ができるからです。
この「察してほしい」という心理は、甘えの構造とも言えます。
自分の意図を言語化して明確に伝える責任を放棄し、その解釈と対応の責任を相手に委ねてしまっている状態です。
このタイプの人は、相手が意図を汲み取ってくれないと、「なぜ分かってくれないんだ」「配慮が足りない」と、一方的に不満を抱くことも少なくありません。
彼らの話を聞く際には、ただ言葉の表面をなぞるだけでなく、その裏に隠された「本当は何を言いたいのか」「何を求めているのか」という本音を探る姿勢が求められることがあります。
しかし、それは聞き手にとって大きな負担であり、コミュニケーションの非効率性を生む大きな原因となるのです。
プライドが高く間違いを認めたくないという性格

一見すると自信がなさそうに見える回りくどい人ですが、その内面には、実は非常に高いプライドが隠されていることがあります。
このタイプの人は、「自分は常に正しく、有能である」という自己イメージを強く持っており、それを少しでも損なう可能性のある事態を極端に恐れます。
自分の発言や判断が間違っていると指摘されることは、彼らにとって耐え難い屈辱なのです。
この心理が、回りくどい話し方に直結します。
断定的な表現をすれば、後からそれが誤りであったと判明した場合、自分の非を認めなければなりません。
それを避けるために、「~という可能性も考えられます」「一概には言えませんが…」といったように、常に逃げ道を用意した言い方をします。
こうすることで、もし状況が思った通りに進まなくても、「私は断定していなかった」と言い逃れができるわけです。
彼らにとって、会話は単なる情報伝達の手段ではなく、自分のプライドを守り、知的な優位性を保つための舞台でもあります。
そのため、本題に入る前に、自分がどれだけ多くの情報を知っているか、どれだけ深く物事を考察しているかを示すために、関連情報や背景説明を延々と語ることがあります。
これは聞き手からすれば冗長でしかありませんが、本人にとっては自分の権威性を示すための重要なプロセスなのです。
また、自分の間違いを認めたくないという気持ちは、他者からの質問に対する態度にも表れます。
何か不明点を質問されると、それを自分の説明不足とは捉えず、「そんなことも分からないのか」という態度を示したり、さらに話を複雑にして煙に巻こうとしたりすることがあります。
これは、質問によって自分の完璧な論理が揺さぶられることを恐れる防衛反応と言えるでしょう。
このようなプライドの高いタイプの人と対話する際は、彼らの自尊心を不必要に傷つけないよう配慮しつつ、冷静に事実ベースで話を進める冷静さが求められます。
彼らの長い前置きや自己弁護に付き合うのではなく、「承知いたしました。それで、結論としてはどうすればよろしいでしょうか」と、敬意を払いながらも話の核心に導くアプローチが有効です。
相手より優位に立ちたい上司の隠れた意図
特に職場において、上司が回りくどい話し方をする場合、そこには単なる性格やコミュニケーションスタイルの問題だけでなく、部下との関係性における力学や隠された意図が存在することがあります。
上司という立場を利用して、意図的に分かりにくい指示を出し、部下の反応を見ることで、その能力や忠誠心を試している可能性があるのです。
このような上司は、明確で具体的な指示を与えてしまうと、仕事の責任の所在が自分にあることがはっきりしてしまいます。
もしプロジェクトが失敗した場合、その責任を負わなければなりません。
それを避けるため、あえて曖昧で回りくどい表現を使い、「私は明確な指示はしていない」「君の解釈が間違っていたのではないか」と後から言えるような余地を残しておくのです。
これは、保身と責任回避のための巧妙な戦略と言えます。
また、回りくどい話し方は、相手に対する知的優位性や権威を示すためのツールとしても機能します。
わざと専門用語を多用したり、複雑な言い回しをしたりすることで、「自分はこれだけ高度なことを考えているんだ」とアピールし、部下に対して「自分の言うことを素直に聞いていれば間違いない」という無言の圧力をかける意図があるかもしれません。
部下が「すみません、よく分からないのですが…」と質問しようものなら、「なぜ、このくらいのことが理解できないんだ」と、逆に指導不足を指摘するような態度に出ることもあります。
これにより、部下は質問しづらくなり、上司の意図を必死に推測しながら仕事を進めるしかなくなります。
このプロセスを通じて、上司は部下を精神的にコントロールし、自分の優位性を確立しようとするのです。
このような上司とのコミュニケーションでは、ただ言われたことを鵜呑みにするのではなく、必ず議事録やメールで指示内容を言語化し、「〇〇というご指示で相違ないでしょうか」と確認する作業が不可欠です。
これにより、後からの「言った、言わない」という水掛け論を防ぎ、自分の身を守ることにつながります。
上司の隠れた意図を理解し、冷静かつ戦略的に対処することが重要です。
とにかく話が長い人の会話パターン

回りくどい人の最も顕著な特徴の一つが、とにかく話が長いということです。
しかし、単に口数が多いというわけではなく、その話の構造に特有のパターンが見られます。
彼らの会話を分析すると、なぜ話が長くなり、要点が伝わりにくくなるのかが明確になります。
まず、彼らの話は時系列に沿って展開されることが多いです。
結論から話すのではなく、事の発端から現在に至るまでの出来事を、順を追ってすべて説明しようとします。
本人にとっては丁寧な説明のつもりかもしれませんが、聞き手にとっては不要な情報が多く、本当に知りたい核心部分にたどり着くまでに多大な時間を要します。
次に、本筋から脱線しやすいという特徴も挙げられます。
話の途中で思いついた別の話題や、関連性の低いエピソードを挟み込むため、話があちこちに飛んでしまいます。
例えば、「昨日の会議の件ですが」と始まった話が、いつの間にか「そういえば、会議室の空調が…」となり、最終的には「最近の電気代は本当に高いですね」といった全く別の話に着地していることも珍しくありません。
思考が整理されておらず、頭に浮かんだ順に言葉を発しているために、このような脱線が起こります。
さらに、予防線を張るための前置きや、自己弁護のための言い訳が非常に長いのも特徴です。
「あくまで私個人の意見なのですが」「これを言うと誤解を招くかもしれませんが」といったクッション言葉から始まり、なぜ自分がそう考えるに至ったかの背景説明を延々と続けます。
これは、自分の意見に対する反論をあらかじめ封じ込め、自分を守ろうとする心理の表れです。
直接的な会話と回りくどい会話の比較
| 項目 | 直接的な会話 | 回りくどい会話 |
|---|---|---|
| 結論 | 最初に提示する | 最後に、あるいは提示されない |
| 話の順序 | 結論 → 理由 → 具体例 | 経緯 → 状況説明 → 脱線 → 関連情報 |
| 情報量 | 必要最小限 | 過剰で冗長 |
| 時間 | 短い | 非常に長い |
この表からも分かるように、回りくどい人の会話は、聞き手にとって情報を整理し、要点を抽出するのが非常に困難な構造になっています。
彼らの話を聞くときは、漫然と聞くのではなく、常に「この話のゴールは何か」を意識し、不要な部分を頭の中でフィルタリングしながら聞くスキルが求められるのです。
もう疲れないための回りくどい人への具体的な対処法
- 職場でのコミュニケーションストレスを溜めない方法
- 上手な付き合い方で会話の主導権を握る
- 回りくどい話し方を改善する治し方とは
- 話の要点を引き出すための具体的な質問術
- イライラした時の気持ちの切り替え方
- 今後の関係性のための回りくどい人への理解
職場でのコミュニケーションストレスを溜めない方法

職場に回りくどい人がいると、日々の業務の中でじわじわとストレスが蓄積していきます。
会議が長引いたり、指示が不明確で手戻りが増えたりと、その影響は決して小さくありません。
こうした状況で、自分自身の心身の健康を守り、過度なストレスを溜めないためには、いくつかの具体的な対策を講じることが重要です。
まず、物理的な距離と時間をコントロールすることが有効です。
話が長くなりそうだと感じたら、「申し訳ありません、次の会議が10分後に迫っておりますので、先に結論からお伺いしてもよろしいでしょうか」といった形で、時間に制約があることを伝えます。
これにより、相手も話を簡潔にまとめようと意識する可能性が高まります。
また、口頭でのやり取りだけでなく、メールやチャットツールを積極的に活用することも一つの手です。
文字でのコミュニケーションは、要点を整理してから伝える必要があるため、自然と話が簡潔になります。
口頭で回りくどい指示を受けた後は、必ず「念のため、先ほどの件をメールで要約してお送りしますね」と伝え、自分の理解が正しいかを確認するプロセスを挟むと、認識の齟齬を防ぎ、ストレスを軽減できます。
精神的なアプローチとしては、完璧主義を捨てることも大切です。
相手の話を100%完璧に理解しようとすると、非常に疲れてしまいます。
「この話の目的は何か」「自分は何をすればいいのか」という最低限の要点さえ押さえられれば良い、と割り切ることで、精神的な負担を軽くすることができます。
相手を変えることは非常に困難ですが、自分の受け止め方や対応の仕方を変えることは可能です。
「この人はこういう話し方をする人なのだ」とある種の諦めを持って受け入れ、ゲーム感覚で「いかに早く要点を引き出すか」というミッションに挑むような気持ちで接すると、不思議とストレスが楽しみに変わる瞬間もあるかもしれません。
重要なのは、相手のペースに完全に巻き込まれるのではなく、自分の中に冷静な軸を保ち続けることです。
上手な付き合い方で会話の主導権を握る
回りくどい人との会話において、ただ受け身で話を聞いているだけでは、時間が無限に過ぎ去ってしまいます。
彼らと上手に付き合っていくためには、聞き手であるこちら側が、巧みに会話の主導権を握り、話の流れをコントロールしていく技術が必要です。
攻撃的にならず、相手に敬意を払いながら話の舵を取る方法をいくつかご紹介します。
最も効果的なテクニックの一つが、「アクティブリスニング(積極的傾聴)」と「要約」です。
相手が長々と話している途中で、適度に相槌を打ちながらも、話の節目で「なるほど、つまり〇〇ということですね?」と、こちらが理解した内容を要約して投げ返します。
この行為には二つのメリットがあります。
一つは、自分の理解が正しいかを確認できること。
もう一つは、話が脇道に逸れそうになった時に、「本題は〇〇でしたよね」と、自然な形で軌道修正を促すことができる点です。
この要約を繰り返すことで、会話は徐々に核心へと絞られていきます。
次に、会話のゴールを明確に設定し、共有することも重要です。
話が始まる前に、「本日は、Aの案件について、Bという点を決定したいと考えております。お時間は15分ほどでよろしいでしょうか」と、議題と目的、そして時間的制約を最初に提示します。
これにより、会話が漂流するのを防ぎ、参加者全員が同じゴールに向かって話を進めることができます。
さらに、未来志向の質問を投げかけることも、会話を前進させるのに役立ちます。
過去の経緯や現状説明が長々と続く場合には、「よく理解できました。ありがとうございます。それでは、今後私たちは具体的にどのようなアクションを取るべきでしょうか」と、話を未来へとシフトさせます。
「どうだったか」ではなく「どうするか」を問うことで、相手の思考を問題解決の方向へと導くのです。
- 要約して確認する: 「つまり、〇〇ということですね?」
- ゴールを共有する: 「本日の目的は△△の決定です」
- 未来志向で質問する: 「では、次に何をすべきでしょう?」
- 選択肢を提示する: 「AとB、どちらの案が良いと思われますか?」
これらのテクニックを駆使することで、あなたはただの聞き手から、会話を生産的な方向へ導くファシリテーターへと変わることができます。
回りくどい人との会話は、受け身でいるとストレスですが、主導権を握ることで、一つのスキルアップの機会と捉えることもできるのです。
回りくどい話し方を改善する治し方とは

もしかしたら、この記事を読んでいる方の中には、「自分こそが回りくどい話し方をしているかもしれない」と自覚している人もいるかもしれません。
もしそうであれば、それは改善に向けた非常に大きな一歩です。
自分のコミュニケーションスタイルに課題意識を持つことは、成長の始まりを意味します。
回りくどい話し方を改善し、より伝わるコミュニケーションを目指すための具体的な治し方について考えてみましょう。
最も基本的で強力な方法は、「PREP法」を意識することです。
PREP法とは、Point(結論)、Reason(理由)、Example(具体例)、Point(結論の再確認)の頭文字を取ったもので、この順番で話すことを心がけるだけで、驚くほど話が分かりやすくなります。
話したいことがあるとき、まず最初に「私の結論は〇〇です」と言い切る勇気を持ちましょう。
その後に「なぜなら~」と理由を述べ、必要であれば具体例を付け加えます。
この訓練を繰り返すことで、結論から話す習慣が身についていきます。
次に、話す前に頭の中で要点を3つに絞る練習をすることも効果的です。
伝えたいことがたくさんあると、どうしても話が散漫になりがちです。
会議での発言前や、誰かに何かを報告する前に、一呼吸おいて「最も重要なポイントは何か」を自問し、キーワードを3つだけ紙に書き出してみましょう。
そして、その3点に絞って話すようにするのです。
これにより、余計な情報を削ぎ落とし、簡潔で力強いメッセージを伝えることができます。
また、自分の会話を客観的に振り返る機会を持つことも重要です。
信頼できる同僚や友人に、「私の話し方で分かりにくいところはない?」とフィードバックを求めてみるのも良いでしょう。
あるいは、スマートフォンの録音機能を使って自分の発言を録音し、後で聞き返してみるのも一つの手です。
おそらく、自分が思っている以上に前置きが長かったり、話が脱線していたりすることに気づき、愕然とするかもしれません。
しかし、その気づきこそが改善の原動力となります。
回りくどい話し方は、長年の癖であり、一朝一夕で治るものではありません。
しかし、PREP法の実践、要点の整理、そして客観的な振り返りというサイクルを粘り強く続けることで、あなたのコミュニケーションは必ずより良いものへと変わっていくはずです。
話の要点を引き出すための具体的な質問術
回りくどい人との会話を効率的に進めるためには、聞き手側の質問力が決定的に重要になります。
適切な質問は、霧の中をさまようような会話に光を当て、目的地への最短ルートを照らし出す灯台のような役割を果たします。
話の要点を的確に引き出すための、具体的な質問術をマスターしましょう。
質問には大きく分けて、「オープンクエスチョン(開かれた質問)」と「クローズドクエスチョン(閉じた質問)」の2種類があります。
この2つを状況に応じて使い分けることが、質問術の基本です。
- オープンクエスチョン: 相手に自由に答えさせる質問。「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」で始まることが多い。例:「その件について、具体的にはどうお考えですか?」
- クローズドクエスチョン: 「はい」か「いいえ」、または限定された選択肢で答えさせる質問。例:「このプロジェクトは、予定通り進めてもよろしいですか?」
回りくどい人が長々と状況説明をしている段階では、まずオープンクエスチョンを使って、相手に考えを整理させるきっかけを与えます。
例えば、「色々とご説明いただきありがとうございます。その中で、最も懸念されている点は何でしょうか?」と尋ねることで、多くの情報の中から優先順位をつけさせることができます。
しかし、オープンクエスチョンだけでは、さらに話が拡散してしまうリスクもあります。
ある程度、話の方向性が見えてきたら、クローズドクエスチョンに切り替えて、話を収束させていく必要があります。
「では、結論として、A案とB案のどちらかを選ぶ、ということでよろしいですね?」といった形で、選択肢を提示し、相手に決断を促します。
この「Yes/No」で答えられる質問を繰り返すことで、曖昧だった論点が一つずつ明確になっていきます。
特に有効なのが、「確認のための質問」です。
「もし私の理解が間違っていたら訂正していただきたいのですが、〇〇という問題に対して、△△という対策を取るべき、というのがご意見でよろしいでしょうか?」
このように、こちらが受け取ったメッセージを要約し、その正否を問う質問は、相手に自分の発言を客観的に見つめ直させる効果があり、非常に強力です。
質問は、相手を問い詰めるための武器ではありません。
あくまで、お互いの理解を深め、スムーズな合意形成に至るためのツールです。
敬意と共感の姿勢を忘れずに、これらの質問術を駆使することで、あなたはどんなに回りくどい人からも、必要な情報を引き出すことができるようになるでしょう。
イライラした時の気持ちの切り替え方

回りくどい人の話に延々と付き合わされていると、どんなに温厚な人でも、さすがにイライラしてしまう瞬間があるでしょう。
「早く結論を言ってくれ!」と心の中で叫びながらも、表情には出せずにいると、そのストレスは心身に悪影響を及ぼします。
こうした状況で、自分の感情をうまくコントロールし、気持ちを切り替えるためのセルフマネジメント術を知っておくことは、非常に重要です。
まず、イライラを感じ始めたら、意識を自分の身体感覚、特に「呼吸」に向けてみましょう。
怒りや焦りを感じると、人の呼吸は無意識のうちに浅く、速くなっています。
そこで、相手の話を聞きながら、ゆっくりと鼻から息を吸い込み、口から静かに長く吐き出す「深呼吸」を試してみてください。
これを数回繰り返すだけで、高ぶった神経が落ち着き、心に少しの余裕が生まれます。
物理的に心拍数を下げることで、感情の波を鎮めることができるのです。
次に、「リフレーミング」という心理学的なテクニックも有効です。
リフレーミングとは、物事の捉え方(フレーム)を変えることで、ネガティブな感情をポジティブなものに転換する思考法です。
例えば、「この人の話は長くて非効率だ」と捉える代わりに、「この人は、物事を非常に慎重に考え、あらゆるリスクを伝えようとしてくれているのかもしれない」と、相手の行動の裏にある(かもしれない)善意に焦点を当ててみます。
あるいは、「この回りくどい会話は、私の忍耐力と傾聴スキルを鍛えるためのトレーニングだ」と、自分自身の成長の機会として捉え直すこともできます。
物事そのものに良いも悪いもなく、すべては自分の解釈次第である、という考え方です。
また、一時的にその場を離れる「タイムアウト」も簡単な方法です。
「申し訳ありません、少しお水をいただいてきてもよろしいですか」と一言断って席を立ち、数分間だけでもその場から離れます。
場所を変え、冷たい水を飲むといった行動は、気分転換に大きな効果があります。
イライラが頂点に達する前に、意識的にクールダウンの時間を作ることが、感情の爆発を防ぐ鍵となります。
これらの気持ちの切り替え方をいくつか持っておくことで、あなたは回りくどい人との対話においても、冷静でプロフェッショナルな態度を保ち続けることができるようになるでしょう。
今後の関係性のための回りくどい人への理解
これまで、回りくどい人の心理や特徴、そして具体的な対処法について詳しく見てきました。
これらのテクニックは、日々のストレスを軽減し、コミュニケーションを効率化するために非常に有効です。
しかし、最終的に私たちが目指すべきは、単にその場をうまく乗り切ることだけではなく、相手とのより良い関係性を長期的に築いていくことではないでしょうか。
そのためには、対処法の実践に加え、回りくどい人という存在そのものへの深い理解と、ある種の共感が不可欠です。
彼らの話し方は、多くの場合、意地悪や悪意から来ているのではありません。
むしろ、その根底にあるのは、自信のなさ、不安、拒絶への恐れといった、人間的な弱さであることがほとんどです。
そう考えると、彼らの冗長な話は、自分を守ろうと必死になっている心の表れと見ることもできます。
この視点を持つことで、イライラや軽蔑の感情が、少しだけ共感や理解へと変わっていくかもしれません。
もちろん、だからといって、彼らの非効率なコミュニケーションをすべて受け入れる必要はありません。
ビジネスの場では、効率と成果が求められます。
しかし、対処する際のあなたの態度が、「この人は厄介だ」という前提に立つのか、「この人は助けを必要としているのかもしれない」という前提に立つのかで、相手に与える印象は大きく変わります。
そして、その印象の違いが、今後の二人の関係性を左右するのです。
もしあなたに余裕があるのなら、彼らが安心して話せるような安全な環境を提供してあげることも、一つのアプローチです。
彼らが何か意見を言ったとき、「なるほど、面白い視点ですね」「教えてくれてありがとうございます」と、まずは肯定的に受け止める姿勢を見せることで、彼らは徐々に「ここではストレートに話しても大丈夫かもしれない」と感じるようになります。
時間はかかるかもしれませんが、こうした関わりを続けることで、彼らの回りくどさは少しずつ解消されていく可能性があります。
回りくどい人との関わりは、私たち自身のコミュニケーションスキルや人間性を試す、一つの挑戦状のようなものかもしれません。
彼らをただの問題として切り捨てるのではなく、彼らの内なる不安を理解し、敬意を持って接することで、私たちはより成熟したコミュニケーターへと成長することができるのです。
最終的には、この記事で得た知識やテクニックが、あなたの職場や人生における人間関係を、より豊かで実りあるものにするための一助となることを願っています。
- 回りくどい人は自信がなく他者の評価を気にしがち
- 結論を言わないのは相手に意図を察してほしいサイン
- プライドが高く自分の間違いを認めたくない心理が働く
- 職場の上司は優位性を示し責任を回避する意図がある
- 話が長いのは時系列で話し脱線しやすいため
- ストレスを溜めないために時間管理と文字での確認が有効
- 会話の主導権を握るには要約やゴール設定が重要
- 回りくどい話し方はPREP法の実践で改善できる
- 改善のためには自身の会話を客観的に振り返ることが必要
- 話の要点を引き出すにはオープンとクローズドの質問を使い分ける
- イライラしたら深呼吸やリフレーミングで気持ちを切り替える
- 一時的に場を離れるタイムアウトも感情のコントロールに役立つ
- 回りくどい話し方の背景には人間的な弱さがあることを理解する
- 相手を理解し敬意を持って接することが長期的な関係改善につながる
- 回りくどい人との関わりは自身のコミュニケーション能力を高める機会になる