
「またいじられてしまった…」
「どうして自分ばかりこんな思いをしなくてはいけないのだろう」
職場や友人との集まりで、いじられるのが嫌いだと感じ、一人で悩んでいませんか。
相手に悪気がないのは分かっていても、何度も続くと大きなストレスになりますよね。
この記事では、いじられるのが嫌いだと感じるあなたのための、具体的な解決策を提示します。
まず、いじられるのが嫌いだと感じる心理や、その背景にある原因を深く探っていきます。
あなたのプライドがどのように関係しているのか、また、HSPのような繊細な性格特性がどう影響するのかを理解することで、自分自身への理解が深まるでしょう。
さらに、いじってくる相手の心理や、なぜそのようなコミュニケーションを取るのかについても分析します。
その上で、職場での人間関係を悪化させずに、上手に対処法を実践する方法を具体的に解説します。
例えば、波風を立てずに相手のいじりを無視する方法や、思わずうなってしまうような、うまい言い返し方、そして今後のために明確なコミュニケーションの境界線を引くことの重要性など、すぐに使えるテクニックを紹介します。
いじりへの反応に困ったり、ストレスを溜め込んだりする必要はもうありません。
過去の経験が原因で、いじりに対して過敏になっている場合でも、適切な対処法を知ることで、心の負担は軽くなります。
信頼できる人に相談することの大切さもお伝えします。
この記事を最後まで読めば、いじられるのが嫌いな自分を責めるのではなく、自分らしく、健やかな人間関係を築くための第一歩を踏み出せるはずです。
- いじられるのが嫌いな人の心理的背景
- いじりが生まれる原因といじってくる相手の意図
- HSPなど個人の繊細な性格特性との関係
- 職場での人間関係を損なわない上手な伝え方
- ストレスを溜めないための無視や言い返す技術
- 健全なコミュニケーションのための境界線の引き方
- いじられるのが嫌いな自分と向き合い楽になる方法
◆◆いじられるのが嫌いと感じる人の心理と主な原因
- 高いプライドが傷つくことへの抵抗感
- いじってくる相手の心理とは何か
- 過去の経験がトラウマになっている可能性
- HSPなど繊細な性格特性との関連性
- 周囲の評価を過剰に気にするストレス
高いプライドが傷つくことへの抵抗感◆◆
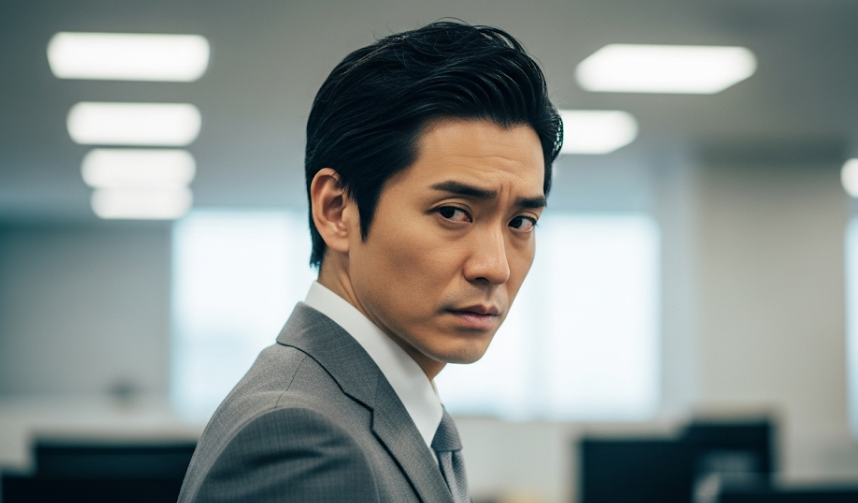
いじられるのが嫌いと感じる心理の根底には、自分自身のプライド、つまり自尊心が深く関わっていることがあります。
プライドは、自分自身を価値ある存在だと認識し、尊重する感情であり、健全な精神を保つために不可欠なものです。
しかし、このプライドが非常に高い、あるいは繊細である場合、他者からの些細な言動でさえも、自己の価値を脅かす攻撃として捉えてしまう傾向があります。
「いじり」という行為は、多くの場合、相手の欠点や特徴をユーモラスに指摘する形で行われます。
いじる側には悪意がなく、むしろ親しみの表現や、その場の空気を和ませるためのコミュニケーションの一環と考えているケースも少なくありません。
しかし、いじられる側、特にプライドが高い人にとっては、その内容がたとえ些細なことであっても、大勢の前で自分の欠点を指摘され、見下された、あるいは軽んじられたと感じてしまうのです。
この感覚は、自分の築き上げてきた自己イメージや、他者から「こう見られたい」という理想像を傷つけられることへの強い抵抗感から生まれます。
自分は有能であり、尊敬されるべき存在であるという自己認識が強いほど、それを揺るがすようないじりに対して、屈辱感や怒りといったネガティブな感情が湧き起こりやすくなります。
自尊心と「いじり」の感受性
自尊心の在り方は、いじりに対する感受性に直接的な影響を与えます。
安定した高い自尊心を持つ人は、自分の価値を確固として信じているため、他者からのいじりを冗談として受け流したり、ユーモアで返したりする心の余裕があります。
自分の価値が他者の評価によって左右されるものではないと理解しているため、いじられても深刻に捉えることが少ないのです。
一方で、プライドは高いものの、その基盤が不安定で、他者からの承認や評価に依存している場合、いじりは深刻な脅威となります。
このような人は、常に他者から良く見られようと努力しており、その努力を踏みにじられるように感じるため、強い不快感を覚えます。
「頑張っているのに、なぜこんなことを言われなければならないのか」という理不尽さや、「自分の価値が否定された」という感覚に陥りやすいのです。
したがって、いじられるのが嫌いという感情は、単なるわがままや気難しさではなく、自分という存在を守ろうとする、ごく自然な防衛反応であると理解することが重要です。
自分のプライドがどのように形成され、何によって傷つくのかを自己分析することで、いじりに対する感情のコントロールや、適切な対処法を見つける第一歩となるでしょう。
プライドを「厄介なもの」と捉えるのではなく、自分を大切にするための重要な要素として認識し、その上で健全な人間関係を築く方法を模索していくことが求められます。
いじってくる相手の心理とは何か◆◆
いじられる側が不快に感じている一方で、いじってくる相手は一体どのような心理状態でいるのでしょうか。
相手の意図を理解することは、感情的な反応を抑え、より冷静な対処法を選択するために役立ちます。
いじってくる相手の心理は、一概に「悪意がある」と断定できるものではなく、いくつかのパターンに分類できます。
1. 親しみの表現・コミュニケーションの一環
最も多いのが、いじりを「親愛の情の表れ」や「コミュニケーションを円滑にするための潤滑油」と捉えているケースです。
特に、日本の文化圏では、相手との距離を縮めるために、あえて少しけなしたり、からかったりすることが良いことだと考えている人が一定数存在します。
彼らは、あなたに対して心を開いており、「これくらいの冗談は許される関係だ」と思い込んでいるのです。
このタイプの人は、相手が傷ついているとは夢にも思っておらず、むしろ反応が良いことを「楽しんでくれている」「ノリが良い」とポジティブに誤解している可能性さえあります。
彼らに悪意はなく、むしろあなたと仲良くなりたいという善意から行動しているため、いきなり強く拒絶すると、相手を困惑させ、関係が気まずくなる恐れがあります。
2. 優位性の誇示・マウンティング
一方で、より厄介なのが、相手をいじることで自分の優位性を確認し、誇示しようとする心理が働いているケースです。
このタイプは、自分に自信がなく、他者を少し下げることで相対的に自分の立場を上げようとします。
彼らは、ターゲットにした相手が反論してこない、あるいは言い返せないことを見越して、意図的にいじりという手法を使います。
この場合のいじりは、もはやコミュニケーションではなく、言葉による巧妙なパワーハラスメント(言葉の暴力)に近いものと言えるでしょう。
彼らは、あなたが不快に感じていることに気づいている場合も多く、その反応を見て楽しんでいることさえあります。
このような相手に対しては、親しみを込めて接するのではなく、明確な境界線を示し、毅然とした態度で臨む必要があります。
3. 場を盛り上げるための役割期待
集団の中にいると、特定の個人が「いじられキャラ」として定着してしまうことがあります。
この場合、いじってくる相手は、あなた個人を攻撃したいわけではなく、その場の空気を盛り上げるため、あるいは笑いを生み出すために、あなたに「いじられ役」という役割を期待しているのです。
周りが笑っていると、いじっている側は「ウケている」と感じ、さらにいじりをエスカレートさせる傾向があります。
この状況では、いじってくる本人だけでなく、周りで笑っている人々も、間接的にいじりを助長していることになります。
このような状況から抜け出すためには、ただ一人を責めるのではなく、集団全体に対して「自分はその役割を担いたくない」という意思表示をすることが重要になります。
以下の表は、いじってくる相手の心理パターンをまとめたものです。
| 心理パターン | 相手の意図 | 対処法の方向性 |
|---|---|---|
| 親しみ・コミュニケーション型 | 仲良くなりたい、場を和ませたい(悪意なし) | 関係を壊さずに、不快であることを優しく伝える |
| 優位性誇示・マウンティング型 | 相手を下げて自分を上げたい(悪意あり) | 毅然とした態度で、明確な境界線を示す |
| 役割期待・エンタメ型 | 場を盛り上げたい、笑いが欲しい | 「いじられキャラ」を降りることを宣言する |
このように、相手の心理を分析することで、画一的な対応ではなく、状況に応じた適切な対処法が見えてきます。
いじられるのが嫌いだと感じたときは、まず一歩引いて、「相手はどのタイプだろうか?」と考えてみることが、感情的な消耗を避けるための第一歩です。
過去の経験がトラウマになっている可能性◆◆

いじられるのが嫌いという強い感情の背景には、過去の辛い経験がトラウマとして影響しているケースが少なくありません。
トラウマとは、心の傷とも言えるもので、強烈な恐怖や苦痛を伴う出来事によって、その後の感情や行動に長期的な影響を及ぼすものです。
特に、いじめや虐待、仲間外れにされた経験などは、他者からのネガティブな言動に対して極度に敏感になる原因となり得ます。
トラウマが「いじり」への過敏さを生むメカニズム
私たちの脳は、生命を脅かすような危険な出来事を経験すると、同じような状況に再び遭遇した際に、すぐに警告を発して身を守るようにプログラムされています。
これが、いわゆるフラッシュバックや過剰な警戒心といったトラウマ反応です。
過去に言葉の暴力によって深く傷ついた経験があると、現在の「いじり」が、たとえ相手に悪意のない冗談であったとしても、脳はそれを過去の危険な状況と結びつけてしまいます。
その結果、当時の恐怖や無力感、悲しみといった感情が瞬時に呼び起こされ、実際以上に強い不快感や恐怖を感じてしまうのです。
例えば、学生時代にいじめのターゲットにされ、容姿や話し方をからかわれ続けた経験のある人は、社会人になってから職場で同様のいじりを受けると、それがどんなに軽いものであっても、当時の辛い記憶が蘇り、パニックに近い状態に陥ることがあります。
周りから見れば「考えすぎ」「気にしすぎ」と映るかもしれませんが、本人にとっては、再び心が傷つけられることへの深刻な恐怖なのです。
トラウマのサインに気づく
いじられたときに、以下のような反応が自分に見られる場合、過去の経験が影響している可能性があります。
- 心臓が激しく動悸する、冷や汗が出る、体が震えるといった身体的な反応が起こる。
- 頭が真っ白になり、何を言えばいいか分からなくなる。
- その場で凍りついたように動けなくなる。
- 後になってから、何度もその場面を思い出して落ち込み、眠れなくなる。
- いじってきた相手に対して、過剰な怒りや憎しみを感じる。
これらの反応は、単なる「嫌い」という感情だけでなく、心と体が危険信号を発しているサインです。
もし、自分がいじりに対して過剰に反応してしまっていると感じ、それが日常生活に支障をきたしているのであれば、それはあなたの心が弱いからではありません。
それは、過去にあなたが大変な経験を乗り越えてきた証拠であり、今もなお、その傷が癒えていないというSOSなのです。
このような場合、一人で抱え込むのは非常に困難です。
過去の経験が現在の感情に影響している可能性を認識し、必要であれば専門家(カウンセラーや心療内科医)に相談することも重要な選択肢の一つです。
専門家の助けを借りて、過去の出来事と現在の感情を整理することで、トラウマの呪縛から解放され、いじりに対してより冷静に対処できるようになる道が開けるかもしれません。
HSPなど繊細な性格特性との関連性◆◆
いじられるのが嫌いという感情は、個人の性格特性、特に「HSP(Highly Sensitive Person)」と呼ばれる非常に繊細な気質と深く関連していることがあります。
HSPは、病気や障害ではなく、生まれ持った気質の一つであり、全人口の約15〜20%、つまり5人に1人程度はHSPであると言われています。
HSPの人は、そうでない人と比べて、あらゆる刺激に対して脳が深く情報を処理するため、感受性が非常に豊かであるという特徴があります。
HSPの主な特徴
HSPの提唱者であるエレイン・アーロン博士によると、HSPには「DOES(ダズ)」と呼ばれる4つの特徴があります。
- D (Depth of processing): 物事を深く処理する。一つの事柄について、深く考えを巡らせる傾向がある。
- O (Overstimulation): 刺激に過剰に反応しやすい。大きな音、強い光、人混み、他人の感情など、外部からの刺激に疲れやすい。
- E (Emotional reactivity and high Empathy): 感情の反応が強く、共感力が高い。他人の喜びや悲しみを、まるで自分のことのように感じてしまう。
- S (Sensitivity to Subtleties): ささいな刺激を察知する。場の雰囲気の変化や、相手の表情、声のトーンといった些細な違いによく気づく。
これらの特徴を持つHSPの人にとって、「いじり」は非常に負担の大きいコミュニケーションとなり得ます。
なぜHSPはいじりが苦手なのか
HSPの人がいじりを特に不快に感じる理由は、その特性に起因しています。
まず、ささいな刺激を察知する(S)ため、相手の言葉の裏にある、ほんの少しの悪意や軽蔑のニュアンスを敏感に感じ取ってしまいます。
相手が「冗談のつもり」で言った言葉でも、HSPの人はその言葉の響きや、その場の微妙な空気感から、自分が軽んじられていると感じ、深く傷ついてしまうのです。
また、物事を深く処理する(D)傾向があるため、いじられた後も、その言葉を何度も頭の中で反芻し、「なぜあんなことを言われたんだろう」「私が何か悪いことをしただろうか」と延々と考え続けてしまいます。
一度気になると、なかなか頭から離れず、精神的なエネルギーを大きく消耗してしまうのです。
さらに、感情の反応が強く、共感力が高い(E)ため、いじられて周りが笑っていると、その「笑われている」という状況に強い羞恥心や屈辱感を覚えます。
同時に、周りの人々の感情にも敏感なため、その場を取り繕うために無理に笑顔を作ったり、平気なふりをしたりして、心の中とは裏腹の行動を取ることで、さらに疲弊してしまいます。
そして、これらの刺激が積み重なることで、過剰な刺激を受けやすい(O)HSPの脳はキャパシティオーバーに陥り、強いストレスを感じる結果となるのです。
もし、あなたが「自分は他の人よりも傷つきやすいかもしれない」「些細なことがずっと気になってしまう」と感じるのであれば、HSPの気質を持っている可能性があります。
自分がHSPであると知ることは、いじられるのが嫌いなのは自分の心が弱いからではなく、生まれ持った特性なのだと理解し、自分を責めるのをやめるきっかけになります。
そして、繊細な自分を守るために、人との距離の取り方や、刺激の少ない環境を選ぶといった、自分に合った対処法を見つけていくことが大切になります。
周囲の評価を過剰に気にするストレス◆◆
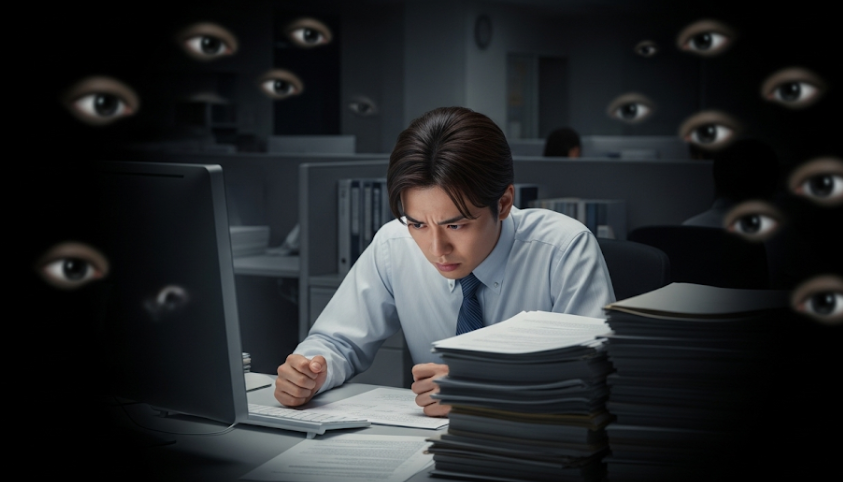
いじられるのが嫌いだと感じる大きな要因の一つに、「周囲からの評価を過剰に気にしてしまう」という心理的な傾向が挙げられます。
私たちは社会的な生き物であるため、他者からどう見られているかを気にするのは自然なことです。
しかし、その気持ちが度を越してしまうと、他人の些細な言動に一喜一憂し、常にストレスを抱えることになってしまいます。
承認欲求と自己肯定感の低さ
周囲の評価を過剰に気にする心理の根底には、強い「承認欲求」と、それに反比例する「自己肯定感の低さ」が隠れていることが多いです。
承認欲求とは、「他者から認められたい」「価値ある存在だと思われたい」という欲求のことです。
この欲求自体は誰もが持っているものですが、自己肯定感が低い人は、自分自身で自分の価値を認めることが難しいため、他者からの承認や評価によってしか、自分の価値を実感することができません。
つまり、「他人の評価=自分の価値」という図式が、心の中に出来上がってしまっているのです。
このような状態にある人にとって、「いじり」は自己価値を根底から揺るがす深刻な出来事となり得ます。
いじられることで、「自分はダメな人間だと思われているのではないか」「周りからバカにされているのではないか」という不安に駆られます。
たとえそれが冗談であったとしても、承認を得たい相手からネガティブな評価(と本人が受け取る言動)をされることは、耐えがたい苦痛なのです。
その結果、いじられた内容そのものよりも、「これを言われたことで、周りは自分のことをどう思っただろうか」という、周囲の視線に対する恐怖やストレスが大きくなっていきます。
失敗への恐怖と完璧主義
また、周囲の評価を気にする人は、失敗することに対して極度の恐怖心を抱いている傾向があります。
「常に完璧でなければならない」「人前で弱みを見せてはいけない」という完璧主義的な思考に陥りがちで、いじりで指摘されるような自分の欠点や失敗を、決して他人に知られたくないと思っています。
いじりは、まさにその隠しておきたい部分を、大勢の前で暴き出す行為に他なりません。
そのため、いじられると、自分の完璧なイメージが崩れ、評価が下がってしまうという強い危機感を覚えるのです。
このタイプの人は、いじりに対してうまく切り返すといった気の利いた反応ができません。
なぜなら、面白い反応をしようとして「スベる」こと、つまり失敗することもまた、評価を下げるリスクだと考えてしまうからです。
結果として、愛想笑いを浮かべてやり過ごすか、あるいは固まってしまうしかなく、その無抵抗な態度が、さらなるいじりを誘発するという悪循環に陥ってしまいます。
もし、あなたが「人からどう思われるかがいつも気になる」「失敗するのが怖い」と感じるのであれば、まずはその完璧主義を少しだけ緩めてみることが大切です。
「人は誰でも欠点を持っているし、失敗もする」「自分の価値は、他人の評価だけで決まるものではない」ということを、少しずつ自分に言い聞かせていくこと。
それが、いじりという名の評価の嵐から、自分自身を守るための心の傘を育てる第一歩となるでしょう。
◆◆いじられるのが嫌いな人が実践できる具体的な対処法
- 職場での人間関係を壊さない伝え方
- 波風を立てずに上手く無視する方法
- 反応に困った時のうまい言い返し方
- コミュニケーションの境界線を引く重要性
- 相談できる信頼できる人を見つける
- いじられるのが嫌いな自分を受け入れストレスを軽減する
職場での人間関係を壊さない伝え方◆◆

いじられるのが嫌いだと感じていても、特に職場の人間関係においては、「嫌だ」と伝えることで関係がギクシャクしてしまうのではないか、という不安から、我慢してしまう人が少なくありません。
しかし、我慢を続けていては、ストレスが溜まる一方です。
大切なのは、相手を攻撃するのではなく、自分の気持ちを誠実に、かつ上手に伝えるコミュニケーションスキルです。
そのための有効な手法として、「アサーティブコミュニケーション」があります。
アサーティブコミュニケーションとは
アサーティブコミュニケーションとは、相手の意見や気持ちを尊重しつつも、自分の意見や感情を正直に、率直に、その場に合った適切な方法で表現するコミュニケーションのことです。
これには、主に3つのタイプがあります。
- アグレッシブ(攻撃的): 自分の意見ばかり主張し、相手を言い負かそうとする。「なんでそんなこと言うんですか!失礼ですよ!」
- ノンアサーティブ(非主張的): 自分の気持ちを抑え、相手に合わせてしまう。愛想笑いや黙って我慢する。
- アサーティブ(誠実・対等): 相手を尊重しつつ、自分の気持ちを伝える。「そう言われると、私は少し悲しい気持ちになります。」
目指すべきは、3つ目のアサーティブな伝え方です。
「I(アイ)メッセージ」で伝える
アサーティブな伝え方の核となるのが、「I(アイ)メッセージ」です。
これは、「You(あなた)」を主語にして相手を責める(例:「あなたはいつもひどい」)のではなく、「I(私)」を主語にして、自分の気持ちや状況を伝える方法です。
「Youメッセージ」が相手への非難に聞こえやすいのに対し、「Iメッセージ」は、あくまで自分の主観的な気持ちを述べているだけなので、相手も受け入れやすくなります。
具体的には、以下の3つの要素を組み合わせて伝えます。
- 客観的な事実: 相手のどのような言動に対してか。「(例)先ほど、みんなの前で私の服装について冗談を言われた時ですが」
- 自分の気持ち: その言動によって、自分がどう感じたか。「(例)私は、少し恥ずかしい気持ちになりました」
- お願い・提案: 今後どうしてほしいか。「(例)申し訳ないのですが、今後はそういった冗談は控えていただけると、とても助かります」
これを繋げると、「先ほど、みんなの前で私の服装について冗談を言われた時ですが、私は少し恥ずかしい気持ちになりました。申し訳ないのですが、今後はそういった冗談は控えていただけると、とても助かります」となります。
ポイントは、感情的にならず、あくまで冷静に、落ち着いたトーンで伝えることです。
また、伝えるタイミングも重要です。相手が忙しい時や、周りに大勢の人がいる時を避け、二人きりで話せる落ち着いた状況を選びましょう。
このように伝えることで、相手は「自分の言動が、この人を傷つけていたのか」と気づくきっかけを得られます。
特に悪意のない相手であれば、「ごめん、気づかなかった」と素直に受け入れてくれる可能性が高いでしょう。
人間関係を壊すことを恐れて何もしなければ、状況は変わりません。
勇気を出して、自分の気持ちを誠実に伝えることが、健全な職場環境を築くための第一歩なのです。
波風を立てずに上手く無視する方法◆◆
「嫌だ」と直接伝える勇気がない場合や、伝えても改善されない相手に対しては、「無視する」というのも有効な対処法の一つです。
しかし、あからさまに相手を無視すると、それはそれで新たな対立を生み、人間関係を悪化させる原因になりかねません。
ここでの「無視」とは、相手の存在を完全に無視するのではなく、「いじり」という行為そのものをスルーし、相手に「いじっても面白くない」と思わせる高等技術を指します。
1. 反応を極端に薄くする
いじってくる相手は、あなたの反応を見て楽しんでいます。
あなたが困ったり、慌てたり、あるいは無理に笑ったりする反応は、彼らにとって「ご褒美」のようなものです。
したがって、そのご褒美を与えなければ良いのです。
いじられた瞬間に、表情を一切変えず、真顔で「はあ」「そうですか」とだけ、低いトーンで返します。
そして、すぐに別の話題に移るか、自分の作業に戻ります。
笑顔を見せたり、何か気の利いたことを言おうとしたりする必要は一切ありません。
この「無反応」を徹底することで、相手は「あれ?ウケないな」「ノリが悪いな」と感じ、手応えのなさに、やがてあなたをいじることをやめていくでしょう。
これは、相手の期待を裏切る、非常に効果的な方法です。
2. 物理的に距離を取る
いじってくる相手が特定されているのであれば、その人と物理的に距離を取ることも有効です。
例えば、休憩時間はその人がいない場所で過ごす、飲み会では遠い席に座る、業務上の関わりがないのであれば、なるべく近づかない、といった行動です。
これは、いじられる機会そのものを減らすための、シンプルかつ効果的な防衛策です。
もし、席が隣であるなど、どうしても物理的に離れられない場合は、常にイヤホンをして音楽を聴いている(ふりをする)、あるいは常に忙しそうにパソコンに向かっている、といった「話しかけづらいオーラ」を出すことも一つの手です。
3. 話題をすり替える
いじられた直後に、全く関係のない、業務上の質問や相談を持ちかけるという方法もあります。
例えば、「その髪型、寝ぐせ?」といじられた瞬間に、「ああ、それより〇〇さん、例の件のデータなんですけど、確認していただけましたか?」と、真面目な顔で切り返します。
相手は、いじりの流れを断ち切られ、仕事のモードに引き戻されるため、それ以上ふざけてくることが難しくなります。
この方法は、相手に主導権を渡さず、会話の流れをこちらがコントロールするという意思表示にもなります。
これらの「上手な無視」は、相手を直接的に攻撃するものではないため、比較的波風を立てずに行うことができます。
大切なのは、「私はあなたのその土俵には乗りません」という冷静で毅然とした態度を、非言語的に示し続けることです。
一貫してこの態度を取り続けることで、相手はあなたを「いじっても面白くない、面倒な相手」と認識し、次第にターゲットから外していく可能性が高いのです。
反応に困った時のうまい言い返し方◆◆

いじられた時、ただ黙って耐えたり、無視したりするだけでなく、時には切り返すことで状況を好転させたい、と考える人もいるでしょう。
しかし、感情的に言い返しては、ただの口喧嘩になってしまいます。
ここでの「うまい言い返し方」とは、相手の攻撃力を削ぎ、かつ自分の品位を落とさない、ユーモアや冷静さを伴った高等なコミュニケーション技術です。
いくつかのパターンを知っておくことで、いざという時に役立つかもしれません。
1. 「オウム返し」で質問する
相手に言われたことを、そのまま疑問形で返す方法です。
例えば、「本当に仕事できないよねー」と言われたら、怒るのではなく、不思議そうな顔で「私が、仕事できない…ですか?」と問い返します。
ポイントは、「〜ですか?」と、あくまで質問の形にすることです。
こうすると、ボールは相手に返ります。
相手は、自分の発言の根拠を説明する責任が生じます。
多くの場合、いじってくる人は深い考えなく発言しているので、具体的な根拠などありません。
そのため、「いや、そういうわけじゃないけど…」などと、しどろもどろになることが多いのです。
これにより、相手の発言がいかに無責任で、根拠のないものであるかを、周囲に示すことができます。
2. ポジティブに変換して受け流す
相手のネガティブな指摘を、あえてポジティブな言葉に変換して返す、ユーモアのある返し方です。
例えば、「頑固で融通が利かないよね」と言われたら、「ありがとうございます!『意志が強い』ってことですよね!」と笑顔で返します。
「心配性すぎるよ」と言われれば、「はい、『危機管理能力が高い』とよく言われます!」と切り返します。
この返し方の良いところは、相手の悪意(あるいは無神経さ)を無力化し、自分の自己肯定感を下げずに済む点です。
相手は「そういうつもりで言ったんじゃないのに…」と拍子抜けし、あなたが自分の欠点を強みとして認識している、精神的に強い人間であるという印象を与えることができます。
3. 感謝を述べて話を終わらせる
相手のいじりに対して、「アドバイス」として受け取った体で、丁寧にお礼を言って話を強制終了させる方法です。
例えば、「〇〇さんのそういうところが、ちょっとね…」などと抽象的なダメ出しをされたら、真面目な顔で「なるほど、貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます」と、深くお辞儀をします。
この対応をされると、相手はそれ以上何も言えなくなります。
皮肉とユーモアが絶妙に混じったこの返し方は、相手に「この人は一枚上手だ」と思わせ、今後のいじりを抑制する効果が期待できます。
4. 真顔で事実を確認する
「それ、本気で言ってます?」「それって、セクハラ(パワハラ)になるってご存知ですか?」と、真顔で冷静に問いかける方法です。
これは、相手の言動が社会的に許容されないものであることを、明確に指摘する、かなり強めの返し方です。
相手がマウンティング目的で、悪意を持って繰り返しいじってくるような場合に特に有効です。
この一言で、相手は自分の言動のリスクを自覚し、青ざめるかもしれません。
ただし、関係性が悪化するリスクも伴うため、使う相手や状況は慎重に選ぶ必要があります。
これらの言い返し方は、あくまで「武器」の一つです。
常に使う必要はなく、自分の心を守るための「お守り」として、引き出しに持っておくと良いでしょう。
そして、どの方法を使うにしても、決して感情的にならず、冷静に、できれば少しのユーモアを添えて行うことが、うまく切り返すための最大のコツです。
コミュニケーションの境界線を引く重要性◆◆
いじられるのが嫌いな人が、長期的に自分を守り、健全な人間関係を築いていく上で、最も重要と言っても過言ではないのが、「コミュニケーションの境界線(バウンダリー)を引く」という概念です。
境界線とは、自分と他者とを区別する、目には見えない心理的な線のことです。
「どこまでが自分で、どこからが相手か」「何を受け入れ、何を受け入れないか」を明確にすることで、他者からの不適切な侵入を防ぎ、自分の心と時間の主導権を握ることができます。
境界線が曖昧だとどうなるか
境界線が曖昧な人は、他者の感情や問題まで、自分のものとして背負い込んでしまう傾向があります。
- 相手の機嫌を損ねることを恐れて、嫌なことでも「ノー」と言えない。
- 相手の問題なのに、自分が何とかしてあげなければならないと感じてしまう。
- 自分の感情よりも、相手の感情を優先してしまう。
- 自分のプライベートな領域に、土足で踏み込まれても何も言えない。
このような状態では、いじってくる相手に対して、明確な拒否の態度を示すことができません。
相手は「この人はどこまでやっても大丈夫だ」と学習し、いじりはどんどんエスカレートしていく可能性があります。
つまり、あなたが境界線を引かないことが、相手の不適切な行動を許可してしまっている、という側面もあるのです。
自分だけの「ルールブック」を作る
境界線を引くための第一歩は、自分自身が「何を許容でき、何を許容できないか」を明確に自覚することです。
まずは、自分だけの「コミュニケーション・ルールブック」を心の中で作ってみましょう。
【許容できること(OKゾーン)】
- 仕事のパフォーマンスに関する、建設的なフィードバック。
- たまに、親しみを込めてニックネームで呼ばれること。
【あまり好ましくないが、状況によっては許容できること(グレーゾーン)】
- 仕事のミスを、ユーモアを交えて軽く指摘されること。(ただし、頻繁でなく、一対一の場面に限る)
【絶対に許容できないこと(NGゾーン)】
- 容姿や家族、プライベートな事柄について、大勢の前で言及されること。
- 人格を否定するような言葉。
- 「冗談だよ」で済まされる、身体的な接触。
このように、自分の中での基準を明確にすることで、いじられた時に、それが自分のNGゾーンに踏み込んでいるかどうかを即座に判断できます。
そして、NGゾーンに踏み込まれた際には、「それは私にとっては受け入れられません」と、毅然とした態度で伝える根拠が生まれます。
境界線を相手に伝える
ルールブックができたら、次はそれを相手に知らせる番です。
もちろん、ルールブックを印刷して渡すわけではありません。
日々の言動を通じて、少しずつ「私の境界線はここです」と示していくのです。
例えば、NGゾーンであるプライベートな質問をされたら、「ごめんなさい、その質問にお答えすることはできません」と、笑顔で、しかしはっきりと断ります。
一度で伝わらなければ、何度でも同じ対応を繰り返します。
大切なのは、一貫性です。
気分によって境界線が動いてしまうと、相手は混乱し、あなたの真意を理解できません。
境界線を引くことは、相手を拒絶する冷たい行為ではありません。
むしろ、「このルールを守ってくれるなら、私はあなたと良好な関係を築きたいです」という、健全な関係性への招待状なのです。
最初は勇気がいるかもしれませんが、自分の心を守るために、少しずつ実践していくことが大切です。
相談できる信頼できる人を見つける◆◆

いじられるのが嫌いだという悩みは、非常に個人的で、デリケートな問題です。
「こんなことで悩んでいるなんて、自分が弱いだけではないか」「他人に話しても理解してもらえないだろう」と考え、一人で抱え込んでしまう人が少なくありません。
しかし、一人で悩み続けることは、精神的な孤立を深め、ストレスを増大させるだけです。
この状況を乗り越えるために、信頼できる人に相談するという行為は、非常に重要で、力強い支えとなります。
誰に相談すれば良いか
相談相手は、誰でも良いというわけではありません。
相手を間違えると、かえって傷ついたり、状況が悪化したりすることもあります。
信頼できる相談相手の条件としては、以下の点が挙げられます。
- 秘密を守れる人: あなたの話を、許可なく他人に漏らさない口の堅い人。
- 傾聴力のある人: あなたの話を途中で遮ったり、否定したりせず、まずは最後まで真摯に聞いてくれる人。
- 客観的な視点を持てる人: あなたの感情に寄り添いつつも、冷静に状況を分析できる人。
- あなたの味方でいてくれる人: たとえ正論ではなくても、まずは「辛かったね」とあなたの気持ちを受け止めてくれる人。
具体的な相談相手としては、以下のような存在が考えられます。
- 職場の信頼できる上司や先輩: 職場の人間関係が原因である場合、状況を理解しており、具体的な解決策(配置転換など)を講じてくれる可能性があります。ただし、相談相手が、いじってくる本人と親しい場合は避けた方が賢明です。
- 社内の人事部やコンプライアンス部門: いじりが度を超え、パワハラやセクハラに該当すると感じる場合は、会社の公式な窓口に相談することが有効です。匿名での相談が可能な場合もあります。
- 家族や親しい友人: あなたのことを深く理解し、無条件で味方になってくれる存在です。話を聞いてもらうだけでも、心の負担は大きく軽減されます。
- 専門家(カウンセラー、心療内科医): 客観的で専門的な知識を持つ第三者です。過去のトラウマが関係している場合や、心身に不調(不眠、食欲不振など)が出ている場合は、迷わず専門家を頼りましょう。
相談することのメリット
相談することには、多くのメリットがあります。
まず、自分の感情や状況を言葉にして話すことで、頭の中が整理され、客観的に問題を見つめ直すことができます。
これを「外在化」と呼び、一人で悶々と考えている時には気づかなかった解決の糸口が見つかることがあります。
また、信頼できる人に「辛かったね」「あなたは悪くないよ」と言ってもらうことで、孤独感が和らぎ、自分だけが悩んでいるわけではない、と安心感を得ることができます。
この「自分は一人ではない」という感覚は、困難に立ち向かうための大きなエネルギーになります。
さらに、自分一人では思いつかなかったような、新しい視点や対処法のアドバイスをもらえる可能性もあります。
相談することは、決して弱い人間のすることではありません。
むしろ、自分の問題を解決するために、他者の力を借りるという、賢明で積極的な行動です。
あなたの周りには、あなたが思っている以上に、あなたの力になりたいと思っている人がいるかもしれません。
勇気を出して、その扉をノックしてみてください。
いじられるのが嫌いな自分を受け入れストレスを軽減する◆◆
これまで、いじられるのが嫌いだと感じる原因や、具体的な対処法について見てきました。
しかし、最も根本的な解決策は、「いじられるのが嫌いな自分」を否定せず、そのまま受け入れることから始まります。
多くの人は、「いじられるくらいで悩むなんて、器が小さいのではないか」「もっとユーモアのセンスがあれば…」と、自分自身を責めてしまいがちです。
しかし、その自己否定こそが、最もあなたを苦しめているストレスの原因なのです。
「嫌い」という感情は、あなたを守るアラーム
いじられて「嫌だ」「不快だ」と感じる感情は、決してネガティブなものではありません。
それは、あなたの心と尊厳が、外部からの攻撃によって傷つけられていることを知らせる、大切な「アラーム機能」なのです。
熱いヤカンに触れた時に「熱い!」と感じて手を引っ込めるのと同じように、心が傷つけられた時に「嫌だ!」と感じるのは、自分を守るためのごく自然で、健康的な反応です。
もし、このアラームが鳴らなかったら、あなたは自分の心が傷ついていることに気づかず、他者からの不適切な侵入を許し続け、やがては心が壊れてしまうでしょう。
だから、「いじられるのが嫌い」という自分の感受性を、恥じたり、変えようとしたりする必要はありません。
むしろ、「私の心を守ってくれて、ありがとう」と、その感情に感謝すべきなのです。
自己肯定感を育む
いじられるのが嫌いな自分を受け入れるためには、他者からの評価に左右されない、安定した「自己肯定感」を育むことが不可欠です。
自己肯定感とは、「ありのままの自分を、良い点も悪い点も含めて肯定し、価値ある存在だと認める感覚」のことです。
自己肯定感が高い人は、他者からいじられても、それを自分の価値全体を否定するものとは捉えません。
「確かに私にはそういう一面もあるかもしれない。でも、それも私の一部だ。私の価値はそれだけでは決まらない」と、どっしりと構えていることができます。
自己肯定感を高めるためには、以下のようなことを日々の生活で意識してみると良いでしょう。
- 小さな成功体験を積み重ねる: 「今日は朝、決めた時間に起きられた」「難しい仕事を一つやり遂げた」など、どんなに小さなことでも良いので、できた自分を褒めてあげる。
- 自分の長所を書き出す: 短所ばかりに目を向けるのではなく、自分の良いところ、得意なことを紙に書き出してみる。
- ポジティブな言葉を使う: 「どうせ私なんて」という口癖を、「私ならできるかもしれない」に変えてみる。
- 自分を大切に扱う: 栄養のある食事をとる、十分な睡眠時間を確保するなど、自分の心と体を労わる時間を作る。
いじられるのが嫌いなのは、あなたの個性であり、感受性が豊かである証です。
その個性を無理に変えようとせず、自分に合った対処法を学び、自分を守る術を身につけていくこと。
そして何より、「こんな自分でも良いんだ」と、ありのままの自分を抱きしめてあげること。
それができた時、あなたは他人の言動に振り回されることなく、穏やかで、自分らしい人生を歩んでいくことができるようになるでしょう。
- いじられるのが嫌いなのは自然な感情
- 原因はプライドや過去のトラウマなど様々
- HSPなど繊細な気質も関係している
- いじる側の心理は必ずしも悪意とは限らない
- 相手の心理を見極めて対処法を変えることが重要
- 対処法①:Iメッセージで不快な気持ちを伝える
- 対処法②:反応を薄くして上手く無視する
- 対処法③:ユーモアや冷静さでうまく言い返す
- 対処法④:コミュニケーションの境界線を明確に引く
- 対処法⑤:一人で抱え込まず信頼できる人に相談する
- いじられても自分の価値は変わらない
* 周囲の評価を気にしすぎないことが大切 * 自己肯定感を育むことでストレスは軽減される * 「嫌い」という感情は自分を守るためのアラーム機能 * いじられるのが嫌いな自分自身を責めずに受け入れる






