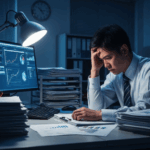「あの人、また休んでいる…」
あなたの職場にも、頻繁に仕事を休む同僚や部下はいませんか。
心配する気持ちと共に、業務のしわ寄せに対する複雑な感情を抱くこともあるかもしれません。
しかし、その背景には、単なる「甘え」や「やる気のなさ」では片付けられない、深刻な問題が隠されていることが多いのです。
仕事をよく休む人の心理を理解することは、本人だけでなく、職場全体の健全な環境を築く上で非常に重要になります。
過度なストレスや複雑な人間関係、あるいはメンタルヘルスの不調など、目には見えないさまざまな要因が絡み合っている可能性があります。
この記事では、仕事をよく休む人の心理に焦点を当て、その背後にある原因や特徴を深く探求します。
そして、上司や同僚としてどのように関わっていけば良いのか、具体的な対処法や、誰もが働きやすい職場環境を整えるためのヒントを提供します。
この問題について理解を深めることは、不要な対立を避け、チームとして支え合う文化を育む第一歩となるでしょう。
- 仕事をよく休む人の心理的背景にある5つの原因
- 休みがちな人に見られる共通の特徴とサイン
- ストレスや人間関係が心身に与える深刻な影響
- メンタルヘルスの不調を見極めるための視点
- 上司や同僚ができる具体的な対処法とサポート
- 休むことへの罪悪感を和らげるための考え方
- 誰もが働きやすい職場環境を構築する重要性
目次
仕事をよく休む人の心理に隠された5つの背景
- 休みがちな人の意外な特徴とは
- 過度なストレスが心身に与える影響
- 複雑な人間関係が引き起こす出勤への抵抗感
- メンタルヘルスの不調を示す重要なサイン
- 休みがちなのは「甘え」なのかという問題
休みがちな人の意外な特徴とは

仕事を頻繁に休む人に対して、私たちは「不真面目」「自己中心的」といったネガティブなイメージを抱きがちです。
しかし、その行動の裏には、意外な特徴や共通点が隠されていることがあります。
仕事をよく休む人の心理を理解するためには、表面的な行動だけでなく、その人の内面的な特性にも目を向ける必要があります。
一つの特徴として、責任感が強く、完璧主義である点が挙げられます。
意外に聞こえるかもしれませんが、常に高いパフォーマンスを自身に課し、少しでも期待に応えられないと感じると、大きなプレッシャーとストレスを抱え込んでしまうのです。
自分の仕事ぶりに満足できず、周囲の期待に応えられていないという思い込みから、出勤すること自体が苦痛になり、結果として休みを選択してしまうケースは少なくありません。
また、他人の評価に非常に敏感で、繊細な気質を持つ人(HSPなど)も、休みがちになる傾向が見られます。
職場での些細な言葉や態度の変化を敏感に察知し、深く傷ついたり、過剰に思い悩んだりします。
このような人々にとって、職場は常に緊張を強いられる場所であり、心身のエネルギーを消耗しやすいため、休息を必要とすることが多くなるのです。
さらに、プライベートと仕事の境界線を引くのが苦手な人も、休みが増えることがあります。
家庭の問題や個人的な悩みを職場に持ち込んでしまい、仕事に集中できなくなるのです。
逆もまた然りで、仕事のストレスを家庭に持ち帰り、プライベートな時間も心から休むことができず、疲労が蓄積していくという悪循環に陥ります。
これらの特徴は、決して「怠けている」わけではなく、むしろ真面目で誠実な人柄の裏返しであることが多いのです。
彼らが抱える内面的な葛藤や困難を理解することが、問題解決への第一歩と言えるでしょう。
過度なストレスが心身に与える影響
現代社会において、仕事上のストレスは誰にでも起こりうる問題ですが、それが過度になると心身に深刻な影響を及ぼし、仕事を休む直接的な原因となります。
仕事をよく休む人の心理を考える上で、ストレスがもたらす影響を理解することは不可欠です。
まず精神的な影響として、意欲の低下、集中力の散漫、不安感、抑うつ気分などが挙げられます。
これまでは楽しめていた仕事に興味が持てなくなったり、簡単なミスを繰り返すようになったりするのは、ストレスによって脳の機能が低下しているサインかもしれません。
特に、「燃え尽き症候群(バーンアウト)」と呼ばれる状態に陥ると、極度の情緒的疲弊感から、仕事への情熱を完全に失い、出勤する気力さえ湧かなくなってしまいます。
次に、身体的な影響も無視できません。
ストレスは自律神経のバランスを乱し、さまざまな身体症状を引き起こします。
- 頭痛やめまい
- 肩こりや腰痛
- 胃痛や吐き気などの消化器症状
- 動悸や息切れ
- 不眠や過眠といった睡眠障害
これらの症状は、病院で検査をしても異常が見つからないことも多く、「気のせい」や「怠け」と誤解されがちです。
しかし、これらは紛れもなくストレスが原因で起きている身体からのSOSサインなのです。
本人は出勤したくても、こうした身体症状のためにやむを得ず休まざるを得ない状況に追い込まれている可能性があります。
さらに、ストレスは免疫機能の低下も招きます。
その結果、風邪をひきやすくなったり、感染症にかかりやすくなったりと、実際に体調を崩す頻度が高くなります。
このように、過度なストレスは精神面、身体面の両方から個人を蝕み、安定して働き続けることを困難にします。
仕事を休むという行動は、これ以上心身が壊れてしまわないための、無意識の防衛反応であるとも捉えることができるでしょう。
複雑な人間関係が引き起こす出勤への抵抗感

多くの人にとって、職場の人間関係は仕事のモチベーションを左右する重要な要素です。
この人間関係が複雑化し、ストレスの原因となると、出勤すること自体に強い抵抗感を感じるようになり、結果として欠勤が増える一因となります。
仕事をよく休む人の心理を探る上で、人間関係の問題は避けて通れません。
具体的にどのような人間関係が問題となるのでしょうか。
威圧的な上司や同僚の存在
高圧的な態度、理不尽な要求、人格を否定するような言動は、部下や同僚に深刻な精神的ダメージを与えます。
毎日顔を合わせなければならない相手から攻撃を受け続けると、職場は安心できる場所ではなく、危険な場所へと変わってしまいます。
出勤前になると動悸がしたり、腹痛が起きたりといった身体症状が現れることもあり、職場から逃避するために休みを選択するのは、自己防衛として自然な反応と言えるかもしれません。
孤立感や疎外感
職場で誰ともコミュニケーションが取れず、孤立している状態も大きなストレスです。
業務上の連携がうまくいかないだけでなく、「自分はここにいてはいけない存在なのではないか」という疎外感を抱き、自己肯定感が低下します。
特に、無視されたり、意図的に情報共有の輪から外されたりするような、陰湿ないじめがある場合は、その精神的苦痛は計り知れません。
このような状況では、職場に行くこと自体が恐怖となり、休むことでしか心の平穏を保てなくなるのです。
過剰な期待とプレッシャー
良好に見える関係性の中でも、問題は生じます。
例えば、上司や同僚からの期待が大きすぎると、それに応えなければならないというプレッシャーが負担になることがあります。
「常に完璧でなければならない」「期待を裏切ってはいけない」という思いが強すぎると、失敗を恐れるあまり、新しい仕事に挑戦したり、自分の意見を述べたりすることができなくなります。
このような息苦しい人間関係は、徐々にその人の心を蝕んでいきます。
これらの人間関係の問題は、個人の性格だけに原因があるわけではありません。
コミュニケーション不足や、ハラスメントに対する意識の低い職場文化など、環境側の要因も大きく影響しています。
仕事をよく休む人の背景に、このような人間関係の悩みが隠されていないか、慎重に観察することが求められます。
メンタルヘルスの不調を示す重要なサイン
仕事を頻繁に休むという行動は、単なる体調不良や一時的なストレスだけでなく、うつ病や適応障害といったメンタルヘルスの不調が背景にある可能性を疑うべき重要なサインです。
これらの不調は、早期に気づき、適切な対応をとることが何よりも重要になります。
仕事をよく休む人の心理と行動の変化に注意を払うことで、深刻な事態を防ぐことができます。
以下に、メンタルヘルス不調の可能性があるサインを挙げます。
- 勤怠の乱れ: 特定の曜日(特に月曜日)に休むことが増える、遅刻や早退が目立つ、無断欠勤があるといった変化は、出勤への意欲が著しく低下していることを示唆します。
- 表情や態度の変化: 以前よりも表情が暗く、口数が少なくなる、周囲とのコミュニケーションを避けるようになる、逆に些細なことでイライラしたり、攻撃的になったりするなど、感情の起伏が激しくなることがあります。
- 仕事のパフォーマンス低下: 集中力が続かず、ミスが増える、仕事のスピードが落ちる、判断力が鈍るといった変化が見られます。これまで問題なくこなせていた業務に時間がかかったり、投げやりな態度が見られたりすることもサインの一つです。
- 身体的な不調の訴え: 頭痛、めまい、吐き気、不眠など、原因の特定しにくい身体症状を頻繁に訴えるようになります。本人は内科などを受診しても異常なしと診断され、周囲からは「気の持ちよう」と誤解されがちですが、これらは精神的な不調が体に現れたものであることが多いのです。
- 興味・関心の喪失: 以前は楽しんでいた趣味や活動に興味を示さなくなる、好きだった食べ物をおいしいと感じなくなるなど、全般的な喜びの感情が失われます。
これらのサインは、一つだけでなく複数が同時に見られることが多いのが特徴です。
もし同僚や部下にこのような変化が見られた場合、それは本人が発しているSOSかもしれません。
専門家ではない私たちが病名を判断することはできませんが、「いつもと違う」という変化に気づき、心配していることを伝え、専門家への相談を促すといったサポートが、本人を救うきっかけになる可能性があります。
メンタルヘルスの問題は、誰にでも起こりうることを理解し、偏見なく受け止める姿勢が職場全体に求められます。
休みがちなのは「甘え」なのかという問題
「仕事をよく休むのは、本人の甘えが原因だ」。
このように結論付けてしまうのは簡単ですが、事態をより複雑にし、本人をさらに追い詰める危険な考え方です。
仕事をよく休む人の心理を理解しようとせず、「甘え」という一言で片付けてしまうことは、問題の本質を見誤ることに繋がります。
確かに、中には本当に責任感が欠如しており、安易に休みを選択する人もいるかもしれません。
しかし、前述の通り、多くのケースでは過度なストレス、劣悪な職場環境、複雑な人間関係、そしてメンタルヘルスの不調といった、個人の意志だけではどうにもならない深刻な問題が背景に存在します。
例えば、燃え尽き症候群に陥っている人に対して「甘えるな、気合で乗り切れ」と叱咤激励することは、火に油を注ぐようなものです。
彼らはすでに心身のエネルギーを使い果たしており、休息こそが必要な状態です。
そこで無理を強いることは、症状をさらに悪化させ、長期の休職や離職につながるリスクを高めてしまいます。
また、「甘え」と見なされることを恐れるあまり、本人はギリギリまで助けを求めることができず、一人で苦しみを抱え込んでいる場合も少なくありません。
周囲に心配をかけたくない、迷惑だと思われたくないという気持ちが強く、心身が限界に達して初めて、休むという選択肢しか取れなくなるのです。
この状況で「甘え」と非難されることは、彼らの罪悪感を煽り、自尊心を深く傷つけることになります。
この問題を考える上で重要なのは、「甘え」か「そうでないか」を裁くことではありません。
そうではなく、「なぜその人は休まなければならない状況に陥っているのか」という視点を持つことです。
行動の背景にある原因を探り、もし職場に問題があるのであれば、それを改善していく努力が求められます。
もちろん、本人にも自身の状態と向き合い、必要であれば専門家の助けを借りるといった行動は必要です。しかし、その一歩を踏み出すためには、周囲の理解とサポートが不可欠なのです。
安易な「甘え」認定は、解決への道を閉ざしてしまう危険性をはらんでいることを、私たちは肝に銘じるべきでしょう。
仕事をよく休む人の心理と職場での適切な関わり方
- 上司としてできる効果的な対処法
- 同僚として心掛けたいサポート
- 働きやすい職場環境を整える重要性
- 休むことへの罪悪感を和らげるために
- 仕事をよく休む人の心理を理解し未来へ繋げる
上司としてできる効果的な対処法

部下が頻繁に仕事を休むようになった時、上司の対応一つで状況は大きく変わります。
頭ごなしに叱責したり、原因を追及したりするのではなく、まずは部下が安心して話せる環境を整え、適切なサポートを提供することが求められます。
仕事をよく休む人の心理を理解した上で、上司として取るべき効果的な対処法をいくつか紹介します。
1. 個別の面談と傾聴
まずは、他の従業員がいない静かな場所で、1対1の面談の機会を設けます。
ここでの目的は、問い詰めることではなく、部下の話に真摯に耳を傾ける「傾聴」です。
「最近、休むことが多いようだけど、何か困っていることはないか?」と、心配している気持ちを伝え、部下が話しやすい雰囲気を作りましょう。
部下が話し始めたら、途中で話を遮ったり、自分の意見を押し付けたりせず、最後までじっくりと聴くことが重要です。
本人が直接的な原因を話せない場合でも、話の中からストレスの要因や悩みのヒントが見つかることがあります。
2. 業務内容と量の見直し
もし過重労働が原因である可能性が考えられる場合は、部下が担当している業務の内容と量を具体的に確認し、見直す必要があります。
一人で抱え込んでいる業務がないか、本人のスキルやキャパシティを超えた仕事が割り振られていないかを確認し、必要であれば業務の再配分やサポートメンバーの追加を検討します。
一時的に業務負担を軽減するだけでも、本人の心身の回復に繋がることがあります。
3. 産業医や相談窓口との連携
部下の不調がメンタルヘルスに関わるものだと感じた場合、上司だけで抱え込むのは危険です。
会社に産業医やカウンセラー、外部のEAP(従業員支援プログラム)などの相談窓口がある場合は、本人にその存在を伝え、利用を促しましょう。
「専門家に相談することも選択肢の一つだよ」と伝えることで、部下は一人で悩まずに済むと感じることができます。
その際、相談内容の秘密は厳守されることを伝え、安心して利用できるよう配慮することが大切です。
4. 休職制度や柔軟な働き方の提案
心身の回復に時間が必要だと判断される場合は、休職制度の利用を検討することも一つの選択肢です。
また、時短勤務やテレワークなど、本人の状態に合わせた柔軟な働き方を提案することも有効です。
「無理して出社するのではなく、まずは回復に専念してほしい」というメッセージを伝えることで、部下は罪悪感なく療養に集中できます。
上司の役割は、部下を管理・評価するだけではありません。
部下が心身ともに健康な状態で最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、環境を整え、支援することも重要な責務なのです。
同僚として心掛けたいサポート
同僚が頻繁に仕事を休むようになると、業務のしわ寄せが来てしまい、不満や苛立ちを感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、その感情を直接ぶつけてしまっては、職場の雰囲気を悪化させ、相手をさらに追い詰めるだけです。
仕事をよく休む人の心理を理解し、同僚としてできる範囲での適切なサポートを心掛けることが、チーム全体の助けになります。
1. まずは声をかける
特別なことをする必要はありません。
「大丈夫?」「無理しないでね」といった、シンプルな声かけだけでも、相手にとっては大きな支えになります。
休んだ翌日に出社してきた際には、「昨日は大変だったね」と気遣う一言があるだけで、本人の罪悪感は少し和らぎます。
重要なのは、相手を非難するのではなく、心配しているという姿勢を示すことです。
これにより、相手は「自分は孤立していない」と感じ、安心感を得ることができます。
2. 憶測で噂話をしない
「また休んでる」「やる気ないんじゃないの」といったネガティブな噂話は、百害あって一利なしです。
本人がいない場所での陰口は、巡り巡って本人の耳に入り、深く傷つけるだけでなく、職場全体の不信感を増大させます。
休んでいる理由について憶測で語るのではなく、事実として分からないことには触れない、という姿勢を貫くことが大切です。
もし他の同僚が噂話を始めたら、同調せずにそっとその場を離れるなどの対応を心掛けましょう。
3. 業務のフォローは「できる範囲で」
休んでいる同僚の業務をカバーすることは、チームとして当然必要なことです。
しかし、それを一人で全て背負い込み、自分が潰れてしまっては元も子もありません。
業務のフォローは、あくまで自分ができる範囲で行うことを意識しましょう。
もし負担が大きすぎると感じる場合は、自分一人で抱え込まず、上司に相談して、チーム全体で業務を分担するよう働きかけることが重要です。これにより、特定の人に負担が偏る「しわ寄せ」を防ぐことができます。
4. 自分のメンタルヘルスも大切にする
悩んでいる同僚をサポートすることは大切ですが、その問題に深入りしすぎると、自分自身が精神的に疲弊してしまう「共感疲労」に陥る可能性があります。
相談に乗ることはあっても、カウンセラーのように全てを解決しようとする必要はありません。
あくまで自分は同僚という立場であることをわきまえ、適度な距離感を保つことも、自分を守るためには必要です。
同僚としてできることは、専門家のような治療ではなく、温かい理解と協力的な姿勢を示すことです。
その小さな積み重ねが、相手の回復を助け、働きやすい職場環境の維持に繋がっていくのです。
働きやすい職場環境を整える重要性

仕事をよく休む人が現れるのは、個人の問題だけでなく、職場環境そのものに原因が潜んでいる場合が少なくありません。
一時的な対症療法ではなく、根本的な解決を目指すためには、誰もが心身ともに健康で、安心して働ける職場環境を整えることが極めて重要です。
仕事をよく休む人の心理的な負担を軽減し、全ての従業員のパフォーマンスを向上させるための環境づくりについて考えてみましょう。
1. コミュニケーションの活性化
風通しの良い職場は、従業員の精神的な安定に不可欠です。
定期的なチームミーティングや1on1ミーティングはもちろんのこと、日常的な挨拶や雑談が奨励される文化を育むことが大切です。
上司や同僚に気軽に相談できる雰囲気があれば、問題を一人で抱え込むことが減り、早期解決に繋がります。
心理的安全性、つまり「この組織では、自分の意見や気持ちを安心して表明できる」と感じられる状態を確保することが、コミュニケーション活性化の鍵となります。
2. ハラスメントへの厳格な対応
パワーハラスメントやモラルハラスメントは、被害者のメンタルヘルスを深刻に破壊し、休職や離職の直接的な原因となります。
会社としてハラスメントを絶対に許さないという明確な方針を打ち出し、全従業員を対象とした研修を定期的に実施することが重要です。
また、匿名で相談・通報できる窓口を設置し、相談者が不利益な扱いを受けないことを保証する体制を整える必要があります。
3. 適切な労働時間管理と休暇取得の促進
長時間労働の常態化は、従業員の心身を確実に疲弊させます。
労働時間を正確に把握し、時間外労働が常態化している部署や個人には、業務プロセスの見直しや人員の補充といった対策を講じる必要があります。
さらに、有給休暇の取得を奨励し、「休むことは権利である」という文化を醸成することも大切です。
上司が率先して休暇を取得するなどの取り組みも効果的でしょう。
4. 多様な働き方への理解と支援
育児や介護、あるいは自身の持病など、従業員はさまざまな事情を抱えながら働いています。
時短勤務、フレックスタイム制度、テレワークなど、個々の状況に応じて柔軟に働き方を選択できる制度を導入・拡充することで、従業員は仕事とプライベートの両立がしやすくなります。
これにより、離職を防ぎ、多様な人材が活躍し続けられる職場が実現します。
働きやすい職場環境は、一朝一夕に作れるものではありません。
しかし、経営層から現場の従業員まで、一人ひとりが意識を変え、継続的に取り組むことで、組織全体の文化として根付いていきます。
それは結果として、従業員の定着率向上や生産性の向上といった、会社にとっての大きな利益にも繋がるのです。
休むことへの罪悪感を和らげるために
日本の職場文化の中には、いまだに「休むことは悪である」という風潮が根強く残っている場合があります。
体調が悪くても無理して出社することが美徳とされ、休むことに対して強い罪悪感を抱いてしまう人は少なくありません。
この罪悪感が、回復を遅らせ、さらなる心身の不調を招く悪循環を生み出します。
仕事をよく休む人の心理を理解し、本人と周囲が共にこの罪悪感を和らげるための考え方を持つことが重要です。
本人(休む側)が持つべき視点
まず、休むことは「権利」であり、「義務」ではないことを認識しましょう。
労働基準法で定められた有給休暇はもちろんのこと、体調が悪い時に休むのは、自分自身の心身を守るための当然の行動です。
「自分が休んだら周りに迷惑がかかる」という気持ちは、責任感の表れでもありますが、それが過剰になると自分を追い詰めます。
最高のパフォーマンスを発揮するためには、適切な休息が不可欠です。休むことは、次の仕事でより良い成果を出すための「戦略的な投資」であると捉え方を変えてみましょう。
また、自分の代わりはいても、自分の健康を守れるのは自分だけです。
無理をして働き続けた結果、長期離脱になってしまう方が、結果的に会社や同僚に大きな負担をかけることになります。
早期に休息をとり、万全の状態で復帰することこそが、真の責任感と言えるかもしれません。
周囲(見送る側)が持つべき視点
同僚が休むことに対して、寛容な姿勢を持つことが職場全体の雰囲気を良くします。
「お互い様」という意識を持つことが大切です。
今日は同僚が体調を崩して休みましたが、明日は自分が同じ状況になるかもしれません。
その時に、罪悪感なく安心して休める職場であるためには、普段からお互いが休みやすい雰囲気を作っておく必要があります。
休んだ人に対して、「ゆっくり休んでね」「仕事のことは気にしないで」と声をかける文化を育てましょう。
また、一人が休んでも業務が回るような体制を普段から構築しておくことも、企業の重要なリスク管理です。
業務のマニュアル化や情報共有を進め、属人化を防ぐことで、誰かが急に休んでもチーム全体でカバーできる体制を整えることができます。
これにより、休む本人も、フォローする側も、心理的な負担を大幅に軽減することが可能です。
休むことへの罪悪感は、個人と組織の両方の努力によって和らげることができます。
休息をポジティブに捉え、誰もが気兼ねなく心身のメンテナンスができる文化を築くことが、持続可能な働き方の実現に繋がります。
仕事をよく休む人の心理を理解し未来へ繋げる

この記事を通じて、仕事をよく休む人の心理が、単なる「甘え」や「怠慢」といった言葉では片付けられない、多様で複雑な背景を持っていることを探ってきました。
過度なストレス、複雑な人間関係、心身のエネルギーの枯渇、そしてメンタルヘルスの不調など、その裏には本人の力だけではどうにもならない深刻な問題が横たわっていることが多いのです。
この問題を解決し、より良い未来へ繋げていくためには、当事者本人、そして上司や同僚といった周囲の人々、さらには会社組織全体が、それぞれの立場で何をすべきかを考え、行動に移す必要があります。
当事者としてできること
もしあなたが今、仕事を休みがちで悩んでいるのであれば、まずは自分を責めるのをやめましょう。
休んでいるのは、あなたの心と体がSOSを発している証拠です。
そのサインを無視せず、信頼できる人に相談することから始めてみてください。
それが友人や家族であれ、社内の上司や同僚であれ、あるいは専門のカウンセラーや医師であれ、一人で抱え込まないことが何よりも大切です。
自分の状態を客観的に把握し、休息が必要であれば堂々と休み、専門的な助けが必要であればそれを受け入れる勇気が、回復への第一歩となります。
周囲としてできること
上司や同僚という立場からは、休んでいる人を「問題社員」として見るのではなく、「サポートを必要としている仲間」として見ることが求められます。
憶測や偏見で判断せず、まずは相手の話に耳を傾け、心配している気持ちを伝えること。
そして、業務のフォローや職場環境の改善など、できる範囲での具体的なサポートを実践すること。
「お互い様」の精神で支え合う文化を育むことが、チームの結束力を高め、結果的に組織全体の生産性を向上させることに繋がります。
組織として取り組むべきこと
根本的な解決のためには、個人やチームの努力だけでは限界があります。
経営層がリーダーシップを発揮し、誰もが心身ともに健康で働ける職場環境を構築するという強い意志を示すことが不可欠です。
適切な労働時間管理、ハラスメントの撲滅、柔軟な働き方の推進、メンタルヘルスサポートの充実など、制度として働きやすさを保証する取り組みが、従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の定着にも繋がるのです。
仕事をよく休む人の心理を理解しようとすることは、単に一人の従業員の問題を解決するだけに留まりません。
それは、私たち一人ひとりが他者への想像力を持ち、より思いやりのある、そして誰もが安心して自分の能力を発揮できる社会を築いていくための、重要なステップなのです。
- 仕事をよく休む人の心理は単なる甘えではない
- 背景には過度なストレスや燃え尽き症候群がある
- 職場の複雑な人間関係が出勤意欲を削ぐことがある
- 責任感が強く完璧主義な人が休みがちになる傾向
- メンタルヘルスの不調は勤怠や態度の変化に現れる
- うつ病や適応障害などのサインを見逃さないことが重要
- 「甘え」と決めつけることは問題解決を遠ざける
- 上司はまず傾聴し部下が安心して話せる環境を作るべき
- 業務量の見直しや専門家との連携が上司の役割
- 同僚は憶測で噂せず温かい声かけを心掛ける
- 業務フォローは無理せずチーム全体で分担することが大切
- 誰もが働きやすい職場環境の構築が根本的な解決策となる
- コミュニケーションの活性化と心理的安全性の確保が鍵
- 休むことへの罪悪感を和らげる文化醸成が必要
- 休息は次のパフォーマンスへの戦略的投資と捉える