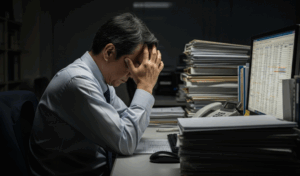「なぜか周りの人のように、うまく生きられない」。
あなたがもし、このように感じているのであれば、それは生きるのが下手な人の特徴に当てはまっているのかもしれません。
現代社会は複雑で、多くの人が生きづらさを感じています。
特に、真面目で優しい人ほど、知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまう傾向があるようです。
この記事では、生きるのが下手な人の特徴について、その根本的な原因から、仕事や人間関係、恋愛といった具体的な場面での悩みまで深く掘り下げていきます。
多くの人が抱える問題として、完璧主義や自己肯定感が低いこと、そしてプライドが高い性格が、どのようにしてストレスの原因となるのかを解説します。
しかし、ご安心ください。
生きづらさを感じるのは、あなたに何か欠陥があるからではありません。
それは、あなたの性格や考え方の癖が、現在の環境と少し合っていないだけのことです。
この記事を最後まで読めば、その特徴を理解し、具体的な改善策を通じて、自分らしく楽に生きるための道筋が見えてくるでしょう。
- 生きるのが下手な人の性格的な特徴
- 完璧主義や自己肯定感の低さが与える影響
- 仕事や人間関係でつまずく原因
- 生きづらさを感じる根本的な理由
- ストレスを溜めずに生きるための改善策
- 考え方を変えて楽になるためのヒント
- 生きるのが下手な人の特徴を強みに変える方法
目次
生きるのが下手な人の特徴とされる10の共通点
- 周囲に流されやすいその性格
- 完璧主義で自分を追い詰める
- 自己肯定感が低く自信がない
- プライドが高く素直になれない
- 人間関係でストレスを溜めやすい
なぜか物事がスムーズに進まない、人間関係でいつも疲弊してしまう。
もしあなたがそう感じているなら、生きるのが下手な人の特徴に当てはまる部分があるのかもしれません。
この章では、多くの人が無意識のうちに抱えている、生きづらさの根源となる共通の特徴について詳しく解説していきます。
これらの特徴を知ることは、自分自身を客観的に理解し、改善への第一歩を踏み出すために非常に重要です。
周囲に流されやすいその性格

生きるのが下手だと感じる人の多くが、周囲に流されやすい性格を持っています。
自分の意見や感情を後回しにして、他人の期待や場の空気に合わせようと努めてしまうのです。
これは、一見すると協調性があるように見えますが、実際には自分自身の軸が確立されていないことの表れでもあります。
例えば、友人から興味のない誘いを受けたときに「断ったら悪いかな」と考えてしまい、本当は疲れているのに無理して参加してしまうことはありませんか。
また、会議の場で、自分の考えとは違う意見が多数派を占めた際に、波風を立てることを恐れて黙り込んでしまうのも、この特徴の一つと言えるでしょう。
このような行動の背景には、「他者から嫌われたくない」「仲間外れにされたくない」という強い不安が隠れています。
自分の意思決定を他人に委ねることで、一時的な安心感を得ようとするのです。
しかし、この状態が続くと、自分が本当に何をしたいのか、何を感じているのかが分からなくなってしまいます。
結果として、他人の価値観に振り回されるだけの人生になり、常に満たされない感覚や虚しさを抱えることになるのです。
私の経験上、このタイプの人は、自分の選択に自信が持てないため、常に誰かの「正解」を探し求めます。
自分の人生の主導権を他人に明け渡してしまっている状態だと言えるでしょう。
この性格を克服するためには、まず小さなことからで良いので、自分で決断する練習を始めることが大切です。
今日の昼食のメニュー、休日に着ていく服、そういった些細な選択から「自分で決める」という感覚を取り戻していく必要があります。
そして、自分の選択が必ずしも他人に受け入れられなくても良いのだと理解することが、自分軸を育む上で不可欠です。
他人の評価を気にしすぎるあまり、自分の心をすり減らしていては、いつまで経っても生きづらさから解放されることはありません。
自分の心の声に耳を傾け、それを尊重することが、生きやすくなるための第一歩となります。
完璧主義で自分を追い詰める
生きるのが下手な人の特徴として、完璧主義もまた、非常に根深い問題です。
何事においても「100点満点でなければ意味がない」と考え、自分自身に非常に高い基準を課してしまいます。
この思考は、質の高い成果物を生み出す原動力になることもありますが、多くの場合、自分を過度に追い詰め、心身を疲弊させる原因となります。
例えば、資料作成を任された際に、細部のデザインや誤字脱字にこだわりすぎるあまり、締め切りギリギリまで作業が終わらない、という経験はないでしょうか。
あるいは、家事を完璧にこなそうとするあまり、少しでも汚れていると気になってしまい、常に掃除や整理整頓に追われ、休む暇がないという状況も考えられます。
完璧主義の背景には、「失敗することへの極端な恐怖」や「他人から無能だと思われたくない」という強い不安が存在します。
彼らにとって、ミスは単なる間違いではなく、自らの価値を揺るがすほどの重大な出来事なのです。
そのため、失敗を避けるために、行動を起こすこと自体をためらってしまう「完璧主義的先延ばし」に陥ることも少なくありません。
「完璧な準備ができるまで始められない」と考え、結果として何も手につかないまま時間だけが過ぎていくのです。
また、完璧主義者は、物事を白か黒か、0か100かで判断する「全か無かの思考」に陥りがちです。
90点の出来栄えであっても、満点ではないという理由で「これは失敗だ」と結論づけてしまいます。
これでは、どれだけ努力しても達成感を得ることができず、自己評価は下がる一方です。
自分自身を褒める機会を自ら奪い、常に欠点ばかりを探してしまうのです。
この呪縛から逃れるためには、「完璧でなくても良い」「60点で合格」という「完了主義」の考え方を取り入れることが効果的です。
まずは「終わらせること」を目標にし、質は後からでも高められると考えるようにシフトするのです。
また、失敗は成長の機会であると捉え直すことも重要になります。
失敗から学び、次に活かすことができれば、それは決して無駄にはなりません。
自分に課した高すぎるハードルを少し下げてあげるだけで、心は驚くほど軽くなり、新しい挑戦への意欲も湧いてくるでしょう。
自己肯定感が低く自信がない

自己肯定感の低さは、生きるのが下手な人が共通して抱える、中心的な課題と言えるでしょう。
自己肯定感とは、ありのままの自分を、良い点も悪い点も含めて肯定し、価値ある存在だと信じる感覚のことです。
この感覚が低いと、常に自分を過小評価し、何事に対しても自信を持って取り組むことができません。
例えば、仕事で成果を上げても「まぐれだ」「周りの人のおかげだ」と素直に自分の実力だと認められなかったり、他人から褒められても「お世辞に決まっている」と疑ってしまったりします。
これは、自分自身の中に「自分は価値のない人間だ」という根深い思い込みがあるためです。
この思い込みは、幼少期の経験や過去の失敗体験から形成されることが多いとされています。
自己肯定感が低いと、他人の評価に過度に依存するようになります。
自分で自分を認められないため、他人からの承認によって自分の価値を確認しようとするのです。
その結果、先述した「周囲に流されやすい」という特徴にも繋がっていきます。
また、新しいことへの挑戦を避ける傾向も強くなります。
「どうせ自分には無理だ」と最初から諦めてしまい、自らの可能性を狭めてしまうのです。
仮に挑戦したとしても、少しの困難に直面しただけで「やっぱりダメだった」とすぐに挫折してしまいがちです。
恋愛や人間関係においても、自己肯定感の低さは深刻な影響を及ぼします。
「こんな自分を好きになってくれるはずがない」と考え、相手の好意を信じられなかったり、逆に相手に過剰に尽くすことで自分の価値を見出そうとしたりします。
これは健全な関係とは言えず、最終的には共依存や破局につながるケースも少なくありません。
自己肯定感を高めるためには、まず自分自身の思考の癖に気づくことが重要です。
無意識のうちに自分を責めたり、他人と比較したりしていないか、日々の思考を観察してみましょう。
そして、小さな成功体験を積み重ね、それを自分で認めてあげることが大切です。
「今日は朝、時間通りに起きられた」「頼まれた仕事を期日内に終えられた」など、どんな些細なことでも構いません。
できたことを記録する「成功日記」をつけるのも良い方法です。
ありのままの自分を受け入れることは、決して簡単なことではありませんが、少しずつでも自分に優しく接することで、生きづらさは確実に軽減していくはずです。
プライドが高く素直になれない
一見すると、自己肯定感が低いことと矛盾するように聞こえるかもしれませんが、「プライドが高い」ことも、生きるのが下手な人の顕著な特徴の一つです。
ここでのプライドの高さとは、健全な自尊心ではなく、「傷つきたくない」「弱い自分を認めたくない」という自己防衛的な感情から生まれる、いわば「見栄」や「意地」に近いものです。
このタイプの人は、自分の非を認めることが極端に苦手です。
仕事でミスをしても、素直に「申し訳ありません」と謝罪できず、言い訳をしたり、他人のせいにしたりしてしまいます。
また、分からないことがあっても「こんなことも知らないのかと思われたくない」というプライドが邪魔をして、他人に質問することができません。
結果として、問題を一人で抱え込み、事態をさらに悪化させてしまうのです。
この行動の根底には、肥大化した「理想の自分」像と、それには程遠い「現実の自分」とのギャップがあります。
彼らは、弱さや欠点を見せることは「負け」であると捉えています。
そのため、常に自分を強く、有能に見せようと必死に鎧をまとっているのです。
しかし、その鎧は非常に脆く、他人からの些細な指摘や批判にも過敏に反応してしまいます。
人間関係においても、この高すぎるプライドは大きな障害となります。
助けを求めることができないため、困っていても誰にも相談できず、孤立を深めていきます。
親しい友人や恋人に対しても、感謝の気持ちや謝罪の言葉を素直に伝えられず、関係がこじれてしまうことも少なくありません。
「ありがとう」や「ごめんなさい」の一言が言えないだけで、多くのものを失ってしまうのです。
私の視点では、このプライドは、低い自己肯定感を隠すための盾のようなものです。
ありのままの自分では受け入れられないという恐怖心が、他者を遠ざける壁を築かせているのです。
この状況を改善するためには、まず「弱さを見せることは恥ずかしいことではない」と認識を改める必要があります。
完璧な人間など、どこにも存在しません。
誰にでも苦手なことや、できないことはあります。
勇気を出して自分の弱さを開示してみると、意外にも周りの人はそれを受け入れ、手を差し伸べてくれることが多いものです。
むしろ、弱さを見せることで、人間的な魅力が増し、より深い信頼関係を築くことができるでしょう。
高いプライドという名の鎧を脱ぎ捨て、等身大の自分でいることを許可してあげることが、生きやすさへの鍵となります。
人間関係でストレスを溜めやすい

これまで述べてきた「周囲に流されやすい」「完璧主義」「自己肯定感が低い」「プライドが高い」といった特徴は、すべて人間関係におけるストレスの大きな原因となります。
生きるのが下手な人は、これらの特徴が複雑に絡み合うことで、他者との関わりの中で過剰な精神的エネルギーを消耗し、疲弊してしまうのです。
例えば、他人の些細な言動を深読みしすぎてしまう傾向があります。
「あの時のあの言葉は、どういう意味だったんだろう」「もしかして、私を嫌っているのではないか」と、頭の中でネガティブなシミュレーションを延々と繰り返してしまいます。
これは、自己肯定感の低さからくる「自分は他人に否定的に見られているはずだ」という思い込みが原因です。
また、人に嫌われることを極端に恐れるため、常に他人の顔色をうかがい、気を使いすぎてしまいます。
自分の意見を抑え、相手に合わせ続けることは、大きなストレスを伴います。
頼み事を断れずに何でも引き受けてしまい、自分のキャパシティを超えてパンクしてしまうことも一度や二度ではないでしょう。
一方で、傷つくことを恐れるあまり、他人と深い関係を築くことを避ける人もいます。
表面的な付き合いに終始し、本音を話せる友人が一人もいないという孤独感を抱えているケースも少なくありません。
プライドの高さが邪魔をして、心を開くことができないのです。
このように、生きるのが下手な人は、他者との距離感の取り方が非常に不器用です。
近づきすぎて依存してしまったり、逆に遠ざけすぎて孤立してしまったりと、安定した関係を保つのが難しいのです。
- 他人の言動を深読みし、ネガティブに解釈する
- 嫌われることを恐れ、自分の意見を言えない
- 頼み事を断れず、一人で抱え込んでしまう
- 傷つくことを恐れ、人と深く関われない
これらの行動パターンは、すべて「自分を守りたい」という気持ちから来ていますが、皮肉なことに、かえって自分自身を苦しめる結果を招いています。
人間関係のストレスを軽減するためには、まず「自分と他人は違う人間である」という事実を深く理解することが大切です。
他人の感情や思考は、あなたにはコントロールできません。
同様に、あなたの感情や思考も、他人がコントロールするものではありません。
この「課題の分離」という考え方を意識するだけで、他人の言動に一喜一憂することが減っていきます。
そして、すべての人に好かれようとする努力は、諦めるべきです。
どれだけ素晴らしい人であっても、その人を嫌う人は必ず存在します。
大切なのは、自分を大切にしてくれる少数の人々との関係を、誠実に育んでいくことです。
そのためには、勇気を出して自分の本音を少しずつ伝えていく練習が必要になるでしょう。
生きるのが下手な人の特徴を克服するための具体的な改善策
- 不器用なりの仕事との向き合い方
- 恋愛がうまくいかない原因と対策
- 考え方を変えて生きづらさを解消
- 自分を許すことから始める克服法
- 生きるのが下手な人の特徴を長所に変える方法
生きるのが下手な人の特徴を理解しただけでは、現状は変わりません。
大切なのは、その知識を元に、具体的な行動を起こしていくことです。
この章では、生きづらさを克服し、より自分らしく楽に生きるための実践的な改善策を、仕事、恋愛、そして考え方といった側面から多角的に提案します。
すぐに全てを実践するのは難しいかもしれませんが、一つでも自分にできそうなことから試してみてください。
小さな一歩が、やがて大きな変化へと繋がっていくはずです。
不器用なりの仕事との向き合い方

生きるのが下手な人は、仕事の場面で特に困難を感じることが多いです。
完璧主義や対人関係の悩みから、能力を十分に発揮できなかったり、過度なストレスを抱えたりしがちです。
しかし、働き方を少し工夫するだけで、その状況は大きく改善される可能性があります。
タスク管理と優先順位付け
まず、仕事の進め方を見直しましょう。
完璧主義の傾向がある人は、全てのタスクを100%の力でこなそうとして、時間切れになったり燃え尽きたりします。
そうならないために、タスクを細分化し、優先順位をつけることが重要です。
例えば、「重要度」と「緊急度」の2軸でタスクを分類するマトリクスを使うのがおすすめです。
「重要かつ緊急」なものから手掛け、時には「重要でないかつ緊急でない」タスクは捨てる勇気も必要です。
「完璧にやること」ではなく「期限内に終わらせること」を第一目標に設定し直しましょう。
60%の完成度でも、まずは提出することが大切です。
報連相の徹底と質問力
プライドが高く、人に頼るのが苦手な人は、一人で問題を抱え込みがちです。
しかし、仕事はチームで行うものです。
分からないこと、困ったことがあれば、早めに報告・連絡・相談(報連相)を徹底しましょう。
「こんなことを聞いたら迷惑かな」と考える必要はありません。
むしろ、問題が大きくなってから報告される方が、周りは迷惑します。
質問する際は、「〇〇について、△△と私は考えているのですが、この認識で合っていますでしょうか?」のように、自分の考えを添えて聞くと、相手も答えやすくなります。
自分に合った環境を選ぶ
そもそも、現在の職場環境や仕事内容が、あなたの特性に合っていない可能性も考えられます。
例えば、頻繁にマルチタスクが求められたり、臨機応変な対人スキルが重要視されたりする職場は、生きるのが下手な人にとってはストレスの原因になりやすいです。
もし可能であれば、一つの作業に集中できる専門職や、自分のペースで進めやすい裁量労働制の仕事、あるいは在宅ワークなどを検討してみるのも一つの手です。
無理に環境に合わせようとするのではなく、自分が輝ける環境を探すという視点も忘れないでください。
恋愛がうまくいかない原因と対策
恋愛は、人間関係の中でも特に密接な関わりを求められるため、生きるのが下手な人にとっては大きな壁となることがあります。
自己肯定感の低さや、素直になれない性格が、健全なパートナーシップを築く上での障害となるのです。
自己肯定感と恋愛の関係
自己肯定感が低いと、「どうせ自分は愛されない」という思い込みから、相手の愛情を常に疑ってしまいます。
相手の些細な言動に不安になり、連絡を過剰に求めたり、束縛したりすることで、相手を疲れさせてしまうことがあります。
逆に、相手に嫌われないようにと過剰に尽くし、自分の意見や感情をすべて押し殺してしまう「尽くしすぎ」に陥ることもあります。
どちらのパターンも、根底にあるのは「ありのままの自分では愛されない」という恐怖です。
この問題を解決するためには、まず恋愛の外で自分の価値を見つけることが重要です。
仕事や趣味など、何でも良いので、自分が夢中になれるものを見つけ、そこで自信をつけましょう。
恋愛は、あなたの価値を決めるものではなく、すでに価値あるあなたを、さらに輝かせるための一要素にすぎません。
素直なコミュニケーションの重要性
プライドの高さから「ありがとう」「ごめんなさい」が言えなかったり、自分の本当の気持ちを伝えられなかったりすることも、恋愛がうまくいかない大きな原因です。
相手に「察してほしい」と期待するのではなく、自分の言葉で気持ちを伝える努力が必要です。
「〇〇してくれて嬉しい、ありがとう」「さっきは感情的になってごめんね」といった言葉を、意識して口に出すようにしましょう。
また、「会えなくて寂しい」「もっと話を聞いてほしい」といった自分の欲求や感情を伝えることも、恐れないでください。
もちろん、伝え方には配慮が必要ですが、本音を伝え合って初めて、二人の関係は深まっていくのです。
もし、自分の気持ちを伝えるのが苦手なら、手紙やメッセージで伝えることから始めてみるのも良い方法です。
素直になることは、負けではありません。
むしろ、相手との信頼関係を築くための、最も賢明な選択なのです。
考え方を変えて生きづらさを解消

生きづらさの多くは、出来事そのものではなく、それをどう捉えるかという「考え方の癖(認知の歪み)」から生まれています。
つまり、この考え方の癖に気づき、修正することで、世界の見え方は大きく変わり、生きづらさを解消できるのです。
認知の歪みに気づく
まずは、自分がどのような認知の歪みを持っているかを知ることから始めましょう。
以下に代表的なものをいくつか挙げます。
- 全か無かの思考:物事を白か黒かで判断し、中間を認めない。「完璧でなければ失敗だ」など。
- 過度の一般化:一度の失敗を、すべてのことに当てはめてしまう。「一度プレゼンで失敗したから、自分は人前で話すのが向いていない」など。
- 心のフィルター:物事のポジティブな側面を無視し、ネガティブな側面だけを見てしまう。
- マイナス化思考:良い出来事も「これは例外だ」などと悪い方向に解釈してしまう。
- 結論の飛躍:根拠がないのに、悲観的な結論を出す。「彼から返信がないのは、嫌われたに違いない」など。
自分が落ち込んだり、不安になったりした時に、どのパターンに陥っているかを客観的に分析する習慣をつけてみましょう。
思考を修正する練習
自分の思考パターンに気づいたら、次はその思考に反論し、より現実的でバランスの取れた考え方を探す練習をします。
例えば、「プレゼンで失敗したから、自分はもうダメだ(全か無かの思考)」と考えたとします。
それに対して、もう一人の自分が「待って。確かに一部は上手くいかなかったかもしれないけど、資料は分かりやすいと褒められたじゃないか。この失敗から学んで、次に活かせば良いだけじゃないか?」と反論するのです。
最初は難しいかもしれませんが、これを繰り返すことで、自動的に湧き上がってくるネガティブな思考を、鵜呑みにしなくなります。
思考は単なる「頭の中に浮かんだ言葉」であり、必ずしも「事実」ではないと理解することが重要です。
「今、ここ」に集中する
生きるのが下手な人は、過去の後悔や未来への不安に心を奪われがちです。
「あの時ああしていれば…」「これからどうなってしまうんだろう…」と考え、目の前のことにおろそかになってしまいます。
この状態から抜け出すために有効なのが、「マインドフルネス」です。
マインドフルネスとは、評価や判断をせず、ただ「今、ここ」の瞬間に意識を向ける心の状態を指します。
例えば、食事をする時に、スマホを見ながらではなく、食べ物の味や香り、食感を一つひとつ丁寧に味わう。
あるいは、呼吸に意識を集中し、空気が鼻を通り、肺が膨らみ、そして出ていく感覚をただ観察する。
このような練習を通じて、過去や未来へとさまよいがちな意識を、現在に戻すことができます。
「今」に集中できるようになると、余計な心配事が減り、心が穏やかになるのを感じられるでしょう。
自分を許すことから始める克服法
生きるのが下手な人の多くは、自分に対して非常に厳しい裁判官です。
常に自分の欠点を探し、小さなミスも許さず、自分を責め続けています。
この厳しい自己批判をやめ、「自分を許す(セルフ・コンパッション)」ことを学ぶのが、克服のための非常に重要な鍵となります。
セルフ・コンパッションとは
セルフ・コンパッションとは、直訳すると「自分への思いやり」です。
親しい友人が失敗して落ち込んでいる時に、あなたはどんな言葉をかけるでしょうか。
「なんてダメなやつなんだ」と罵倒するでしょうか。
いいえ、きっと「誰にでもそういうことはあるよ」「辛かったね」「よく頑張ったね」と優しい言葉をかけるはずです。
セルフ・コンパッションとは、その優しさを、自分自身にも向けてあげることです。
自分が困難な状況にある時、失敗してしまった時に、自分を責めるのではなく、自分自身の良き理解者となり、味方になってあげるのです。
自分を許すための具体的なステップ
では、どうすれば自分を許せるようになるのでしょうか。
- 自分の苦しみに気づく:まずは、自分が今、辛い状況にあること、苦しんでいることを認め、受け入れます。「ああ、今私は苦しいんだな」と客観的に認識します。
- 苦しみは誰もが経験するものだと知る:その苦しみや失敗は、自分だけが経験している特別なものではなく、人間であれば誰しもが経験する共通のものであると理解します。「失敗するのは、人間だから当たり前だ」と考えるのです。
- 自分に優しく接する:そして最後に、自分自身に思いやりのある言葉をかけたり、行動をとったりします。温かい飲み物を淹れてあげる、好きな音楽を聴く、ゆっくりお風呂に入るなど、自分を労わる行動を実践します。
自分を許すことは、自分を甘やかすこととは違います。
それは、ありのままの自分を受け入れ、再び立ち上がるためのエネルギーを与える、非常に建設的な行為なのです。
自分を責めている限り、人は前に進むことができません。
自分を許し、自分の一番の味方になることができた時、あなたは本来持っている強さと優しさを取り戻し、どんな困難にも立ち向かっていけるようになるでしょう。
生きるのが下手な人の特徴を長所に変える方法

この記事の最後に、最も伝えたいことがあります。
それは、これまでネガティブなものとして語られてきた、生きるのが下手な人の特徴は、見方を変えれば素晴らしい長所にもなり得るということです。
克服とは、これらの特徴を消し去ることではなく、そのエネルギーをポジティブな方向に転換し、自分の強みとして活かしていくことなのです。
例えば、以下のようにリフレーミング(捉え直し)することができます。
| 特徴(短所) | リフレーミング(長所) |
|---|---|
| 完璧主義 | 質の高い仕事ができる、責任感が強い |
| 周囲に流されやすい | 協調性がある、共感力が高い、優しい |
| 自己肯定感が低い | 謙虚、常に向上心がある、慎重 |
| プライドが高い | 理想が高い、向上心がある |
| 心配性・考えすぎる | 危機管理能力が高い、思慮深い、計画性がある |
| 不器用 | 一つのことに集中できる、誠実、丁寧 |
いかがでしょうか。
あなたの短所だと思っていた部分は、実は素晴らしい才能の裏返しなのです。
完璧主義だからこそ、誰も真似できないような質の高い成果を生み出せるのかもしれません。
共感力が高く優しいからこそ、人の痛みに寄り添い、誰かを救うことができるのかもしれません。
慎重で思慮深いからこそ、他の人が見落とすようなリスクに気づき、チームを危機から救うことができるのかもしれません。
大切なのは、自分の特性を正しく理解し、それが活かせる場所を選ぶことです。
そして、短所が顔を出しそうになったら、「これは私の強みである〇〇の一面だな」と客観的に捉え、うまくコントロールしていくことです。
生きるのが下手なのではなく、あなたはただ、他の人とは違う、ユニークで素晴らしい感受性を持っているだけなのです。
その特性を呪うのではなく、誇りに思ってください。
自分自身を深く理解し、受け入れ、そして活かす道を選んだ時、あなたの「生きづらさ」は、あなただけの「生きがい」へと変わっていくでしょう。
- 生きるのが下手な人は周囲に流されやすい性格を持つ
- 自分の意見より他人の期待を優先してしまう
- 完璧主義は自分を追い詰め心身を疲弊させる
- 失敗を恐れるあまり行動できなくなることがある
- 自己肯定感の低さが自信のなさに繋がる
- ありのままの自分を価値ある存在だと信じられない
- プライドの高さが素直なコミュニケーションを阻害する
- 自分の非を認められず助けを求められない
- これらの特徴が絡み合い人間関係のストレスを生む
- 仕事では完璧より完了を目指すことが大切
- 恋愛では自分軸を持ち素直に伝える努力が必要
- 考え方の癖に気づき修正することで生きづらさは解消される
- 自分を責めずに許し思いやることが克服の鍵
- 生きるのが下手な人の特徴は見方を変えれば長所になる
- 自分の特性を理解し活かすことが重要である