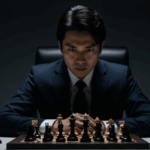「一生懸命仕事に取り組んでいるのに、なぜかミスばかりしてしまう」
「真面目だと言われることが多いけれど、うっかりミスが多くて自己嫌悪に陥ってしまう」
このように、真面目だけどミスが多いという状況に悩んでいる方は少なくありません。
その真面目さゆえに、人一倍責任感が強いにもかかわらず、仕事でミスを繰り返してしまう自分を責めてしまうこともあるでしょう。
この問題の背景には、単なる不注意だけでなく、HSPのような気質や、ADHDといった発達障害の可能性が隠れていることもあります。
しかし、ご安心ください。
真面目だけどミスが多い原因と対策を正しく理解し、適切な改善方法を実践すれば、状況は必ず好転します。
この記事では、真面目だけどミスが多い人の特徴や、考えられる原因を深掘りし、明日から実践できる具体的な対策を詳しく解説していきます。
病気の可能性についても触れながら、あなたが自分らしく、安心して仕事に取り組めるようになるためのヒントを提供します。
- 真面目だけどミスが多い人の具体的な特徴がわかる
- ミスを引き起こす根本的な原因を理解できる
- 明日から実践できる具体的な改善策が見つかる
- 責任感が強い性格とうまく付き合う方法を学べる
- うっかりミスを防ぐための具体的なテクニックを知れる
- HSPやADHDなど、考えられる病気の可能性について知れる
- 自分を責めずに前向きに行動するためのヒントが得られる
目次
真面目だけどミスが多い人の5つの特徴と原因
- 完璧主義で物事を柔軟に考えられない
- 強い責任感から一人で抱え込んでしまう
- 仕事の全体像を把握するのが苦手
- ストレスや疲れで集中力が低下している
- ADHDやHSPなど発達障害の可能性も
完璧主義で物事を柔軟に考えられない

真面目だけどミスが多い人の特徴として、まず挙げられるのが完璧主義である点です。
何事も完璧にこなそうとするあまり、一つの作業に時間をかけすぎてしまったり、細部にこだわりすぎて全体のバランスを見失ったりすることがあります。
この傾向は、高い品質を求める真面目さの表れでもあるのですが、同時にいくつかのデメリットも生み出します。
例えば、資料作成において、誤字脱字がないか、フォントやレイアウトは完璧か、といった点に意識が集中しすぎると、本来伝えるべき内容の優先順位が下がってしまうかもしれません。
結果として、提出期限に間に合わなくなったり、重要なポイントが抜けてしまったりするミスにつながるのです。
また、完璧主義な人は「こうあるべきだ」という強い固定観念を持っていることが多く、予期せぬトラブルや仕様変更に対して柔軟に対応するのが苦手な傾向があります。
私の経験上、計画通りに進まない事態が発生した際に、思考が停止してしまい、どう対処して良いかわからなくなるケースは少なくありません。
完璧を求めるあまり、精神的なプレッシャーが大きくなり、かえって視野が狭くなってしまうことも原因の一つと言えるでしょう。
この状態では、普段ならしないような単純な確認ミスや判断ミスを誘発しやすくなります。
したがって、100点を目指すのではなく、まずは80点で完成させて、残りの時間で見直しや修正を行うといった、良い意味での「妥協」を覚えることが、ミスを減らすための第一歩となるでしょう。
真面目な性格は大きな長所ですが、そのエネルギーをどこに注ぐべきか、優先順位を考える視点を持つことが重要です。
強い責任感から一人で抱え込んでしまう
真面目な人は、一般的に責任感が非常に強い傾向があります。
「任された仕事は自分の力で最後までやり遂げなければならない」という思いが強いため、困難な課題や大量のタスクに直面しても、安易に他人に助けを求めることができません。
この強い責任感は、周囲からの信頼を得る上で大きな武器となりますが、一方で、ミスを引き起こす原因にもなり得ます。
なぜなら、一人で仕事を抱え込むことは、客観的な視点を失うことにつながるからです。
自分一人で作業を進めていると、思い込みや勘違いに気づきにくくなります。
例えば、業務の指示内容を誤って解釈したまま作業を進めてしまい、最終段階で大きな手戻りが発生する、といったケースは典型例でしょう。
もし、作業の初期段階で上司や同僚に「この解釈で合っていますか?」と一言相談していれば、防げたミスかもしれません。
また、一人で抱え込むことは、単純に業務過多につながりやすいです。
自分のキャパシティを超えた仕事量をこなそうとすれば、当然、一つひとつのタスクに対する集中力は散漫になります。
結果として、焦りから確認作業が疎かになったり、疲労で注意力が低下したりして、うっかりミスを連発してしまうのです。
私の視点では、真面目な人ほど「人に頼るのは申し訳ない」「自分の能力不足だと思われたくない」と感じがちですが、組織で仕事をする上では、適切な報告・連絡・相談が不可欠です。
一人で完璧にこなすことだけが責任感の示し方ではありません。
周囲と協力し、チーム全体として最適な成果を出すことも、また重要な責任の果たし方であると認識を改める必要があるでしょう。
仕事の進捗状況を共有したり、少しでも疑問に思った点を気軽に質問したりする習慣をつけることが、結果的にミスを減らし、仕事の質を高めることにつながります。
仕事の全体像を把握するのが苦手

真面目な性格の人は、目の前にある一つひとつのタスクを丁寧に、正確にこなすことに長けています。
しかし、その一方で、木を見て森を見ず、つまり仕事の全体像や最終的な目的を把握するのが苦手な場合があります。
これは、与えられた指示を忠実に守ろうとするあまり、その作業がプロジェクト全体の中でどのような位置づけにあるのか、何のために行っているのか、という視点が抜け落ちてしまうためです。
例えば、上司から「A社のデータをまとめておいて」と指示されたとします。
このとき、真面目な人は、とにかくA社に関するあらゆるデータを集め、きれいに整理することに全力を注ぐかもしれません。
しかし、そのデータが「次の会議で、A社の過去5年間の売上推移を比較検討するために使う」という目的を知らされていれば、まとめるべき情報の範囲や形式は自ずと変わってくるはずです。
全体像を理解していないと、このように求められている成果物との間にズレが生じ、結果として「指示されたことはやったが、目的を果たせていない」というミスにつながってしまうのです。
また、全体像が見えていないと、複数のタスクを抱えた際の優先順位付けも難しくなります。
すべてのタスクが同じ重要度に見えてしまい、緊急性の高い仕事よりも、自分が得意な作業や、すぐに終わりそうな作業から手をつけてしまうことがあります。
結果的に、最も重要で期限が迫っている仕事が後回しになり、焦って取り組んだ結果、ミスを犯してしまうという悪循環に陥るのです。
このような事態を避けるためには、仕事を始める前に、必ずその目的や背景、そして最終的なゴールを確認する習慣をつけることが重要です。
「この作業は何のために行うのですか?」「最終的にどのような状態を目指していますか?」といった質問をすることで、仕事の全体像を把握し、より的確なアプローチで業務に取り組むことができるようになります。
これは、決して指示を疑っているわけではなく、より良い成果を出すための前向きなコミュニケーションと言えるでしょう。
ストレスや疲れで集中力が低下している
真面目だけどミスが多いという悩みは、精神的なストレスや身体的な疲労が原因で引き起こされているケースも少なくありません。
真面目な人は、常に高いパフォーマンスを維持しようと自分にプレッシャーをかけがちです。
また、周囲の期待に応えようとするあまり、無理な仕事量を引き受けてしまったり、長時間労働が常態化したりすることもあります。
このような状態が続くと、心身ともに疲弊し、脳のパフォーマンスが著しく低下してしまいます。
具体的には、以下のような症状が現れることがあります。
- 注意力が散漫になり、簡単な指示を聞き逃す
- 記憶力が低下し、やるべきことを忘れてしまう
- 思考力が鈍り、物事を順序立てて考えられない
- 判断力が低下し、適切な意思決定ができない
これらの症状は、いわゆる「脳疲労」と呼ばれる状態で、十分な休息が取れていないサインです。
脳が疲れている状態では、普段なら絶対にしないような、単純な計算ミスや入力ミス、確認漏れといった「うっかりミス」が頻発するようになります。
いくら「気をつけよう」「集中しよう」と意識しても、脳の機能自体が低下しているため、気力だけではどうにもならないのです。
私の経験上、ミスが続いている時ほど、本人は「もっと頑張らなければ」とさらに自分を追い込んでしまいがちですが、これは逆効果です。
本当に必要なのは、根性ではなく、質の高い休息です。
意識的に休息時間を確保し、仕事から離れてリラックスする時間を作ることが、結果的に集中力を回復させ、ミスを減らすことにつながります。
例えば、睡眠時間をしっかりと確保する、休日は趣味に没頭する、軽い運動でリフレッシュするなど、自分に合った方法で心身を休ませてあげましょう。
また、ストレスの原因が職場環境や人間関係にある場合は、一人で抱え込まずに信頼できる人に相談したり、必要であれば専門家やカウンセラーの助けを借りたりすることも大切です。
自分自身の心と体の健康を守ることが、安定したパフォーマンスを発揮するための最も重要な基盤となります。
ADHDやHSPなど発達障害の可能性も

これまで挙げてきた原因に心当たりがなく、対策を試しても一向にミスが減らない場合、その背景にはADHD(注意欠如・多動症)やHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)といった発達障害や気質が関係している可能性も考えられます。
真面目に努力しているにもかかわらず、不注意によるミスが多発する、というのはADHDの特性の一つである「不注意優勢型」によく見られるケースです。
ADHDの不注意特性には、以下のようなものがあります。
- 細かい部分への注意が苦手で、ケアレスミスが多い
- 集中力を持続させることが難しく、話を聞いていないように見えることがある
- 忘れ物や、やるべきことの失念が多い
- タスクの段取りを組んだり、整理整頓したりすることが苦手
これらの特性は、本人の「真面目さ」や「努力」とは関係なく、脳の機能的な偏りによって生じるものです。
そのため、「気を引き締めろ」といった精神論では根本的な解決にはなりません。
一方で、HSPは病気や障害ではなく、生まれ持った気質ですが、その繊細さゆえに仕事で困難を抱えることがあります。
HSPは、周囲の環境からの刺激を非常に強く受け取るため、音や光、他人の感情などに敏感です。
オフィスのような多くの情報が飛び交う環境では、刺激過多で疲れやすく、集中力を維持するのが難しい場合があります。
また、人の気持ちを察しすぎるあまり、頼み事を断れずに多くの仕事を抱え込んでしまったり、些細なミスでも過度に自分を責めてしまったりする傾向があります。
これらの精神的な負担が積み重なり、結果としてミスにつながることも少なくありません。
もし、これらの特性に心当たりがあり、長年にわたって生きづらさを感じているのであれば、一度、専門の医療機関に相談してみることをお勧めします。
専門家による診断を受けることで、自分の特性を正しく理解し、適切な対処法やサポートを知ることができます。
それは、自分を責めるのをやめ、自分に合った働き方や生き方を見つけるための重要な一歩となるでしょう。
決して一人で悩まず、専門家の力を借りるという選択肢があることを覚えておいてください。
真面目だけどミスが多い状況を改善するための対策
- 仕事の優先順位を明確にする
- わからないことはすぐに相談する習慣をつける
- こまめなメモとタスクの言語化を徹底する
- 自分に合った職場環境への転職も視野に
- うっかりミスは病気の可能性も考え専門医を受診
- 真面目だけどミスが多い自分を責めすぎない
仕事の優先順位を明確にする

真面目だけどミスが多い人がまず取り組むべき対策は、仕事の優先順位を明確にすることです。
多くのタスクを前にして、何から手をつければ良いか分からなくなると、焦りが生じてミスを誘発します。
すべての仕事を「重要」で「緊急」だと感じてしまうと、効率的な業務遂行は難しくなるでしょう。
そこで有効なのが、「緊急度」と「重要度」の2つの軸でタスクを分類する「アイゼンハワー・マトリクス」という考え方です。
具体的には、すべてのタスクを以下の4つの領域に分類します。
- 重要かつ緊急なタスク: すぐに取り組むべき最優先事項(例:クレーム対応、今日が締め切りの仕事)
- 重要だが緊急ではないタスク: 将来の成功に不可欠な、計画的に取り組むべき事項(例:スキルアップのための学習、長期的なプロジェクトの準備)
- 重要ではないが緊急なタスク: 他人に任せたり、効率化したりすることを検討すべき事項(例:多くの定例会議、突然の来客対応)
- 重要でも緊急でもないタスク: やめること、断ることを検討すべき事項(例:不要な資料整理、惰性で続けている業務)
このフレームワークを使うことで、今本当に集中すべきタスクが何であるかを客観的に判断できます。
特に、真面目な人は第2領域の「重要だが緊急ではないタスク」を後回しにしがちですが、ここに時間を投資することが長期的な成長とミス削減につながります。
日々の業務を始める前に、今日やるべきことをすべて書き出し、この4つの領域に振り分けてみましょう。
そして、第1領域のタスクから順番に着手し、それが終わったら第2領域のタスクに取り組む、というルールを徹底するのです。
この習慣を身につけるだけで、仕事の進め方が整理され、精神的な余裕が生まれます。
どの仕事から手をつけるべきか迷う時間が減り、一つのタスクに集中して取り組めるようになるため、結果的にケアレスミスを大幅に減らすことができるでしょう。
タスク管理ツールや手帳を活用し、この優先順位付けを日々の習慣にすることが、改善への大きな一歩です。
わからないことはすぐに相談する習慣をつける
真面目な人ほど、「こんなことを聞いたら迷惑ではないか」「能力が低いと思われるのではないか」と考え、疑問点をそのままにして作業を進めてしまう傾向があります。
しかし、前述の通り、この小さな躊躇が、後々大きな手戻りや致命的なミスにつながることは少なくありません。
ミスを減らすための非常に効果的で、かつシンプルな対策は、「わからないことはすぐに相談する」という習慣を徹底することです。
これを実践するためには、まず「相談=迷惑」という考え方を「相談=リスク回避」という考え方に転換する必要があります。
上司や同僚の視点に立てば、曖昧な理解のまま作業を進められて後で大きな問題になるよりも、初期段階で5分間の質問に答える方が、はるかに効率的です。
適切な相談は、チーム全体のリスクを管理する上で不可欠なコミュニケーションなのです。
とはいえ、いきなり何でも聞くのは気が引けるかもしれません。
そこで、相談をスムーズに行うための工夫をいくつか紹介します。
相談のポイント
1. まずは自分で調べる: 質問する前に、社内マニュアルや過去の資料などを確認し、自分で調べられる範囲のことは調べておきましょう。その上で、どこまで分かっていて、何が分からないのかを明確にして質問します。
2. 相手の状況を配慮する: 相手が忙しそうなタイミングを避け、「今、5分ほどよろしいでしょうか?」と声をかける配慮が大切です。
3. 質問を具体的にする: 「どうすればいいですか?」と丸投げするのではなく、「私は〇〇だと考えたのですが、この進め方で問題ないでしょうか?」というように、自分の考えを添えて質問すると、相手も答えやすくなります。
これらの小さな工夫を重ねることで、相談へのハードルはぐっと下がります。
そして、一度相談する習慣がつけば、業務の理解度が深まり、自信を持って仕事に取り組めるようになります。
結果として、思い込みによるミスは劇的に減少し、周囲との円滑な連携によって仕事の質も向上するでしょう。
勇気を出して、まずは小さな質問から始めてみてください。
こまめなメモとタスクの言語化を徹底する

人間の記憶力には限界があります。
特に、複数の指示を同時に受けたり、多くのタスクを並行して進めたりしていると、「覚えていたはずなのに忘れてしまった」というミスは誰にでも起こり得ます。
真面目だけどミスが多い人は、このワーキングメモリ(作業記憶)の容量が一時的にいっぱいになっている可能性があります。
この問題に対する最も効果的な対策は、脳の負担を減らすこと、つまり「記憶に頼らない仕組み」を作ることです。
そのための具体的な方法が、こまめなメモとタスクの言語化です。
指示を受けたら、どんなに簡単な内容だと思っても、必ずメモを取る習慣をつけましょう。
この時のポイントは、単に相手の言葉を書き写すだけでなく、自分の言葉で要点をまとめ直すことです。
そして、メモを取った後には「〇〇というご指示ですが、この理解で合っていますでしょうか?」と、自分の言葉で復唱して確認する(言語化)のが理想的です。
このプロセスを踏むことで、以下のメリットが生まれます。
- 指示内容の聞き間違いや解釈のズレをその場で修正できる
- 頭の中の情報が文字として整理され、後から見返せる
- 「メモした」という安心感から、脳のワーキングメモリに空きができる
- やるべきことがリスト化され、タスクの抜け漏れを防げる
メモを取るツールは、手帳やノートでも、PCのメモ帳アプリやタスク管理ツールでも、自分が使いやすいもので構いません。
重要なのは、すべての情報を一元管理し、「あれはどこに書いたっけ?」と探す手間がないようにすることです。
また、To-Doリストを作成する際には、単に「資料作成」と書くのではなく、「〇〇会議用のAに関するデータを抽出し、グラフ化してパワポにまとめる」というように、具体的なアクションレベルまで分解(言語化)することが重要です。
タスクが具体的であればあるほど、何から手をつけるべきかが明確になり、行動へのハードルが下がります。
このように、頭の中だけで管理しようとせず、外部のツールに記録・整理する習慣を徹底することが、うっかりミスを防ぎ、安定して業務を遂行するための強力な武器となるのです。
自分に合った職場環境への転職も視野に
これまで紹介した対策を実践しても、ミスが減らずに苦しい状況が続く場合、問題はあなた個人の能力や努力だけではなく、現在の職場環境とのミスマッチにある可能性も考えられます。
真面目な人ほど、「自分がこの環境に適応しなければならない」と頑張りすぎてしまいますが、人にはそれぞれ、能力を発揮しやすい環境と、そうでない環境があります。
例えば、以下のような環境は、ミスを誘発しやすいと言えるかもしれません。
- 常にマルチタスクを求められ、頻繁に電話や割り込み業務が入る職場
- 業務の進め方が標準化されておらず、個人の裁量や判断に任されることが多い職場
- 質問や相談がしにくい雰囲気があり、コミュニケーションが不足している職場
- 短納期で高いプレッシャーがかかる仕事が多い職場
もしあなたが、静かな環境で一つのことにじっくり集中したいタイプであれば、上記のような職場では本来の能力を発揮できず、ストレスからミスを連発してしまう可能性があります。
逆に、マニュアルが整備され、一つひとつの業務を正確に着実にこなすことが評価される職場であれば、あなたの真面目な性格は大きな強みとなるでしょう。
自分を責め続けるのではなく、一度立ち止まって「この環境は本当に自分に合っているのだろうか?」と客観的に見つめ直すことも大切です。
転職は大きな決断ですが、自分の特性に合った環境に移ることで、まるで別人のように生き生きと働けるようになるケースは少なくありません。
例えば、HSPの気質がある人なら、在宅勤務が可能な会社や、個人のパーテーションがしっかり区切られているオフィスを選ぶと、刺激が減って働きやすくなるかもしれません。
ADHDの特性がある人なら、自分のペースで仕事が進められる専門職や、興味のある分野をとことん追求できる研究職などで才能を開花させることも考えられます。
すぐに転職活動を始める必要はありません。
まずは、転職エージェントに登録して、どのような求人があるのか、自分のスキルや特性が活かせる職場はどこなのか、といった情報収集から始めてみるだけでも、視野が広がり、精神的な逃げ道を作ることができます。
今の場所で苦しみ続けることだけが選択肢ではない、ということを覚えておいてください。
うっかりミスは病気の可能性も考え専門医を受診

真面目だけどミスが多いという悩みは、性格や環境だけでなく、医学的な問題が背景にある可能性も否定できません。
特に、以前は問題なかったのに、最近急にうっかりミスが増えた、集中力が続かなくなった、といった変化がある場合は注意が必要です。
考えられる病気としては、前述したADHD(注意欠如・多動症)のほかに、うつ病や適応障害、甲状腺機能低下症などが挙げられます。
うつ病や適応障害は、気分の落ち込みだけでなく、思考力の低下や集中困難、判断力の低下といった認知機能の症状を伴うことが多く、これが仕事上のミス増加に直結することがあります。
過度なストレスが原因で発症することが多く、真面目で責任感の強い人ほど、自分の不調に気づかずに無理を続けてしまい、症状を悪化させる傾向があります。
また、甲状腺機能低下症は、体の新陳代謝を司る甲状腺ホルモンの分泌が減少する病気で、症状の一つとして、物忘れがひどくなったり、ぼーっとしたり、仕事の能率が落ちたりすることが知られています。
これらの病気は、精神論や努力で改善するものではなく、専門的な治療が必要です。
もし、ミスが続くことに加えて、気分の落ち込み、不眠、食欲不振、倦怠感といった心身の不調を感じているのであれば、一人で抱え込まずに専門医を受診することを強くお勧めします。
「どの診療科に行けばいいかわからない」という場合は、まずは心療内科や精神科に相談してみるのが良いでしょう。
受診のメリット
専門医に相談することで、血液検査や心理検査などを通じて、不調の原因を客観的に特定することができます。
もし病気が見つかれば、適切な治療を受けることで症状が改善し、それに伴って仕事のミスも減っていくことが期待できます。
また、ADHDなどの発達障害と診断された場合も、それは決してネガティブなことではありません。
自分の脳の特性を正しく理解し、カウンセリングや認知行動療法、環境調整といった適切な対処法を学ぶことで、困難を乗り越え、自分の強みを活かす道筋が見えてきます。
自分の状態を正しく知ることは、解決への第一歩です。
勇気を出して、専門家の扉を叩いてみてください。
真面目だけどミスが多い自分を責めすぎない
最後に、そして最も重要な対策としてお伝えしたいのは、「真面目だけどミスが多い自分を責めすぎない」ということです。
ミスをしてしまった時、真面目な人ほど「なぜ自分はこんなにダメなんだろう」「また周りに迷惑をかけてしまった」と、過度に自己否定に陥りがちです。
しかし、自分を責め続けることは、何の解決にもなりません。
それどころか、過度な自己批判はストレスを増大させ、自己肯定感を低下させ、さらなるミスを誘発するという負のスパイラルを生み出すだけです。
ミスは、誰にでも起こりうることです。
重要なのは、ミスをしたという事実そのものではなく、そのミスから何を学び、次にどう活かすか、という視点です。
ミスが起きたら、まずは感情的に自分を責めるのではなく、事実を客観的に分析してみましょう。
「なぜこのミスは起きたのか?」「どの段階で気づくことができたか?」「次に同じミスを防ぐためには、どのような仕組みが必要か?」と、原因と対策を冷静に考えるのです。
このプロセスは「リフレクション(内省)」と呼ばれ、失敗を成長の糧に変えるための重要なスキルです。
そして、真面目であることは、あなたの素晴らしい長所であることを忘れないでください。
物事に真摯に取り組む姿勢、最後までやり遂げようとする責任感は、多くの場面で高く評価されるべき資質です。
今は、その真面目さが裏目に出てしまっているだけかもしれません。
この記事で紹介したような対策を通じて、仕事の進め方や考え方を少し調整するだけで、あなたの真面目さは、ミスではなく、高い成果を生み出す力に変わるはずです。
完璧ではない自分を受け入れ、小さな成功体験を積み重ねていくこと。
少しずつでも改善しようと努力している自分を認め、褒めてあげること。
そうした自己肯定の姿勢が、心を軽くし、結果的にパフォーマンスを向上させる一番の近道となるでしょう。
- 真面目だけどミスが多い悩みは多くの人が抱えている
- 原因の一つに完璧主義があり柔軟な思考を妨げる
- 強い責任感が一人で仕事を抱え込む原因になる
- 仕事の全体像を把握せず部分的な作業に集中しがち
- ストレスや疲労が集中力低下を招きミスを誘発する
- ADHDやHSPといった発達障害や気質の可能性も考慮する
- 対策として仕事の優先順位を明確化することが有効
- 緊急度と重要度のマトリクスでタスクを整理する
- わからないことはすぐに相談する習慣がミスを防ぐ
- 相談はリスク回避のための重要なコミュニケーション
- 記憶に頼らずメモとタスクの言語化を徹底する
- 職場環境とのミスマッチが原因の場合転職も選択肢
- うっかりミスが続く場合は病気の可能性も考え専門医を受診する
- 自分を責めすぎずミスを学びの機会と捉えることが大切
- 真面目さは長所であり活かし方次第で強みになる