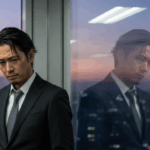「なぜか自分だけ仕事量が多い気がする…」
毎日遅くまで残業し、休日も仕事のことが頭から離れない。
その一方で、同僚は定時で帰り、プライベートを楽しんでいるように見える。
このような状況が続くと、「自分だけ仕事量が多いのは勘違いなのだろうか」と、自身の感覚を疑いたくなるかもしれません。
あるいは、会社に対する不公平感や、どうしようもないストレスに苛まれることもあるでしょう。
その感情は、あなたの責任感が強いからこそ生まれるのかもしれませんし、もしかしたら何らかの心理的な要因が隠れている可能性も考えられます。
しかし、一人で抱え込んで悩む必要はありません。
この記事では、まず自分だけ仕事量が多いと感じる原因を深掘りし、それが勘違いなのか、それとも事実なのかを客観的に判断するための基準を提示します。
さらに、その状況から抜け出すための具体的な対処法、例えば上司への相談の仕方や、業務の効率化、時には仕事を断る勇気を持つことの重要性についても詳しく解説していきます。
あなたの悩みを整理し、解決への第一歩を踏み出すためのヒントがここにあります。
- 自分だけ仕事量が多いと感じる心理的な原因がわかる
- 仕事量が本当に多いのかを客観的に判断する基準がわかる
- 仕事の不公平感から生まれるストレスのサインがわかる
- 仕事を抱え込んでしまう人の特徴と対策がわかる
- 上司に仕事量を相談する際の具体的な伝え方がわかる
- 業務を効率化して自分の時間を取り戻す方法がわかる
- 仕事の過負荷から抜け出すための最終的な手段がわかる
目次
自分だけ仕事量が多いと感じる原因
- 不公平だと感じるのはどんな心理からか
- 仕事量を客観視するための具体的な判断基準
- 勘違いを生むストレスとそのサイン
- なぜか仕事を抱え込んでしまう人の特徴
- 周囲と比較して焦りが生まれるケース
自分だけが忙しいと感じる時、その背景には様々な心理的要因や状況が複雑に絡み合っています。
もしかしたら、自分だけ仕事量が多いのは勘違いかもしれないと考えること自体が、すでにストレスのサインである可能性もあります。
この章では、なぜそのような感情が生まれるのか、その根本的な原因を探っていきます。
不公平感の正体から、客観的な判断基準、ストレスの影響、そして仕事を抱えがちな人の特性まで、多角的に分析することで、ご自身の状況を冷静に見つめ直すきっかけを提供します。
不公平だと感じるのはどんな心理からか

職場において「自分だけ仕事量が多い」と感じ、不公平感を抱く背景には、いくつかの特徴的な心理が働いています。
まず一つ目は、「貢献の可視性」の違いです。
自分の努力や費やしている時間、こなしているタスク量は自分にとって非常に明確ですが、他人の仕事の全容は見えにくいものです。
例えば、あなたが膨大な資料作成に時間を費やしている一方で、同僚は顧客との電話交渉に多くの時間を使っているかもしれません。
目に見える成果物(資料)と、目に見えない成果(交渉)では、どうしても前者の負担が大きいように感じてしまいがちです。
二つ目に、「正義感や公正さへの期待」が挙げられます。
多くの人は、組織内では仕事が公平に分配されるべきだと無意識に考えています。
そのため、その期待が裏切られたと感じた時に、強い不公平感を抱くのです。
特に、真面目で責任感の強い人ほど、この傾向は強くなります。
自分の頑張りが正当に評価されていない、あるいは他の人が楽をしているように見えると、「なぜ自分だけが」という怒りや失望につながるのです。
さらに、「認知バイアス」の影響も無視できません。
人間は自分自身の苦労や努力を過大評価し、他人のそれを過小評価する傾向があります。
これは「自己奉仕バイアス」の一種とも言えます。
自分が深夜まで残業した事実は強く記憶に残りますが、同僚が休日にスキルアップのために勉強している姿は知りません。
自分の視点から見える情報だけで全体を判断してしまうため、どうしても「自分だけが損をしている」という結論に至りやすくなるのです。
これらの心理は、誰にでも起こりうる自然な心の働きです。
大切なのは、自分がこのような心理状態にある可能性を認識し、一度立ち止まって冷静に状況を見つめ直すことと言えるでしょう。
仕事量を客観視するための具体的な判断基準
「自分だけ仕事量が多い」という感覚が、事実なのか、それとも心理的な要因によるものなのかを見極めるためには、感情を一旦横に置いて、客観的な基準で現状を分析することが不可欠です。
ここでは、仕事量を冷静に評価するための具体的な判断基準をいくつか紹介します。
まず、最も基本的なのが「業務の可視化」です。
タスクリストの作成と時間計測
一週間、あるいは一ヶ月間、自分が行った全ての業務を詳細にリストアップしてみましょう。
「〇〇の資料作成」「△△社との打ち合わせ」「メール対応」といった大きな項目だけでなく、「A案件のデータ入力(3時間)」「B会議の議事録作成(1.5時間)」のように、各タスクにかかった時間を記録することが重要です。
これにより、自分が何にどれくらいの時間を使っているのかが明確になります。
同僚やチームの標準との比較
次に、自分の業務内容を、同じ部署の同僚やチーム全体の標準的な業務量と比較してみましょう。
もちろん、個人の能力や役職によって差があるのは当然です。
しかし、明らかに自分だけが担当しているプロジェクト数が多かったり、他の人にはない定常業務を抱えていたりする場合は、仕事量が多いと判断できる材料になります。
可能であれば、信頼できる同僚に「今、これくらいのタスクを抱えているんだけど、一般的にどう思う?」と軽く相談してみるのも一つの手です。
時間外労働の実態
残業時間や休日出勤の頻度も、客観的な指標となります。
恒常的に月45時間を超える残業が続いている、あるいは毎週のように休日出勤をしないと仕事が終わらないという状況は、個人の能力の問題ではなく、物理的な仕事量が許容量を超えている可能性が高いと言えます。
勤怠記録を確認し、具体的な数値を把握しておきましょう。
業務の質と難易度の評価
仕事量は、単純なタスクの数や時間だけでは測れません。
一つ一つの業務の「質」や「難易度」も考慮に入れる必要があります。
例えば、高度な専門知識を要する分析業務や、精神的な負担が大きいクレーム対応などは、単純な事務作業に比べて一時間あたりの負荷が大きく異なります。
自分が担当している業務に、特に難易度が高いものや精神的負荷の大きいものが集中していないかを確認することも大切です。
これらの基準を用いて自分の仕事量を評価することで、「なんとなく忙しい」という曖昧な感覚から、「〇〇という業務に週20時間かかっており、これがチームの平均より10時間多い」といった具体的な事実に落とし込むことができます。
この客観的なデータこそが、次のアクションを考える上での強力な武器となるのです。
| 判断基準 | 具体的な確認方法 | 客観性の高さ |
|---|---|---|
| 業務の可視化 | タスクリストを作成し、各作業にかかった時間を記録する | 高 |
| 他者との比較 | 同僚やチームの平均的なプロジェクト数や業務範囲と比較する | 中 |
| 時間外労働 | 勤怠記録を確認し、月間の残業時間や休日出勤日数を把握する | 高 |
| 業務の質・難易度 | 担当業務の専門性、精神的負荷、責任の重さを評価する | 中 |
勘違いを生むストレスとそのサイン

「自分だけ仕事量が多いのは勘違いかもしれない」と感じること自体が、実は心身が発している重要なサインである可能性があります。
過度なストレスは、私たちの認知を歪め、正常な判断を難しくさせることが科学的にも知られています。
ストレスがかかると、脳内ではコルチゾールというストレスホルモンが分泌されます。
これが長期的に続くと、物事をネガティブに捉えやすくなったり、視野が狭くなったりするのです。
その結果、周囲の状況を冷静に判断できなくなり、「自分だけが大変な状況に置かれている」と思い込みやすくなります。
同僚が効率的に仕事を進めている姿が「楽をしている」ように見えたり、上司からの期待が「過剰な要求」に感じられたりするのは、この認知の歪みが原因かもしれません。
では、具体的にどのようなサインに気をつけるべきでしょうか。
心身からのSOSを見逃さないために、以下のチェックリストを確認してみてください。
身体的なサイン
身体は正直です。
ストレスが蓄積すると、様々な不調として現れます。
- 原因不明の頭痛や腹痛が続く
- 寝つきが悪い、または夜中に何度も目が覚める
- 朝、起きるのが非常につらい
- 食欲が極端にない、または過食気味になる
- 以前はなかった肩こりやめまいに悩まされる
精神的なサイン
心の変化は、自分では気づきにくいこともあります。
注意深く自己観察することが大切です。
- 仕事のやる気が全く起きない、集中力が続かない
- ささいなことでイライラしたり、落ち込んだりする
- 好きだった趣味を楽しめなくなった
- 人とのコミュニケーションが億劫に感じる
- 仕事でミスが増えたり、物忘れが激しくなったりする
これらのサインが複数当てはまる場合、あなたの心身は相当なストレスを抱えている状態です。
仕事量が多いという感覚が「勘違い」であったとしても、ストレスが限界に達しているという事実は揺るぎません。
まずは仕事量の問題を考える前に、自分自身の心と体を休ませ、ケアすることが最優先です。
信頼できる友人や家族に話を聞いてもらったり、専門のカウンセリングを受けたりすることも有効な手段となります。
なぜか仕事を抱え込んでしまう人の特徴
仕事量が物理的に多い場合もあれば、無意識のうちに自分で仕事を増やし、抱え込んでしまっているケースも少なくありません。
もしあなたが「自分だけ仕事量が多い」と感じているなら、自分自身の仕事への向き合い方や性格に、その原因が隠されている可能性もあります。
ここでは、仕事を抱え込みがちな人の特徴をいくつか見ていきましょう。
責任感が強く、完璧主義
「任された仕事は完璧にこなさなければならない」という強い責任感は、ビジネスパーソンとして美徳です。
しかし、それが度を超すと、全てのタスクに120%の力を注ごうとしてしまいます。
資料の細かな体裁にこだわりすぎたり、メールの文面を何度も推敲したりと、本来の目的以上に時間をかけてしまうのです。
また、「この仕事は自分にしかできない」と思い込み、他人に任せることを躊躇する傾向もあります。
他者からの評価を気にしすぎる
「断ったら、仕事ができないと思われるかもしれない」「期待に応えなければ、評価が下がってしまう」といったように、周囲からの評価を過度に気にする人も仕事を抱え込みがちです。
上司や同僚からの依頼を断れず、自分のキャパシティを超えて安請け合いしてしまいます。
「良い人」「仕事ができる人」と思われたいという承認欲求が、結果的に自分を追い詰めることにつながるのです。
NOと言えない、頼み事を断るのが苦手
これは他者からの評価を気にする心理とも関連しますが、シンプルに「断る」という行為自体が苦手なタイプです。
相手をがっかりさせたくない、場の空気を悪くしたくないという気持ちが強く働き、無理な依頼でも「大丈夫です」と引き受けてしまいます。
自分の限界を伝えることよりも、相手との関係性を優先してしまう優しさが、仕事の過負荷を招いているのです。
仕事の全体像を把握するのが苦手
目の前のタスクに集中するあまり、仕事の優先順位付けや全体的なスケジュール管理が苦手な人も、結果的に仕事を抱え込むことになります。
緊急度は低いけれど重要なタスクを後回しにし、締め切り間近になって慌てて残業するといったことが頻発します。
また、どの仕事にどれくらい時間がかかるかの見積もりが甘く、気づいた時には膨大なタスクに埋もれてしまっているという状況に陥りやすいです。
これらの特徴に心当たりがある場合、仕事量の問題は、会社の体制だけでなく、あなた自身の働き方や考え方を見直すことで改善できる可能性があります。
自分を責める必要はありません。
まずは自分の傾向を認識することが、問題解決の第一歩となります。
周囲と比較して焦りが生まれるケース

「自分だけ仕事量が多い」という感情は、多くの場合、他者との比較から生まれます。
特に、オフィスのような閉じた環境では、同僚の働きぶりが常に目に入るため、比較の罠に陥りやすくなります。
例えば、定時になるとすぐに退社する同僚Aさんを見て、「なぜAさんはいつも早く帰れるのだろう。
それに比べて自分は…」と感じてしまうケースです。
この時、私たちはAさんが日中の業務時間内に、いかに集中して効率的に仕事を進めているかというプロセスを見ていません。
あるいは、Aさんの担当業務が、短時間で完結するタイプのタスクが多いのかもしれません。
見えているのは「定時で帰る」という結果だけであり、その結果だけを自分の状況と比較して、不公平感や焦りを募らせてしまうのです。
また、SNSの普及も、この比較による焦りを加速させる一因となっています。
同僚や友人が、仕事後に充実したプライベートを過ごしている様子をSNSで見て、「自分はこんなに仕事に追われているのに、他の人は人生を楽しんでいる」と感じてしまうことはないでしょうか。
SNSに投稿されるのは、その人の生活の「キラキラした一部分」に過ぎません。
しかし、私たちはその断片的な情報と、自分の24時間全てを比較してしまい、あたかも自分だけが取り残されているかのような孤独感や劣等感を抱いてしまうのです。
役割と評価軸の違い
重要なのは、人それぞれ役割や期待されている成果、評価の軸が異なるという事実を理解することです。
例えば、営業職であれば顧客との関係構築や契約数が評価されますし、開発職であれば製品の品質や納期遵守が評価されます。
仕事の性質が違えば、時間の使い方も、忙しさのピークも全く異なります。
あなたが膨大なデータと向き合っている時間に、営業の同僚は外回りで足を使っているかもしれません。
どちらが大変かは、一概には言えないのです。
周囲と比較して焦りを感じた時は、「自分と他人は違う」という当たり前の事実を思い出すことが大切です。
比較するべき相手は、過去の自分です。
昨日より少しでも効率的に仕事を進められたか、先月より何か新しいスキルが身についたか、といった内面的な成長に目を向けることが、不必要な焦りから解放されるための鍵となります。
自分だけ仕事量が多いのは勘違いではない場合の対処法
- まずは上司に相談するタイミングと伝え方
- 業務の効率化で自分の時間を確保する
- できない仕事には断る勇気も必要
- 頑張りすぎないためのセルフケア方法
- 自分だけ仕事量が多いのは勘違いではなかった時の最終手段
前章で解説した客観的な判断基準を試した結果、「やはり、自分だけ仕事量が多いのは勘違いではない」と確信に至るケースもあるでしょう。
その場合、感情的に不満を募らせたり、一人で抱え込んで心身をすり減らしたりするのは最も避けるべき事態です。
問題が明確になった今こそ、具体的な行動を起こす時です。
この章では、過剰な仕事量という問題を解決するための、実践的な対処法をステップごとに解説します。
上司への効果的な相談の仕方から、日々の業務効率化、そして自分を守るための最終手段まで、あなたの状況を改善するための具体的な武器を手にしていきましょう。
まずは上司に相談するタイミングと伝え方

仕事量の問題が個人の努力だけでは解決できないレベルに達している場合、直属の上司に相談することは不可欠なステップです。
しかし、伝え方を間違えると、ただの不満や愚痴と捉えられかねません。
効果的に問題を伝え、具体的な改善につなげるためには、事前の準備と戦略的なコミュニケーションが重要になります。
相談のベストタイミング
相談を持ちかけるタイミングは慎重に選びましょう。
上司が締め切りに追われていたり、他のトラブル対応で忙殺されていたりする時に話を持ちかけても、じっくりと耳を傾けてもらうことは難しいです。
週の初めや、比較的落ち着いている時間帯を見計らい、「業務の進め方についてご相談したいことがあるのですが、15分ほどお時間をいただけないでしょうか」と、事前にアポイントを取るのが最も丁寧で確実な方法です。
これにより、上司も話を聞く心構えができます。
伝えるべき内容と準備
相談の場では、感情的に「忙しくて大変なんです」と訴えるのではなく、客観的な事実(ファクト)を元に話を進めることが成功の鍵です。
前章で整理したデータを活用しましょう。
具体的には、以下の3つのポイントを準備しておくと、話がスムーズに進みます。
- 現状の客観的なデータ:担当しているプロジェクトの一覧、各タスクにかかっている工数、月の平均残業時間など、具体的な数値を示します。「現在、A、B、Cの3つのプロジェクトを担当しており、それぞれの工数は週に15時間、20時間、15時間で、合計50時間となっています。結果として、月の平均残業時間は60時間に達しています」のように伝えます。
- 問題点と懸念:その状況が続くことで、どのような問題が発生するかを伝えます。「このままでは、各プロジェクトの品質維持が難しくなり、ミスが発生するリスクが高いと感じています。また、自身の心身の健康にも不安があります」と、会社にとってもリスクであることを示唆します。
- 改善のための提案:ただ問題を指摘するだけでなく、自分なりの改善案を提示できると、より建設的な話し合いになります。「可能であれば、Cプロジェクトの一部を他の方にお手伝いいただけないでしょうか。または、Bプロジェクトの納期を調整することは可能でしょうか」といった具体的な提案です。
伝え方のポイント
相談する際は、あくまで「前向きな改善のための相談」というスタンスを崩さないことが大切です。
「誰かのせいで」といった他責の姿勢や、不満をぶつけるような態度は避けましょう。
「チーム全体の生産性を上げるために、業務の再配分についてご相談させてください」というように、自分個人の問題ではなく、チームや組織の問題として捉えていることを示すと、上司も協力的な姿勢になりやすいです。
冷静に、論理的に、そして前向きに。この3つを意識して相談に臨むことで、問題解決の可能性は大きく高まるはずです。
業務の効率化で自分の時間を確保する
上司への相談と並行して、自分自身でできる業務の効率化を進めることも、状況を改善するために非常に重要です。
たとえ仕事の総量が減らなかったとしても、一つ一つのタスクをより短い時間でこなせるようになれば、結果的に自分の時間を確保し、心身の負担を軽減することができます。
ここでは、すぐに実践できる業務効率化のテクニックをいくつか紹介します。
タスクの優先順位付けを徹底する
全ての仕事を同じ熱量でこなそうとすると、時間はいくらあっても足りません。
「緊急度」と「重要度」の2つの軸でタスクを4つに分類する「アイゼンハワー・マトリクス」を活用しましょう。
| 重要度:高 | 重要度:低 | |
|---|---|---|
| 緊急度:高 | 第1領域:すぐやるべき仕事(クレーム対応、締切間近のタスク) | 第3領域:できれば人に任せる、やらない仕事(多くの会議、突然の来客) |
| 緊急度:低 | 第2領域:最優先で取り組むべき仕事(長期的な計画、スキルアップ) | 第4領域:やらない、後回しにする仕事(無駄な雑談、情報収集) |
多くの人は第1領域と第3領域の「緊急な仕事」に追われがちですが、本当に成果につながるのは第2領域の「緊急ではないが重要な仕事」です。
毎朝、その日のタスクをこのマトリクスに当てはめ、第2領域の仕事に取り組む時間を意識的に確保することが重要です。
シングルタスクに集中する
メールをチェックしながら資料を作成し、時々チャットにも返信する…といったマルチタスクは、一見効率的に見えますが、実際には脳に大きな負担をかけ、集中力を散漫にさせて生産性を低下させることが分かっています。
一つのタスクに取り組む時間を決め(例えば25分間のポモドーロ・テクニックなど)、その間は他の通知をオフにするなどして、一つの作業に没頭する「シングルタスク」を心がけましょう。
その方が、結果的に質の高い仕事を早く終えることができます。
ツールを積極的に活用する
定型的な作業や単純作業は、積極的にツールやテクノロジーに任せましょう。
例えば、何度も入力する文章はテキストエディタのスニペット機能に登録しておく、Excelのマクロを組んでデータ集計を自動化する、タスク管理ツールでチームの進捗を共有するなど、探せば業務を効率化するヒントは無数にあります。
新しいツールを覚えるのには少し時間がかかるかもしれませんが、長期的に見れば大きな時間短縮につながります。
これらの効率化は、一度に全てを完璧に行う必要はありません。
自分にできそうなことから一つずつ試してみて、少しでも「楽になった」と感じられれば、それがあなたの負担を軽くする大きな一歩となるはずです。
できない仕事には断る勇気も必要

業務の効率化を図り、上司にも相談した。
それでもなお、物理的に不可能な量の仕事を依頼されることがあるかもしれません。
そんな時、自分を守るために必要になるのが、「断る勇気」です。
多くの真面目で責任感の強い人にとって、「断る」ことは非常に心苦しい行為かもしれません。
相手をがっかりさせたくない、自分の評価を下げたくないという気持ちが働くからです。
しかし、自分のキャパシティを超えた仕事を引き受けてしまうことは、長期的には誰のためにもなりません。
無理に引き受けた結果、仕事の質が低下したり、納期に遅れたりすれば、かえって相手に迷惑をかけ、信頼を損なうことになります。
また、あなた自身が心身の健康を害してしまっては、元も子もありません。
プロフェッショナルとして、質の高い仕事を継続的に提供するためには、自分の限界を把握し、それを正直に伝えることも重要な責任の一つなのです。
上手な断り方のコツ
ただ「できません」と突き放すのではなく、相手への配慮を示しつつ、誠実に状況を伝えることがポイントです。
以下に、角を立てずに断るための具体的な言い回しを紹介します。
- 感謝と代替案を示す:「お声がけいただき、ありがとうございます。大変魅力的なお話なのですが、現在Aの案件で手一杯でして…。もし来週までお待ちいただけるようでしたら、ぜひ担当させていただけますでしょうか。」
- 優先順位を確認する:「承知いたしました。その仕事をお引き受けする場合、現在進めているBのタスクの優先度を下げることになりますが、よろしいでしょうか。」(上司からの依頼の場合に有効)
- できない理由を正直に伝える:「申し訳ありません。その業務に関する知識が私には不足しており、ご期待に沿えるクオリティで仕上げるのが難しい状況です。この件でしたら、専門である〇〇さんの方が適任かと思います。」
このように、単に拒否するのではなく、代替案を提示したり、優先順位の判断を相手に委ねたりすることで、協力的な姿勢を示すことができます。
断ることは、決してネガティブな行為ではありません。
それは、あなた自身の仕事の質と、あなたの心身の健康を守るための、積極的で賢明な選択なのです。
最初は勇気がいるかもしれませんが、一度実践してみることで、意外と相手も理解してくれることに気づくはずです。
頑張りすぎないためのセルフケア方法
仕事量が多い状況が続くと、知らず知らずのうちに心と体は限界に近づいていきます。
問題解決に向けて行動することも大切ですが、それと同時に、意識的に自分を労り、心身を回復させる「セルフケア」の時間を確保することが不可欠です。
「忙しくてそんな時間はない」と感じるかもしれませんが、短い時間でも効果的なセルフケアは可能です。
ここでは、日々の生活に取り入れやすいセルフケア方法をいくつかご紹介します。
デジタルデトックスの時間を設ける
スマートフォンやPCは仕事のツールであると同時に、私たちの脳を常に刺激し続ける存在です。
就寝前の1時間や、休日の半日など、意識的にスクリーンから離れる時間を作りましょう。
その時間に、読書をしたり、音楽を聴いたり、あるいはただぼーっとするだけでも、脳を休ませることができます。
特に、仕事の連絡が気になるからと、休日もメールやチャットをチェックする習慣がある人は、意識してデジタルデトックスを実践することが重要です。
質の高い睡眠を確保する
睡眠は、心身の疲労を回復させるための最も基本的な活動です。
単に長く眠るだけでなく、「質」にこだわりましょう。
寝る前にぬるめのお風呂にゆっくり浸かる、寝室の照明を暗くしてリラックスできる環境を整える、アロマを焚くなど、自分なりの入眠儀式を見つけるのがおすすめです。
睡眠不足は、集中力や判断力の低下に直結し、日中の仕事のパフォーマンスを悪化させる悪循環を生みます。
忙しい時こそ、睡眠時間を削るのではなく、最優先で確保するようにしましょう。
軽い運動を習慣にする
デスクワークが続くと、体は凝り固まり、血行も悪くなります。
ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、軽い運動を習慣にすることで、心身のリフレッシュにつながります。
運動には、ストレスホルモンを減少させ、幸福感をもたらすセロトニンなどの脳内物質の分泌を促す効果もあります。
ジムに通う時間がなくても、一駅手前で降りて歩いたり、寝る前に5分だけストレッチをしたりと、できる範囲で体を動かすことを意識してみてください。
仕事と全く関係ない趣味に没頭する
仕事のことを完全に忘れられる時間を持つことは、精神的な健康を保つ上で非常に効果的です。
それが、映画鑑賞でも、ガーデニングでも、プラモデル作りでも、何でも構いません。
「これをしている時は、仕事の悩みなんてどうでもよくなる」と思えるような、あなたが心から楽しめる趣味に没頭する時間を作りましょう。
セルフケアは、自分を甘やかすことではありません。
明日も元気に働き、良いパフォーマンスを発揮するための、大切な自己投資なのです。
自分だけ仕事量が多いのは勘違いではなかった時の最終手段

これまで紹介したあらゆる対処法を試しても、状況が全く改善されない。
上司に相談しても理解が得られない、あるいは会社の体制そのものに問題があり、個人の努力ではどうにもならない。
そのような場合、残念ながら、その環境に身を置き続けることは、あなたのキャリアと健康にとって大きなリスクとなります。
自分だけ仕事量が多いのは勘違いではなかったと明確になった時、最終手段として「環境を変える」という選択肢を真剣に検討する必要があります。
これは、決して「逃げ」ではありません。
あなたの価値を正当に評価し、あなたが健康的に能力を発揮できる場所を求める、戦略的で前向きな決断です。
具体的には、社内での「異動」や、会社そのものを変える「転職」が考えられます。
異動を検討する
もし、現在の部署の体質や、特定の上司との関係性に問題の原因がある場合、社内での部署異動が有効な解決策となることがあります。
人事部やキャリア相談窓口などに、現状を客観的な事実に基づいて伝え、異動の希望を申し出てみましょう。
会社としても、優秀な人材を社外に流出させるのは損失です。
あなたの貢献度が高ければ、真剣に検討してくれる可能性があります。
転職を視野に入れる
会社の文化そのものが長時間労働を是としていたり、慢性的な人手不足で業務量が構造的に過剰であったりする場合は、転職が最も現実的な選択肢となります。
今の会社で頑張り続けて心身を壊してしまう前に、新しい可能性を探し始めるべきです。
転職活動を始めることには、多くのメリットがあります。
まず、自分の市場価値を客観的に知ることができます。
また、他の会社の労働環境や文化について情報収集する中で、いかに現在の職場が異常であるかに気づくこともあります。
すぐに転職するつもりがなくても、転職エージェントに登録して情報収集を始めるだけでも、精神的な「お守り」になり、心に余裕が生まれます。
大切なのは、あなた自身です。
会社のために自分を犠牲にする必要は全くありません。
あなたの心と体が「もう限界だ」と悲鳴を上げているのなら、その声に正直に耳を傾け、自分自身を守るための行動を起こしてください。
その勇気ある一歩が、より良い未来への扉を開くことになるはずです。
- 「自分だけ仕事量が多い」と感じる背景には心理的な要因がある
- 他人の仕事は見えにくく自分の貢献を過大評価しがち
- 仕事量を客観視するには業務の可視化と時間計測が有効
- 残業時間や休日出勤の頻度は客観的な判断材料になる
- 過度なストレスは認知を歪め正常な判断を妨げる
- 原因不明の体調不良や集中力低下はストレスのサイン
- 責任感が強く完璧主義な人は仕事を抱え込みやすい
- 他者評価を気にして依頼を断れないのも原因の一つ
- 仕事量の不満は客観的データを用意して上司に相談する
- 相談は感情的にならず前向きな改善提案として伝える
- タスクの優先順位付けで重要な仕事に集中する
- キャパシティを超える仕事は勇気を持って断ることも重要
- 断る際は代替案を示し協力的な姿勢を見せる
- 心身の健康を守るためのセルフケアを意識的に行う
- あらゆる手段を尽くしても改善しない場合は環境を変える選択肢を持つ