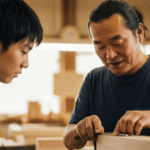あなたの周りに、いつも視線が定まらずキョロキョロする人はいませんか。
あるいは、あなた自身が「人から落ち着きがないと思われていないか」と悩んでいるかもしれません。
キョロキョロする人という行動の裏には、様々な心理や原因が隠されています。
単なる癖だと片付けてしまうこともできますが、その背景には不安や警戒心、自信のなさといった心理状態が関係していることが多いのです。
この記事では、キョロキョロする人の心理的特徴を深掘りし、その行動がなぜ起こるのか、原因を明らかにしていきます。
男性や女性といった性別による悩みの違いや、仕事の場面での影響、さらには病気の可能性にまで言及し、多角的な視点から解説します。
また、挙動不審に見えてしまうこの行動をどうすれば改善できるのか、具体的な治し方やトレーニング方法も紹介します。
この記事を読めば、キョロキョロする人への理解が深まるだけでなく、もしご自身が悩んでいるのであれば、その解決に向けた第一歩を踏み出せるでしょう。
- キョロキョロする人の隠れた心理状態
- 行動の背景にある具体的な原因
- 落ち着きがないと思われる人の行動パターン
- 男性と女性で異なる悩みの傾向
- 仕事への影響と具体的な対策
- 癖を改善するための具体的な治し方
- 考えられる病気や発達障害との関連性
目次
キョロキョロする人の心理的な原因とは
- 周囲を警戒してしまう癖の心理
- 落ち着きがない人の行動の特徴
- 病気や発達障害の可能性
- 挙動不審に思われる男性の悩み
- 女性に多い自信のなさの表れ
周囲を警戒してしまう癖の心理

キョロキョロする人の行動の根底には、周囲の環境や人々に対する強い警戒心が隠れていることが少なくありません。
これは、過去の経験から形成された一種の防衛本能であると考えられます。
たとえば、過去に人間関係で傷ついた経験があると、他者からの批判や悪口を極度に恐れるようになります。
その結果、常に周囲の人の表情や声色をうかがい、自分に危害が及ばないかを確認する癖がついてしまうのです。
この心理は、自分を守りたいという強い思いの表れであり、決して悪意のある行動ではありません。
また、新しい環境や慣れない場所にいるときにも、警戒心は強まる傾向があります。
未知の状況では、何が起こるか予測できないため、情報を少しでも多く集めようと無意識に視線を動かしてしまいます。
これは、危険を察知し、迅速に対応するための生存本能とも言えるでしょう。
しかし、この警戒心が過剰になると、日常生活において常に緊張状態を強いられることになり、心身ともに疲弊してしまう可能性があります。
キョロキョロと視線を動かすことで、自分にとって安全な場所かどうか、敵意を持つ人物はいないかといった情報を常に収集している状態なのです。
この心理状態にある人は、物音に敏感であったり、人の気配をすぐに察知したりする特徴も見られます。
本人は無意識のうちにこの行動をとっている場合が多く、周囲から「挙動不審だ」と指摘されて初めて自覚することもあります。
したがって、キョロキョロする人の行動を理解するためには、その背景にある警戒心という心理を無視することはできません。
警戒心を強める環境的要因
人の心理は環境によって大きく左右されます。
特に、常に評価や監視の目にさらされていると感じる職場環境は、警戒心を強める一因となり得ます。
例えば、上司が部下の行動を細かくチェックしたり、同僚同士の競争が激しかったりする環境では、従業員は常に他者の目を意識せざるを得ません。
このような状況下では、ミスをしないように、あるいは他者から出し抜かれないようにと、自然と周囲への警戒アンテナが敏感になります。
結果として、無意識のうちにキョロキョロと周りを見渡す行動が増えることになるのです。
また、プライベートな空間が確保されにくい場所、例えばオープンなオフィスや騒がしいカフェなども、人を落ち着かなくさせ、警戒心を煽る可能性があります。
自分のパーソナルスペースが脅かされていると感じると、人は不安を覚え、周囲の状況を把握しようと視線を動かします。
このような環境的要因が、キョロキョロする癖を助長しているケースは少なくありません。
過去の経験が与える影響
過去のトラウマやネガティブな経験も、現在の警戒心に深く関わっています。
いじめや裏切り、大きな失敗などを経験した人は、他者や社会に対して不信感を抱きやすくなります。
「また同じような辛い思いをしたくない」という強い思いが、無意識のうちに自己防衛的な行動、つまり周囲を警戒する行動へとつながるのです。
このような経験を持つ人は、他者の些細な言動にも敏感に反応し、その真意を探ろうとします。
相手の表情や視線の動き、声のトーンから情報を読み取ろうとするため、自然と観察するような視線の動きが多くなります。
これは、次に起こりうる危険を予測し、心の準備をするための行動と言えるでしょう。
しかし、過去の経験に縛られすぎると、すべての人や状況を色眼鏡で見てしまい、健全な人間関係を築くのが難しくなることもあります。
キョロキョロする癖の裏にある、過去の傷ついた経験を理解することが、その人への深い共感につながる第一歩となります。
落ち着きがない人の行動の特徴
キョロキョロする人は、しばしば「落ち着きがない」という印象を他人に与えがちです。
この落ち着きのなさは、視線の動きだけでなく、他の様々な行動にも表れることがあります。
これらの特徴を理解することで、なぜその人が落ち着きなく見えるのか、その背景にある心理をより深く探ることができます。
まず、最も顕著な特徴は、一つのことに集中するのが苦手であるという点です。
会話中に相手の話を聞いているようで、視線は窓の外や通り過ぎる人に向いていたり、手元のスマートフォンを頻繁に確認したりします。
これは、外部からの刺激に意識が散漫になりやすい、あるいは内面的な不安や焦りから一つの対象に注意を向け続けることが困難になっている状態です。
また、身体的な動きにも落ち着きのなさが現れます。
- 貧乏ゆすりをする
- 指で机をトントンと叩く
- 頻繁に姿勢を変える
- 髪の毛や顔を何度も触る
これらの行動は、内に溜まったエネルギーやストレスを発散させようとする無意識の表れと考えられます。
じっとしていることへの苦痛や、何か別のことをしたいという衝動が、こうした細かな動きとなって表面化するのです。
さらに、思考や会話の面でも落ち着きのなさは見られます。
話のテーマが次々と飛んだり、相手の話を最後まで聞かずに自分の話を始めてしまったりすることがあります。
これは、頭の中で多くの考えが駆け巡っており、それらを整理する前に言葉として発してしまうために起こります。
本人は多くのことを伝えたい、あるいは早く結論を知りたいという焦りから行動しているのかもしれませんが、周囲からは「話がまとまらない人」「せっかちな人」という印象を持たれやすくなります。
これらの行動は、その人の性格的な側面だけでなく、強いストレスや不安、あるいはADHD(注意欠如・多動症)などの特性が関係している可能性も考えられます。
単に「落ち着きがない」と評価するのではなく、その背後にあるかもしれない困難や特性に目を向けることが重要です。
病気や発達障害の可能性

キョロキョロするという行動は、多くの場合、性格や心理状態に起因するものですが、中には医学的な背景が隠れている可能性も考慮する必要があります。
特に、その行動が日常生活や社会生活に支障をきたすほど顕著である場合は、専門家の診断を仰ぐことも一つの選択肢です。
考えられる可能性の一つとして、ADHD(注意欠如・多動症)が挙げられます。
ADHDの特性の一つに「不注意」があり、これは物事に集中し続けることが難しいという特徴です。
周囲の些細な物音や光景にすぐに注意がそれてしまうため、結果としてキョロキョロと視線が動きやすくなります。
また、「多動性」の特性は、じっとしていることへの困難さとして現れ、常にそわそわとしたり、体を動かしたりする行動につながります。
これらの特性が組み合わさることで、「落ち着きがなく、キョロキョロする人」という印象が強まることがあります。
次に、不安障害(不安症)も関連が考えられます。
全般性不安障害や社交不安障害などを抱えている人は、常に過剰な心配や恐怖を感じています。
そのため、周囲の環境に危険がないか、他者から否定的に評価されていないかなどを常に確認しようとし、視線が定まらなくなるのです。
これは、不安という内的な脅威から自分を守るための行動であり、本人の意思でコントロールすることが難しい場合があります。
さらに、あまり一般的ではありませんが、特定の薬の副作用や、甲状腺機能亢進症などの身体的な病気が、落ち着きのなさや多動といった症状を引き起こすこともあります。
もし、キョロキョロする行動に加えて、極端な気分の落ち込みや集中力の低下、睡眠障害などが伴う場合は、単なる癖ではなく、治療が必要な状態かもしれません。
ただし、これらの症状があるからといって、すぐに病気や障害であると自己判断するのは危険です。
キョロキョロするという行動は、多くの人が程度の差こそあれ経験するものです。
大切なのは、その行動が本人の苦痛につながっていたり、社会生活を送る上で大きな障壁となっていたりする場合に、適切な相談先に繋がることです。
心療内科や精神科、あるいは発達障害者支援センターなどが、専門的な相談窓口となります。
挙動不審に思われる男性の悩み
キョロキョロする行動は、特に男性の場合、周囲から「挙動不審」「怪しい」といったネガティブなレッテルを貼られてしまうことがあります。
社会的に「男性は堂々としているべき」という無言のプレッシャーが存在するためか、視線が定まらない男性は、自信がなく、何かを企んでいるかのように見られがちなのです。
この悩みは、本人の意図とは全く異なる誤解を生むため、深刻なストレスの原因となり得ます。
例えば、電車の中でキョロキョロしているだけで、痴漢と間違われるのではないかという恐怖を感じる男性もいます。
また、職場で周囲を見渡していると、「仕事をサボって周りを監視している」とか「他人の粗探しをしている」などとあらぬ疑いをかけられるケースもあります。
本人は、ただ考え事をしていたり、次の仕事の段取りを考えていたりするだけかもしれません。
しかし、その行動が他者に不安や不信感を与えてしまうことで、人間関係に亀裂が入ることも少なくないのです。
このような誤解は、男性が抱える内面的な不安や警戒心をさらに増幅させるという悪循環を生み出します。
「普通にしているつもりなのに、なぜか怪しまれる」という経験が積み重なると、人と接すること自体が怖くなり、ますます行動がぎこちなくなってしまいます。
この悩みの根底には、自分の行動が他者にどう映るかを過剰に意識してしまう「自意識過剰」の状態があるとも言えるでしょう。
特に、思春期や青年期に、自分の容姿や振る舞いについて他人からからかわれた経験があると、そのトラウマが尾を引いて、成人してからも他者の視線を過度に気にする傾向が強まります。
キョロキョロする行動は、その不安から逃れるため、あるいは周囲からの評価を探るための行動であるとも解釈できます。
この悩みを抱える男性にとっては、まず自分の行動の背景にある心理を自己理解することが重要です。
そして、必要であれば、後述するような改善策やトレーニングを通じて、少しずつ自信を取り戻し、他者の視線を気にしすぎない心の強さを育てていくことが求められます。
女性に多い自信のなさの表れ

一方で、女性がキョロキョロする行動の背景には、自信のなさが大きく影響しているケースが多く見られます。
これは、自分の容姿や発言、能力に対する自己評価が低く、常に他者からの評価を気にしてしまう心理状態の表れです。
「変に思われていないか」「場違いな格好をしていないか」といった不安が、無意識のうちに視線を彷徨わせる行動につながります。
例えば、会議やプレゼンテーションの場で、発言を求められた際にキョロキョロしてしまう女性がいます。
これは、自分の意見に自信が持てず、聞き手の反応をうかがったり、誰かに助けを求めたりする心理が働いているためです。
視線を合わせることで、相手から否定的な反応が返ってくることを恐れているとも言えます。
また、パーティーや懇親会のような社交の場でも、この傾向は顕著に現れます。
誰と話していいかわからず、手持ち無沙汰になったときに、落ち着きなく周囲を見渡してしまうのです。
この行動は、「私はここにいてはいけない人間なのではないか」という疎外感や不安を紛らわすための、無意識の対処行動である可能性があります。
自信のなさは、他者との比較によって生まれることも少なくありません。
SNSなどで他人の華やかな生活や成功を目にする機会が増えた現代では、自分と他人を比較して落ち込み、自己肯定感を下げてしまいがちです。
その結果、「自分は他人より劣っている」という思い込みが強まり、人前で堂々と振る舞うことが難しくなります。
キョロキョロする行動は、そうした内面的な葛藤が外に現れたサインなのです。
自信のなさを克服するために
自信のなさが原因でキョロキョロしてしまう女性にとって、大切なのは自己肯定感を育むことです。
自己肯定感とは、ありのままの自分を認め、尊重する感覚のことを指します。
これを高めるためには、まず小さな成功体験を積み重ねることが有効です。
- 今日一日、笑顔で挨拶ができた
- 頼まれていた仕事を期限内に終えられた
- 作った料理が美味しくできた
どんなに些細なことでも構いません。
自分で自分を褒める習慣をつけることで、「自分にもできることがある」という感覚が少しずつ育っていきます。
また、自分の長所に目を向けることも重要です。
短所ばかりを気にするのではなく、「自分の好きなところ」「人から褒められたことがあるところ」を紙に書き出してみるのも良いでしょう。
客観的に自分の良い面を認識することで、自己評価が徐々に変わっていきます。
自信は一朝一夕に身につくものではありませんが、日々の小さな積み重ねが、やがては堂々とした振る舞いにつながり、キョロキョロする癖の改善にも繋がっていくはずです。
キョロキョロする人の直し方と接し方
- 仕事中にできる具体的な治し方
- 意識的に視線を定めるトレーニング
- 不安を軽減するストレス解消法
- 相手に安心感を与えるコミュニケーション
- キョロキョロする人との上手な付き合い方
仕事中にできる具体的な治し方

キョロキョロする癖は、特に仕事の場面で「集中力がない」「自信がなさそう」といったマイナスの印象を与えかねません。
しかし、意識的に対策を講じることで、この癖は改善することが可能です。
仕事中でも実践できる具体的な方法をいくつか紹介します。
まず、デスク周りの環境を整えることが重要です。
視界に入る情報が多すぎると、注意が散漫になり、キョロキョロする原因となります。
デスクの上には、現在取り組んでいる仕事に必要なものだけを置き、不要な書類や小物は引き出しにしまいましょう。
また、パーテーションを利用したり、壁向きの席に移動したりするなど、物理的に視界に入る刺激を減らす工夫も有効です。
次に、タスクを細分化し、一つひとつに集中する習慣をつけることです。
「ポモドーロ・テクニック」のように、25分間集中して5分間休憩するといったサイクルを繰り返すことで、集中力の維持がしやすくなります。
タイマーをセットし、その時間内は目の前のタスク以外に意識を向けないと決めるのです。
この小さな成功体験の積み重ねが、集中力への自信につながります。
会議や打ち合わせの場面では、意識的に発言者の目を見て話を聞くことを心がけましょう。
もし直接目を見るのが苦手な場合は、相手の眉間や鼻のあたりに視点を置くと、自然なアイコンタクトを保ちやすくなります。
また、手元にノートとペンを用意し、要点をメモしながら聞くことも、視線を安定させ、集中力を高めるのに役立ちます。
これは、話の内容を理解しようという積極的な姿勢を相手に示すことにもつながり、一石二鳥の効果があります。
さらに、自分の思考の癖に気づくことも大切です。
仕事中にふと別の考えが浮かんで意識が逸れたら、「今、集中が途切れたな」と客観的に認識し、再び目の前のタスクに意識を戻す練習をします。
これを繰り返すことで、注意が散漫になるパターンを自覚し、コントロールする力を養うことができます。
これらの方法は、すぐに完璧にできるものではありません。
しかし、日々の業務の中で意識的に取り組むことで、徐々にキョロキョロする癖は改善され、仕事のパフォーマンス向上にも繋がるでしょう。
意識的に視線を定めるトレーニング
キョロキョロする癖を根本的に改善するためには、日常生活の中で意識的に視線をコントロールするトレーニングを取り入れることが効果的です。
これは、視線を安定させるための筋力トレーニングのようなものです。
継続することで、無意識下でも視線がぶれにくくなります。
まず、自宅で簡単にできるトレーニングとして、「一点集中法」があります。
静かな部屋でリラックスした姿勢をとり、壁の一点や置物など、動かない対象物を一つ決めます。
そして、その一点をまばたきをしながら、まずは1分間、じっと見つめ続けます。
途中で他のことに意識がそれそうになったら、ゆっくりと呼吸を整え、再びその一点に意識を戻します。
慣れてきたら、時間を2分、3分と少しずつ延ばしていきます。
このトレーニングは、注意を一つの対象に留める訓練であり、集中力を高める効果が期待できます。
次に、外出時にできるトレーニングです。
電車やバスに乗っているとき、向かいの壁の広告や、窓の外の特定の建物など、目標物を決めて視線を合わせてみましょう。
周囲の人の動きや騒音に惑わされず、目標物から視線を外さないように意識します。
これは、様々な刺激がある環境下で集中力を保つための、より実践的なトレーニングとなります。
また、人と話す際のトレーニングも重要です。
前述の通り、相手の目を直接見るのが苦手な場合は、眉間や鼻、口元など、顔の特定の部分を見るようにします。
大切なのは、視線を一点に定める意識を持つことであり、相手を威圧するほど凝視する必要はありません。
会話の内容に応じて、相槌を打ちながら自然に視線を動かすことも大切ですが、基本的には相手の顔の周辺から視線を外さないように心がけます。
これらのトレーニングを日常的に行うことで、視線をコントロールする脳の回路が強化されます。
最初は意識しないと難しいかもしれませんが、習慣化することで、無意識のうちに視線が安定し、落ち着いた印象を与えることができるようになるでしょう。
不安を軽減するストレス解消法

キョロキョロする行動の多くは、内面的な不安やストレスが原因となっています。
したがって、癖そのものを治そうとするだけでなく、その根本原因であるストレスを効果的に解消することが、問題解決への近道となります。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、日常生活に組み込むことで、心の安定を取り戻しましょう。
まず、心身のリラックスに効果的なのが、深呼吸や瞑想です。
特に、腹式呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックス状態に導く効果があります。
やり方は簡単です。
- 楽な姿勢で座り、目を軽く閉じます。
- 鼻からゆっくりと息を吸い込み、お腹を膨らませます。
- 口からゆっくりと、吸うときの倍くらいの時間をかけて息を吐ききり、お腹をへこませます。
これを数分間繰り返すだけで、高ぶった神経が静まり、不安感が和らぐのを感じられるでしょう。
仕事の合間や寝る前など、毎日の習慣にすることをお勧めします。
次に、適度な運動もストレス解消に非常に有効です。
ウォーキングやジョギング、ヨガなどの有酸素運動は、「幸せホルモン」とも呼ばれるセロトニンの分泌を促し、気分を前向きにしてくれます。
激しい運動である必要はありません。
「心地よい」と感じる程度の運動を、週に数回、継続することが大切です。
運動中は、体の感覚に意識を集中させることで、頭の中の心配事から一時的に解放されるという効果もあります。
また、自分の感情や考えを紙に書き出す「ジャーナリング」も、頭の中を整理し、不安を客観視するのに役立ちます。
誰かに見せるものではないので、まとまりのない文章でも、ネガティブな感情でも、ありのままを書き出してみましょう。
文字にすることで、自分が何に不安を感じているのかが明確になり、漠然とした不安が具体的な課題へと変わります。
課題が明確になれば、対策を考えやすくなり、心の負担が軽くなることがあります。
これらのストレス解消法に加えて、十分な睡眠、バランスの取れた食事、趣味の時間を楽しむことなど、基本的な生活習慣を整えることも、心の安定には不可欠です。
自分を大切にケアする時間を持つことが、結果的にキョロキョロする行動の改善に繋がっていきます。
相手に安心感を与えるコミュニケーション
キョロキョロする癖を自覚している人にとって、他者とのコミュニケーションは緊張を伴うものかもしれません。
しかし、少しの工夫で、相手に安心感を与え、円滑な人間関係を築くことは可能です。
ここでのポイントは、視線以外の部分で、相手への関心や誠実さを示すことです。
まず、会話を始める際に、穏やかな笑顔で挨拶をすることを心がけましょう。
笑顔は、相手に対する敵意がないことを示す最も分かりやすいサインです。
たとえ視線が多少泳いでしまったとしても、最初にポジティブな表情を見せることで、相手は心を開きやすくなります。
次に、効果的なのが「相槌」と「反復」です。
相手が話しているときに、「はい」「ええ」「なるほど」といった相槌を適切なタイミングで打つことで、「あなたの話をしっかりと聞いていますよ」というメッセージを伝えることができます。
さらに、「〇〇ということですね」と相手の言ったことを繰り返したり、要約したりすることも有効です。
これは、話の内容を正確に理解しようとしている姿勢を示すだけでなく、自分の理解が正しいかを確認する機会にもなります。
また、視線を合わせるのが苦手でも、体の向きは相手の方に正対させることが大切です。
体がそっぽを向いていると、相手は「自分に興味がないのかな」「早く話を切り上げたいのかな」と感じてしまいます。
椅子に座っている場合は浅く腰掛け、少し前のめりの姿勢をとると、より積極的に話を聞いている印象を与えることができます。
質問を効果的に使う
自分の話をするのが苦手だったり、緊張してしまったりする場合は、相手に質問をすることも有効なコミュニケーション手法です。
ただし、矢継ぎ早に質問すると尋問のようになってしまうので、注意が必要です。
効果的なのは、相手の話した内容に関連するオープンクエスチョン(5W1H:When, Where, Who, What, Why, How)を投げかけることです。
例えば、「そのとき、どう感じましたか?」「もう少し詳しく教えていただけますか?」といった質問は、相手に更なる発言を促し、関心があることを示します。
相手が話している間は、自分は聞き役に徹することができ、視線をどうするかというプレッシャーも軽減されます。
これらのコミュニケーションの工夫は、キョロキョロするという行動を直接的に治すものではありません。
しかし、相手との間に信頼関係や安心感を築くことで、コミュニケーションに対する不安が減少し、結果として心に余裕が生まれ、落ち着いて人と接することができるようになるという好循環を生み出す可能性があります。
キョロキョロする人との上手な付き合い方

もし、あなたの周りにキョロキョロする人がいる場合、その人とどのように接すれば良いのでしょうか。
相手の行動を不快に感じたり、不安に思ったりすることもあるかもしれませんが、その背景にある心理を理解することで、より良い関係を築くことができます。
最も大切なのは、相手の行動を頭ごなしに否定したり、責めたりしないことです。
「なんでそんなにキョロキョロしているの?」「落ち着きがないな」といった直接的な指摘は、相手を深く傷つけ、萎縮させてしまいます。
前述の通り、その行動は本人がコントロールできない不安や警戒心から来ている場合が多いのです。
まずは、その行動の裏にあるかもしれない相手の繊細さや困難を想像し、受け入れる姿勢を持つことが重要です。
会話をする際には、穏やかで安心できる雰囲気を作ってあげることが効果的です。
高圧的な態度や早口は避け、ゆっくりとした口調で話しかけましょう。
また、個室や静かなカフェなど、周囲の刺激が少ない環境を選ぶと、相手はよりリラックスして話に集中しやすくなります。
相手が視線を合わせてくれなくても、気にしすぎる必要はありません。
視線が合わないからといって、あなたの話を無視しているわけではないのです。
むしろ、緊張のあまり視線を合わせられないのかもしれません。
あなたは、穏やかな表情で相手の顔のあたりを見ながら、話を続けてください。
相手の意見や感情を尊重し、共感的な態度で接することも、信頼関係を築く上で欠かせません。
相手が何かを話したら、まずは「そうなんですね」「大変でしたね」と受け止める言葉を返しましょう。
相手は、「この人は自分のことを理解しようとしてくれる」と感じ、少しずつ心を開いてくれるはずです。
もし、あなたが相手の行動を心配していて、何か助けになりたいと思うのであれば、タイミングを見計らって、優しく声をかけることもできます。
「何か悩み事でもあるの?」「もしよかったら話を聞くよ」といったように、相手を気遣う気持ちを伝えるのです。
ただし、相手が話したがらない場合は、無理に聞き出そうとせず、そっと見守る姿勢も大切です。
キョロキョロする人との付き合い方は、相手への思いやりと想像力が鍵となります。
行動の表面だけを捉えるのではなく、その内面にある心理に寄り添うことで、お互いにとって心地よい関係性を築いていくことができるでしょう。
- キョロキョロする人の多くは周囲への強い警戒心を持っている
- 過去のネガティブな経験が警戒心を強める原因になる
- 落ち着きがない行動は視線だけでなく体の動きにも現れる
- 一つのことに集中するのが苦手という特徴がある
- 行動の背景にADHDや不安障害が隠れている可能性も考慮する
- 自己判断はせず必要であれば専門家への相談が重要
- 男性は挙動不審と誤解されやすい悩みを抱えることがある
- 女性の場合は自信のなさが行動の主な原因となることが多い
- 仕事中はデスクの整理やタスクの細分化が改善に繋がる
- 一点集中法など意識的な視線のトレーニングは効果的
- 根本原因である不安を解消するためにストレスケアが不可欠
- 深呼吸や適度な運動は心の安定に役立つ
- コミュニケーションでは視線以外の要素で安心感を与える
- 相手と接する際は穏やかな雰囲気作りを心がける
- キョロキョロする人の行動を否定せず背景を理解しようと努める